旧約聖書【出エジプト記】岩波文庫版を読む|燃える芝と“全能者”の神話的ドラマ
キリスト教の聖典・聖書を、宗教書ではなく「作品」あるいは「文献」として読む視点から、岩波文庫版の『出エジプト記』を紹介する。学術的に翻訳・注解された本シリーズは、宗教的信仰とは異なる角度から旧約聖書を理解したい人にとって貴重な入り口となる。
●「創世記」についてのレビューはこちら → 旧約聖書【創世記】岩波文庫版・紹介〜作品としてのモーゼ五書
燃える芝と名を呼ばれる存在
旧約の「出エジプト記」は、ノアの洪水と並ぶほどドラマ性の高い物語を持つ。奴隷とされたイスラエルの民を、神の命によって解放へと導くモーゼの物語である。
エジプト王ファラオのもとで身分を偽って育てられたヘブライ人の子・モーゼ。やがて自らの出自に目覚めた彼は王宮を去り、さまよう中でシナイ半島・ホレブ山に辿り着く。そこで彼は、“燃える芝”の中から自分の名を呼ぶ声を聞く──「モーゼ、モーゼ」。
この場面は、ヘルメス文書『ポイマンドレース』の冒頭に非常に似ている。思惟に沈潜し、身体の感覚が停止した時、突如名を呼ばれる体験。デカルトの「我思う、ゆえに我あり(I think, therefore I am)」と並べても象徴的だ。
モーゼの返答「Here I AM(はい、ここにいます)」は、存在の宣言としての「I AM」に重なる。“名を呼ばれる”という出来事は、神話や哲学において、自己認識と存在の始まりを告げる鍵でもある。
●関連 → デカルト【哲学原理】より導き出される真実と認識〜ヘルメス思想との接点
十の災いと海の奇跡
神(全能者)から使命を受けたモーゼは、兄アロンとともにエジプトのファラオのもとに赴き、イスラエルの民の解放を要求する。だがファラオはそれを拒否する。
ここから“十の災い”がエジプトを襲う:
- ナイル川の水が血に変わる
- カエル・イナゴ・ぶよの大群
- 疫病、暗闇、雷火、そして全ての長子の死
最後の災いによってついにファラオは折れ、イスラエルの民は解放される。しかし、逃げ出した彼らを追いかけてきたエジプト軍に対し、神はさらなる奇跡を見せる。
モーゼは神から授かった杖を振るい、海を割って民を通す。乾いた海底を歩いて渡る民の背後で、エジプト軍が海に飲み込まれていく──圧巻のクライマックスだ。
後半と律法の章へ
前半の壮大な神話的物語に比して、後半は律法や聖所の設計・規定に関する記述が中心となる。読者によっては退屈に感じられるかもしれないが、宗教体系としてのイスラエルの成り立ちを理解するためには欠かせない部分でもある。
とはいえ、読み物として魅力が高いのはやはり前半部分。「創世記」と「出エジプト記」の二書が、モーゼ五書の中で特に親しみやすく読みやすい理由でもある。
“全能者”と弱き者のための神話
モーゼとアロンの背後にいた存在は、自然法則を超えてあらゆる奇跡を起こす「全能者」である。その圧倒的な力によって、絶対的権力者・ファラオに勝ち、奴隷とされた民を解放した。
もちろんこの話を“史実”として見るのは無理がある。アレクサンドロス大王のように実際に戦って勝利した英雄とは異なり、これは「強さのない者」にとっての救済神話だ。
読者がこの幻想的な物語を必要とするのは、自分が弱く、抵抗する術を持たないときなのかもしれない。そんな時、「海を割る神」の存在を思い出せばよいのだ。


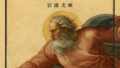

コメント