岩波文庫版『旧約聖書 創世記』論考
岩波文庫版『創世記』(関根正雄訳)は、旧約聖書の冒頭を飾る「モーセ五書(トーラー)」の第1巻である『創世記』を、日本語で精緻に訳出したものである。本書『創世記』は、天地創造から人類の起源、祖祖たち(族長)物語までを含む聖典であり、「罪を犯して神から追放を受けた人類とその人類に対する神の救い」が聖書全体を貫くテーマであるとすれば、まさにその出発点にあたる書物である。本稿では、岩波文庫版『創世記』の翻訳と注釈の特徴を踏まえつつ、その文献学的背景・神学的意義、正典(カノン)形成の歴史と異端文書との関係、さらに『創世記』本文の文学的特徴(創造、言葉、光、系譜)について、学術的トーンで論じる。
モーセ五書の文献学的価値と『創世記』
『創世記』は、モーセ五書(Pentateuch)の一書として伝統的に「モーセの著述」に帰されてきた。しかし近代以降の聖書文献学では、モーセ五書は複数の典拠資料が編集されたものであるとする四資料仮説(Documentary Hypothesis)が提唱され、旧約学における標準的学説となっているja.wikipedia.org。この仮説によれば、『創世記』にはヤハウィスト資料(J資料)やエロヒスト資料(E資料)、祭司資料(P資料)など異なる伝承層が識別される。例えば、創造物語が二つ存在する点(第1章の神(エロヒム)による宇宙規模の創造と、第2章以降の主なる神(ヤハウェ)による人間中心の創造)は、異なる伝承資料の融合と解釈されている。一方で、この仮説はあくまで仮説であり、細部には諸説あることにも留意が必要であるja.wikipedia.org。とはいえ、『創世記』を含むモーセ五書が様々な時代の伝承を集積・編集した文書であることは広く認められており、その文献学的価値は、古代イスラエルの宗教思想と社会背景を反映する歴史資料として極めて高い。
『創世記』の内容は天地創造から始まり、アダムとエヴァの物語、カインとアベル、ノアの洪水、バベルの塔といった原初史(創世記1章~11章)、そしてアブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフに至る族長史(同12章~50章)へと連なっていく。これらの物語は、単なる伝説ではなく、イスラエル民族の自己理解と宗教的アイデンティティの根幹を成す神話的歴史として位置づけられる。古代オリエントの創造神話や洪水伝説(例:バビロニアの『エヌマ・エリシュ』や『ギルガメシュ叙事詩』)との比較においても、『創世記』は多神教的・神話的世界観を脱し、「唯一神による創造と倫理的な人間観」という聖書特有の思想を打ち出している点で独自の価値を持つ。従って、『創世記』は文学作品としてだけでなく、古代中東世界の宗教思想史の文脈でも重要な研究対象であり、聖書の文献的・作品的価値を理解するうえで避けて通れない。
旧約聖書正典の形成と異端文書をめぐる歴史
『創世記』を含む旧約聖書が**「正典」として確立していく過程では、歴史的に様々な書物の取捨選択が行われ、同時に外典・偽典や異端的とみなされた文書との境界線が引かれた。ユダヤ教においては紀元1世紀末頃のヤムニア会議**(ヤブネ会議)で、ヘブライ語聖書の範囲が概ね確定されたとされるja.wikipedia.org。ユダヤ教正典はモーセ五書、預言書、諸書からなる24書で構成され、その本文は後代にマソラ学者によって整えられてマソラ本文として伝承されたja.wikipedia.org。
一方、ヘレニズム時代のエジプトでは、ヘブライ語聖書をギリシア語に翻訳した『七十人訳聖書(セプトゥアギンタ)』が編纂された(紀元前3世紀頃)。伝説によれば、プトレマイオス朝のエジプト王プトレマイオス2世は、その有名なアレクサンドリア図書館にユダヤ教の律法書を収蔵するため、72人の学者に命じてヘブライ語のトーラー(モーセ五書)をギリシア語訳させたというcojs.org。この翻訳事業によって生まれたセプトゥアギンタ(LXX)は史上初の聖書翻訳であり、以後ディアスポラのユダヤ人や初期キリスト教徒によって広く使用されたja.wikipedia.org。事実、新約聖書の著者たち(パウロを含む)は聖書引用の際に主にギリシア語訳聖書を用いており、キリスト教会は伝統的にこのギリシア語訳を旧約の正典とみなしてきたja.wikipedia.org。セプトゥアギンタにはヘブライ語聖書には含まれない幾つかの書(トビト記、ユディト記、マカバイ記、ソロモンの知恵、ベン・シラの知恵〈集会の書〉等)が含まれており、これらは後にラテン語訳ヴルガタにも継承されてローマ・カトリック教会の正典に組み込まれたcojs.org。他方、ユダヤ教はキリスト教と分離した後、セプトゥアギンタ以外の独自のギリシア語訳を求めるようになり、結果としてカトリックが正典とする一部の書物はユダヤ教からは排除され外典扱いとなった。16世紀の宗教改革期には、ルターがヘブライ語原典に基づきドイツ語聖書を翻訳した際、ヘブライ語聖典に含まれない書物を旧約から除外したため、プロテスタント教会の旧約正典はユダヤ教と同じ39書(※ユダヤ教の24書と配列は異なるが内容は同一)に限定されることになったja.wikipedia.org。一方カトリック教会はトリエント公会議(1546年)で旧約46書を正典と再確認し、プロテスタントが除外した書を「続編」として引き続き聖書に含めたja.wikipedia.org。このように、旧約聖書のカノン形成はユダヤ教からキリスト教、さらに教派間の歴史的経緯により変遷したため、正典の範囲や順序は一様ではない。正典と外典の峻別は必ずしも当初から明確だったわけではなく、歴史の中で正統(オーソドクシー)と異端(ヘレシー)の攻防を経て形作られたものである。
とりわけ、紀元1~3世紀の地中海世界では、多様な宗教思想が聖書解釈に影響を及ぼした。例えば、初期キリスト教の周辺にはグノーシス主義と呼ばれる神秘主義的潮流が現れ、『創世記』の創造物語を大胆に異端的に解釈し直した。webfrance.hakusuisha.co.jpグノーシス主義の宇宙論では、この世界は至高神から流出した下位の存在であるデミウルゴス(造物主。別名ヤルダバオート)によって創造された物質世界であり、旧約聖書の創造神ヤハウェはまさにこのデミウルゴスに相当するものと見なされたwebfrance.hakusuisha.co.jp。彼らによれば、デミウルゴスは無許可に世界を作った不完全な存在であり、人間は本来至高の神的世界(プレローマ)の霊的要素を持ちながら肉体という牢獄に閉じ込められている。ゆえに物質世界は本質的に悪であり、人間が救済されるには秘教的な知識(グノーシス)によって霊的本源に目覚める必要があるwebfrance.hakusuisha.co.jp。このような二元論的神話に立つグノーシス派は、『創世記』第三章の楽園物語さえも正統的解釈と正反対に捉えた。すなわち、エデンの園で人類を堕落させた蛇について、教会の正統教義がそれを悪魔の象徴とみなしたのに対し、グノーシス派では「人類に禁断の木の実を勧めて霊的知識を授けた蛇こそ善なる存在の象徴である」と逆転評価したのであるwebfrance.hakusuisha.co.jp。彼らにとっては、無知のまま盲目的服従を強いる創造主(デミウルゴス)の支配から人間を解放した知恵の蛇こそが救いの使者であり、この蛇は自己の尾を咥える輪(ウロボロス)として再生と完全性を象徴し、ひいては復活したキリストの暗喩ですらあったwebfrance.hakusuisha.co.jp。無論、こうした解釈は当時の教会から異端として厳しく退けられ、2世紀の教父エイレナイオスが『異端反駁』を著してグノーシス思想を批判・排斥したことはよく知られる。
グノーシス主義と並んで古代末期に台頭したヘルメス文書(コルプス・ヘルメティクム)もまた、聖書正典には加えられなかった外典的思想の宝庫である。ヘルメス文書群は、ヘレニズム期エジプトのアレクサンドリアにおいて、ギリシア神のヘルメスとエジプト神のトートを同一視したヘルメス・トリスメギストス(三重に偉大なヘルメス)に帰せられる啓示録として編まれた神秘哲学文書の総称であるnote.com。その内容は多様で占星術、錬金術から哲学的対話篇まで含まれるが、思想的にはプラトン主義・ピタゴラス主義、新プラトン主義、さらにグノーシス主義やゾロアスター教の教説まで混淆した複合思想となっているnote.com。ヘルメス文書の中でも特に著名な冒頭書簡「ポイマンドレース」には宇宙創造の神話が語られるが、そこでは至高神とは異なる創造神(デミウルゴス)によって宇宙が作られ、惑星の霊的支配者たるアルコーンが運命として人間を拘束しているという、一種グノーシス的な反宇宙論観が示されているnote.com。このようなヘルメス文書は一神教の教義(一元的な創造論)と相容れない側面を持っていたため、キリスト教やユダヤ教において公的な聖典とは認められず秘教として細々と伝承されたkotobank.jp。結果として、その正典化はなされず、中世以降はイスラム圏やルネサンス期のヨーロッパにおけるオカルティズムの潮流の中で再評価されるに留まったkotobank.jpkotobank.jp。
以上のように、旧約聖書の正典成立の陰には、グノーシス文書やヘルメス文書をはじめとする多様な外典・異端の思想が存在し、それらとの思想的対決を経て正統教義と経典の枠組みが形作られていった歴史がある。岩波文庫版『創世記』の巻末解説や訳注においても、こうした神学的・歴史的背景への言及がなされている。例えば、『創世記』本文中の語句や概念について、同時代の他民族の神話資料や第二神殿期ユダヤ教文献との比較が示され、聖書正典の位置づけが相対化して論じられている箇所もある。正典と異端の問題は、単に歴史的興味にとどまらず、聖書テキストそのものの理解(何が正統な解釈か、どのテクストが権威を持つか)に関わる重要な論点であり、岩波版の詳細な注釈は読者にこの点を考察させる助けとなっている。
岩波文庫版『創世記』の翻訳と注釈の特徴
岩波文庫版旧約聖書『創世記』の日本語訳は、聖書学者・関根正雄(1912–2000)によって行われた。関根は内村鑑三の無教会派に属した人物であり、戦後日本における旧約聖書の個人訳に先鞭をつけた一人であるnote.com。岩波文庫では戦後に塚本虎二訳の新約聖書(福音書など)が刊行されていたが、旧約聖書については関根正雄訳による分冊版が1950年代以降順次出版されたnote.com。『創世記』岩波文庫初版は1956年に刊行され、その後1967年に改版されて現在の体裁(青801-1番)となっているnote.com。本文は旧約聖書ヘブライ語原典に忠実に訳されており、日本語として明晰でありながら原文のニュアンスをできるだけ伝える方針が採られている。例えば、固有名詞や神名の訳語選択、韻律や語呂の再現などにも配慮が見られ、文語訳聖書や口語訳聖書とは一線を画した学究的な翻訳となっている。
岩波文庫版『創世記』の最大の特徴の一つは、その詳細な訳注と解説である。関根訳旧約聖書は、後に出版された教文館版の全訳聖書に比べても注の充実度が高く、資料的価値が優れていると評価されているnote.com。各章各節に対応した注釈が巻末または欄外に付されており、語句の原義、異文(写本間の相違)、他の経典との関連、神学的含意などが丁寧に解説されている。この訳注は非常に学術的で専門性が高いため、「解説が難しすぎてむしろ本編より難解」と感じる読者もいるほどであるamazon.co.jp。しかし、それこそが岩波版の真骨頂であり、宗教や聖書について一定の知識を持つ読者にとっては、原典批判や歴史的背景の情報源として極めて有用である。事実、新約聖書学者の田川建三も、関根訳の岩波旧約聖書は注釈が豊富で研究資料として優れていると述べているnote.com。
加えて、岩波文庫版『創世記』には巻末に総論的な解説が収録されている。ここでは『創世記』の成立過程、思想的特徴、ユダヤ教・キリスト教における位置づけなどが論じられ、聖書全体の中での創世記の役割が概観されている。おそらく執筆者は関根正雄自身か、あるいは同時代の聖書学者によるもので、「聖書の思想と歴史」といったテーマで神学的・歴史的背景を詳説するエッセイになっていると推測される(実際、中央公論社『世界の名著12 聖書』所収の前田護郎による同題の論考など、当時の聖書学者による解説エッセイが知られるnote.com)。この解説部分と訳注のおかげで、岩波文庫版『創世記』は単なる邦訳聖書に留まらず、一種の聖書学の入門書・研究書としての価値をも有している。翻訳そのものの正確さと相まって、読者は原典に即した理解を深めることができるだろう。
『創世記』の文学的特徴:創造と言葉、光と系譜
最後に、『創世記』本文の文学的特徴について、いくつかのキーワードに沿って検討する。岩波版訳注は、こうしたテキスト内部の構造やモチーフにも目配りしており、それらを踏まえて読むことで作品としての『創世記』の深みが見えてくる。
「創造」と「言葉」:言語による宇宙の秩序化
『創世記』冒頭に記される天地創造の物語(第1章)は、極めて簡潔な言葉でコスモスの起源を描写する。その書き出しは「初めに、神は天地を創造された。」(創世記1:1)という威厳ある一句で始まり、混沌と闇が支配する原初の状態から、神の一連の創造行為が展開していく。特筆すべきは、神が世界を創造する手段として**「言葉」を用いている点である。すなわち「神は言われた。『光あれ。』こうして、光があった。」(創世記1:3)というように、神の発する言(ことば)そのものが創造の原動力として機能し、混沌に秩序をもたらしてゆくのである。言葉によって世界が存在へと呼び出されるというこのモチーフは、ヘブライ語聖書の思想の核を成すと同時に、西洋思想全般にも大きな影響を与えた。新約聖書『ヨハネ福音書』の書き出し「初めに言があった。言は神と共にあった。言は神であった。」(ヨハネ1:1)は、この創造における言葉の神学的意義を背景に、キリストを万物を成したロゴス(言)として位置づけるものであると解される。また、日本語において「言霊(ことだま)」の思想が古来重視されてきたことに照らしても、『創世記』の「言による創造」のコンセプトは普遍的な関心を呼び起こす。岩波版の訳文は、この箇所を簡潔な日本語で「神は言われた『光あれ。』そして光があった。」と訳し(例えば新共同訳聖書とほぼ同様の訳出)、原文の持つリズムと威厳を損なわず伝えている。訳注では、ヘブライ語で「言った」に当たる動詞 amar の用法や、「光(オール)」という語の象徴的意味について詳しい説明が付され、単なる逐語訳を超えて神学的解釈**への手がかりが提示されている。つまり、言語による創造という普遍テーマに対し、読者が多角的に思索できるよう配慮されているのである。
「光」と「闇」:秩序と善の象徴
上述のように創造第一日目に現れる**「光」は、『創世記』において極めて象徴的な要素である。興味深いことに、創世記1章では光は天地創造の最初に創られるが、太陽や月などの光源となる天体が創造されるのは第四日目である(創世記1:14-19)。この構成は、光を単なる物理的現象以上のもの―すなわち神によってもたらされた秩序と善の象徴**―として描いていることを示唆する。実際、神は光を見て「良し」と評価し、光と闇を分けて昼と夜と名づけた(創世記1:4-5)。闇は混沌や悪のメタファーとして、多くの宗教的テクストで扱われるが、創世記では神がまず光を創り出すことで闇に境界を設定し、世界に秩序を確立したと描かれる。この「光と闇の分離」は、後のヨハネ福音書冒頭で「光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった」(ヨハネ1:5)と神学的に言及されるように、救済史における善と悪、啓示と無知の対立を象徴する主題へと発展していく。
岩波文庫版『創世記』の訳注では、創造における「光」に関して哲学的・神学的な背景にも触れている。例えば、古代ユダヤ教の思想家フィロンが創造論をプラトン哲学と調停しつつ**「理性的光」**を論じたことや、グノーシス思想で光と闇の対立が宇宙論の骨子となったことなど、聖書本文の行間を埋めるような知見が提供されている。読者は単に物語として光の創造を読むだけでなく、その背後にある普遍的なシンボリズム—光=善・秩序、闇=悪・混沌—を理解することで、『創世記』の叙述が持つ深い象徴性を味わうことができるだろう。
「系譜」と物語構造:歴史を貫く人間の物語
『創世記』には幾つかの系譜(ジネアロジー)リストが挿入されており、物語全体の構造を形作っている。第5章ではアダムからノアまでの人物系譜が詳細に述べられ、「アダムは百三十歳になって、自分にかたどり、自分のかたちのような男の子を生み、その名をセツと名づけた。」(創世記5:3)churchofjesuschrist.orgといった形で、各人の年齢・子孫・寿命が淡々と記録されている。この系譜は単調にも思える記述であるが、神学的・文学的には重要な役割を担っている。それは、楽園追放後に始まる死すべき人類の歴史が、断絶することなくアダムからノア、さらにアブラハムへと連続していくことを示し、神の救済計画が歴史を貫いて展開していくことを読者に意識させる点である。すなわち、罪を犯したアダム夫妻から始まった人類も、子孫を生み繁栄し(「産めよ、増えよ、地に満ちよ」創世記1:28)、神はその歴史の中でなお働きかけを続ける—そうした希望のラインを系譜記事は象徴している。
また、『創世記』には「〜の系譜は次のとおりである」(êlleh tôlĕdōṯ エッレ・トレドート)という定型句が全体を区切るように反復して登場する(創世記5:1, 6:9, 10:1, 11:10, 11:27等)。これはヘブライ語で「これが…の歴史である」とも訳せる表現で、創造記事後に「これは天と地が創造された時の由来である」(2:4)と用いられているのをはじめ、物語の章見出しのような機能を果たすwordproject.org。この**「トルドット構文」*によって、『創世記』全体が10の区分(天地、アダム、ノア、ノアの子、セム、テルア、イシュマエル、イサク、エサウ、ヤコブの歴史)に整理されているとの指摘もある。つまり、創世記記者は系譜という形式を用いて、膨大な年代記的伝承を秩序立てつつ、最終的にイスラエルの祖先ヤコブ(イスラエル)の物語へと収斂させているのである。岩波版訳注では、この繰り返し出現する「〜の系譜」*という句に着目し、その都度原語の意味や物語区分上の意義が解説されている。例えば、「系譜 (tôlĕdōṯ) とは単に血統記録ではなく『由来・生成の記録』を意味し、ここでは後続する叙事全体を指し示す」という趣旨の説明があり、読者は物語構造を意識しながらテキストを読み解くことができるよう工夫されている。
さらに系譜記事から得られる含意として、人間の寿命の漸減というテーマが指摘できる。『創世記』第5章の系譜ではアダムは930年生き、ノアも950年生きたとされるが(創世記5:5, 9:29)、やがて創世記11章の系譜では寿命が数百年単位に短縮し、族長たちに至っては百数十年程度になっていく(例:アブラハム175年、イサク180年、ヤコブ147年)。これは、創世記6:3で神が人の一生を120年に制限すると宣言したことの漸次的な実現を示唆しているとも読め、罪により**「死」が人類史に浸透していく過程**を反映するとの解釈もある。岩波版の訳注でも、この寿命短縮について触れ、人間の有限性と死の問題が聖書全体のテーマ(創世記から啓示録に至るまで)であることを読者に喚起している。このように細部にわたる考察を促す注釈により、『創世記』の系譜という一見退屈にも思える部分が、神学的含意を持つ重要なテクストであることが浮かび上がるのである。
おわりに
岩波文庫版『旧約聖書 創世記』は、その正確な翻訳と充実した注釈によって、単なる聖書の日本語訳を超えた学術的レビューとも言える内容を提供している。本稿で論じたように、『創世記』は文献学・歴史学的側面から見ても、神学・思想的側面から見ても、極めて豊かなテキストである。その成立には複数資料の編集という背景があり、古代の多神教的神話世界に対して一神教的世界観を打ち立てた意義があり、また後代の正典形成や異端思想との緊張関係の中で解釈史が紡がれてきた。本書の訳注・解説は、そうした広範な知見を盛り込み、読者に深い理解を促す。『創世記』本文そのものも、創造における言葉と光のモチーフや、人類史を繋ぐ系譜構造など、文学作品として精巧に構成されていることを見てきた。岩波文庫版はこれらを的確に捉え、日本語学術文体で明晰に表現している。
宗教に通暁した読者にとって、岩波版『創世記』は神学的・歴史的背景に思いを致しつつ原典を読み解く格好の案内役となろう。創造主による「光あれ」の一言が闇を切り裂いた太古の光景から、人類の系譜が紡ぐ歴史ドラマまで、関根正雄の翻訳と言及によって新たな意味の光が当てられている。webfrance.hakusuisha.co.jpまさに聖典そのものへの敬意と、研究者の厳密なまなざしが融合した一冊であり、『創世記』という不朽の古典に現代の読者が向き合うための優れた学術的リソースであると評価できる。

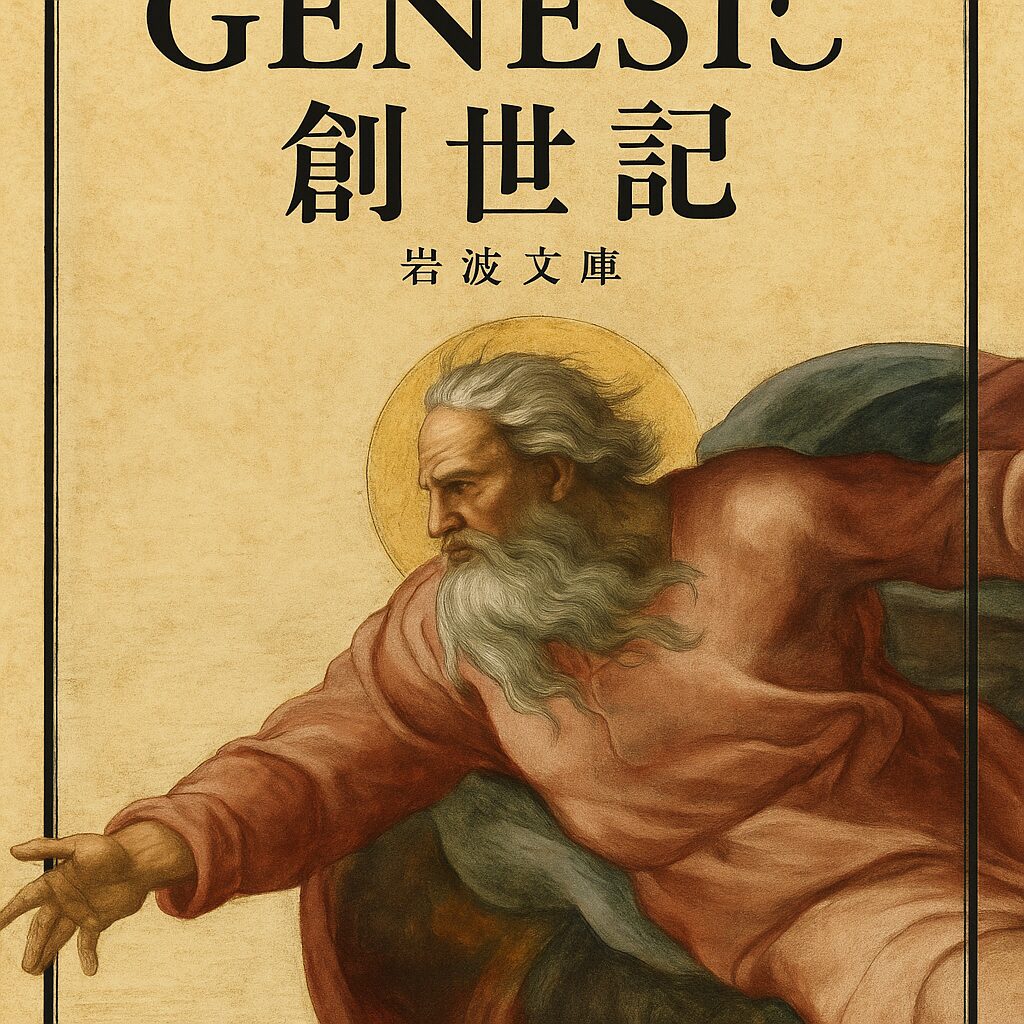


コメント