【夏目漱石】『道草』紹介・感想|自伝風読み切りに垣間見える苦悩と素顔
あらすじ|書斎から一歩外へ
夏目漱石の『道草』は、晩年に完成した自伝的小説である。たとえば『硝子戸の中』が、病弱な身体を抱えた漱石が自室にこもりながら綴った“内向き”な作品だとすれば、『道草』はもう少し外に開かれた――とはいえやはり、漱石独特の自己省察の色が濃い作品だ。
『硝子戸の中』は世相を見渡す随筆かと思いきや、実際には過去の記憶や身辺雑記が大半を占める。『道草』も同様で、しかもさらに個人的で、やや重たい。読者によっては肩透かしを食らったような気持ちになるかもしれない。
風流を求めて
筆者としては『永日小品』や『思い出すことなど』『夢十夜』といった作品に見られる、漱石の気取らぬ“風流”に惹かれてきた。しかし『道草』にはそれがほとんど感じられない。親戚との金銭トラブル、気に食わない妻との軋轢……。延々と続く悶々とした心情描写は、どこか高校生の思春期日記のようにも思える。
そんな読み疲れるような感覚に襲われ、「これは選択を誤ったか」と正直思ったほどだ。
唯一の盛り上がり|“父になる漱石”の姿
それでも後半、物語はわずかに明るさを取り戻す。連載終盤、心に少しゆとりが生まれたのか、いつもの軽妙な語り口が戻ってくる。そして物語にひとつの山場が訪れる。――それは、妻が出産するシーンだ。
産婆が間に合わず、暗がりの中で漱石自らが赤ん坊を受け取る。生まれたての子を「プリプリしていて寒天のようだ」と描写する感性が面白い。さらに息をしていないのではないかと焦り、棚から脱脂綿を引っつかんで赤子の上に山のように積み上げる。
後に産婆が来て事なきを得るのだが、このエピソードからも、時代の素朴さと切実さが伝わってくる。なお「お産で死ぬかと思った」という妻の台詞は、『夢十夜』の第一夜を思い起こさせる。
まとめ|苦さと滑稽さ、そのあいだに
では漱石作品に私たちは何を求めるのか? ――それは、風流とユーモア、そして気取りのなさである。三島由紀夫や谷崎潤一郎のような華麗な文体美とは対照的に、漱石の文章はどこか“にじむ”ように染み込んでくる。
彼は「偉くなろう」とはせずに、自然体のまま、まるでワニが胃の内容物を吐き出すように、苦悩や思索を文章にしていった。そしてそれが、結果的に芸術作品として昇華されたのだと思う。
その原点が『吾輩は猫である』であり、短編では『倫敦塔』『一夜』などがある。そしてこの『道草』を読むことで、その滑稽さの影にあった“実人生の苦さ”が、より鮮やかに浮かび上がってくる。


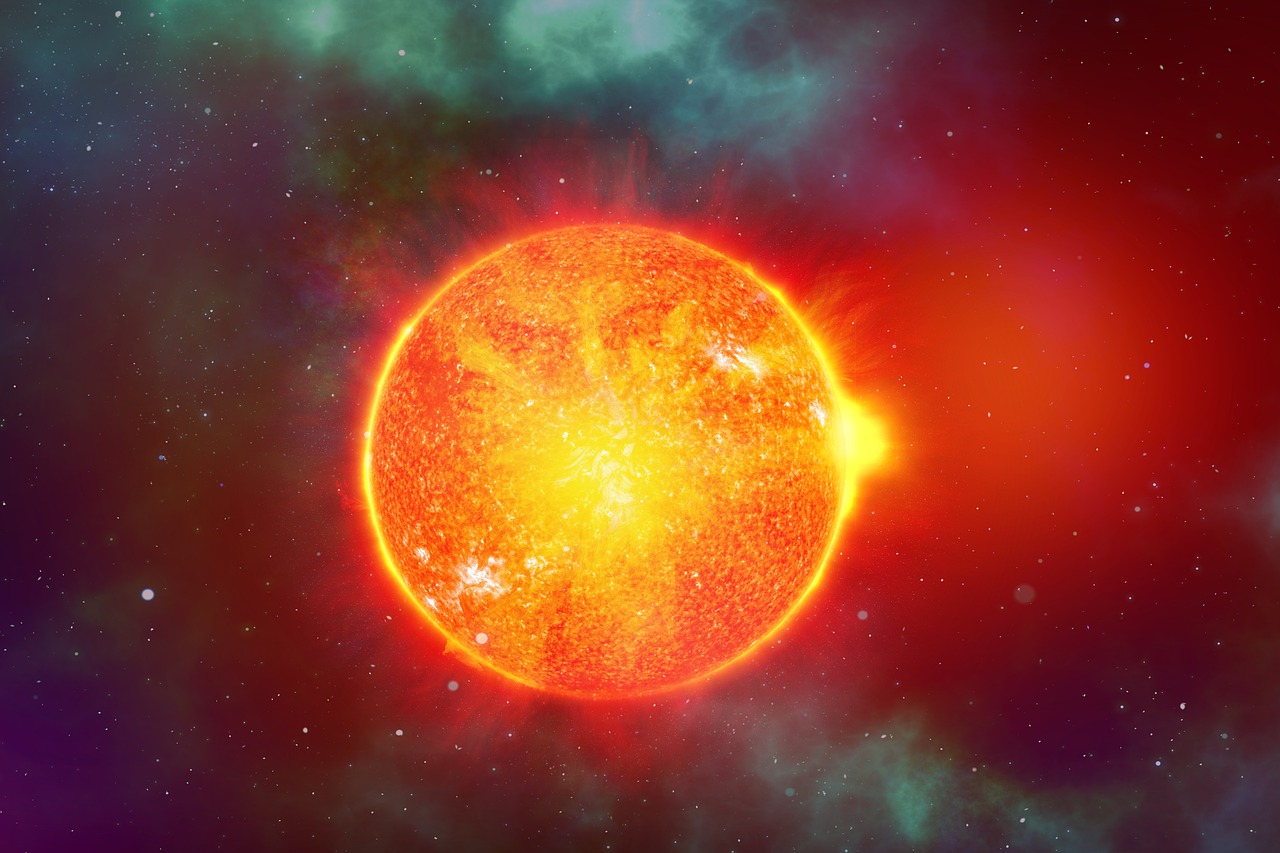

コメント