ジョルジュ・バタイユ「エロティシズムに関する逆説」「エロティシズムと死の魅惑」内容紹介・レビュー
概要
角川文庫版『マダム・エドワルダ』には、バタイユの処女作「眼球譚」をはじめ、短編小説「マダム・エドワルダ」「死者」が収録されている。だが、真に注目すべきは巻末に添えられた二つのテキストだ──「エロティシズムに関する逆説」という短い論文と、「エロティシズムと死の魅惑」という講演討論会の記録である。
本稿ではこの二つ、特に1957年にパリで行われた講演記録に焦点を当てつつ、バタイユのエロティシズム観の中核を浮かび上がらせたい。
●「眼球譚」の紹介記事はこちら →
<a href=”https://saitoutakayuki.com/syousetsu/batille-oeuf/”>ジョルジュ・バタイユ【眼球譚】の内容カンタン解説〜レビュー・紹介</a>
講演:エロティシズムとは何か
1957年2月12日、パリのレンヌ街44番地「セルクル・ウヴェール」という文化団体にて、バタイユは“エロティシズム”をテーマに講演を行った。聴衆の中には、アンドレ・ブルトンやハンス・ベルメールなど著名なシュルレアリストたちの姿もあったとされる。
講演内容は、バタイユ自身が後に「エロティシズムに関する逆説」で述べた思想と軌を一にする。性とは本質的に“死”の領域と結びつくものであり、その快楽はタブーの侵犯を通してしか得られない──バタイユの一貫した主張である。
討論会では、バタイユの論に対する賛否が飛び交い、その議論の濃度と緊張感は、まるで生中継で見ているかのような臨場感を読者に与える。
黒いエロスと「光の側」
この講演の背景には、アンドレ・ピエール・ド・マンディアルグによる短評「黒いエロス」の存在がある。マンディアルグはこの評論の中で、バタイユの思想を擁護し、“愛”や“自由”、“歓喜”といった軽薄な言葉でエロティシズムを語る風潮を激しく批判している。
●「黒いエロス」の紹介はこちら →
<a href=”https://saitoutakayuki.com/hyouron/eros-noir/”>マンディアルグの【黒いエロス】〜見直されなければならないエロティシズムの定義</a>
エロティシズムとは死と隣接する暗黒の世界だ。それを「愛と光」にすり替えようとするのは、欲望の根源にある恐怖や禁忌を見ないふりする欺瞞である──バタイユもマンディアルグも、そう訴えている。
性の“解放”とその末路
戦後フランス──大量消費社会の始まりとともに、性のタブーが次々と取り払われていく時代。バタイユが講演を行っていた頃は、ちょうどマンディアルグが『大理石』を発表した1953年以降の雰囲気と重なる。
●『大理石』の紹介はこちら →
<a href=”https://saitoutakayuki.com/syousetsu/mandiargues-marbreiii/”>【マンディアルグ】小説「大理石」に隠されたシュルレアリスティックな秘密</a>
だが、性の“自由”が実現した現代において、果たして我々は幸福になっただろうか?──否。大量のポルノはあふれ、恋愛は臆病となり、自由な性交の果てに孤独が深まる。あまつさえ「恋の情熱」は法によって去勢され、思春期の衝動すら抑圧の対象となった。
この「自由」は、本当に自由だったのか?
それとも、規制と萎縮による“新しい不自由”だったのか?
歴史と倫理のねじれ
現在ではタブー視されることも、歴史的には異なっていた。バタイユの名の下にここで敢えて触れるならば、かつて結婚は「神聖な絆」として十代前半の少女との婚姻すら許された。エドガー・アラン・ポーは13歳のヴァージニアと結婚し、聖アウグスティヌスは10歳の少女と婚約した。
●ポーの特集記事はこちら →
<a href=”https://saitoutakayuki.com/matomekizi/matome-de-poe/”>【エドガー・アラン・ポー短編作品】オリジナル・レビューまとめ</a>
倫理の変遷は文化の反映であり、断罪すべきは個人よりも制度そのものだろう。バタイユが見つめていたのも、人間社会が「性」という根源的欲望をどう取り扱い、どう歪め、どう隠してきたかという構造そのものであった。
まとめ:エロティシズムの本質とは
「エロティシズム」とは、そもそも文学と芸術の語彙であった。しかしそれが大衆社会に飲み込まれるとき、その言葉は意味を失い、安易な性愛の代名詞と化す。性の楽園を夢見た人類は、気づけば性の奴隷制度の中で踊らされていた──そんな皮肉が、バタイユの声から聴こえてくる。
清潔なベッドで微笑む裸の恋人たちの映像を見て、あなたは何を感じるだろう?
それが“エロティシズム”だと呼ばれるとき、バタイユならこう叫ぶだろう。
「そうじゃない、そうじゃないんだ!」



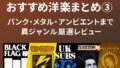
コメント