 哲学
哲学 【バフォメットとは何か?】悪魔と山羊の象徴・角の意味を読み解く
【悪魔と山羊】バフォメットの角はなぜ象徴なのか?中世ヨーロッパの魔女裁判、あるいは近代オカルティズム、あるいはブラックメタルのCDジャケット──そこに必ずといっていいほど現れるのが、山羊の頭をもった謎めいた存在、「バフォメット」である。この...
 哲学
哲学 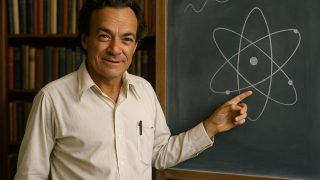 評論
評論 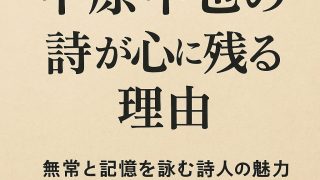 詩
詩  哲学
哲学  評論
評論 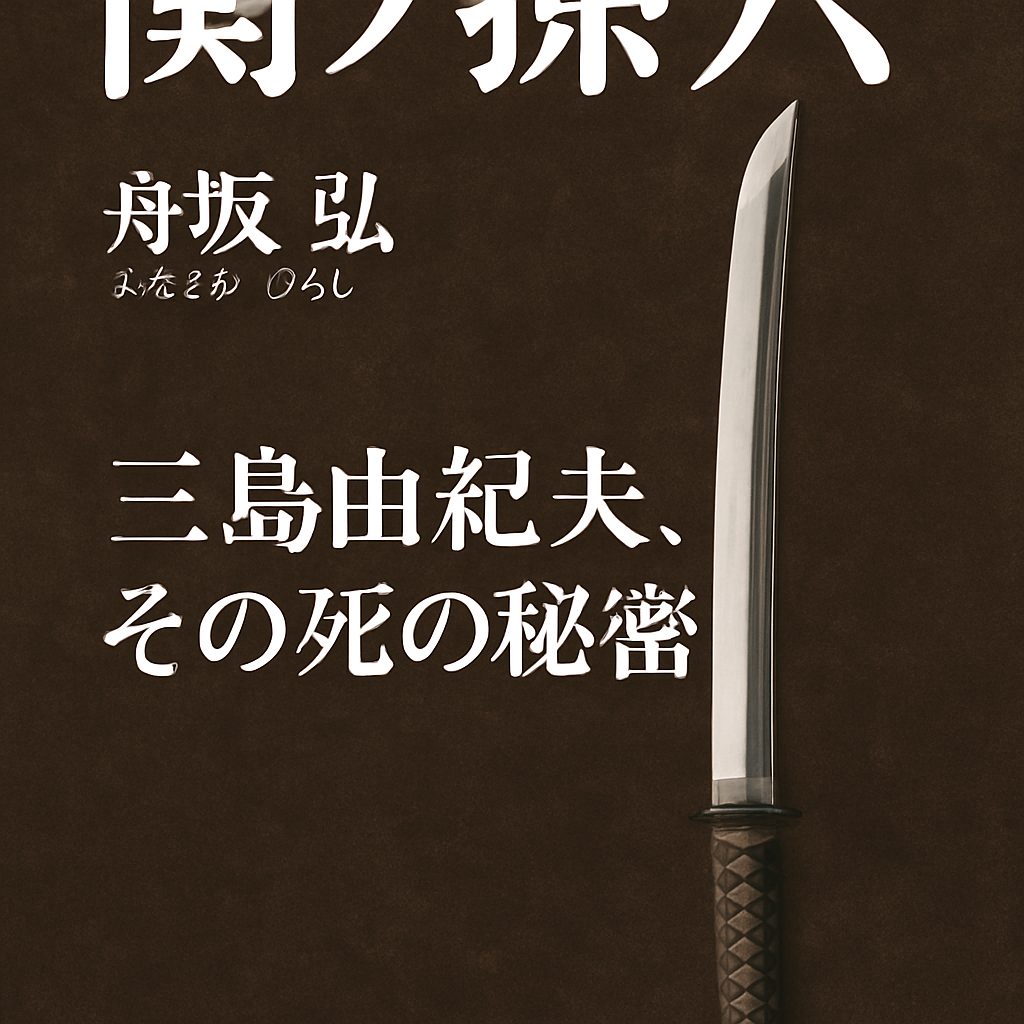 評論
評論 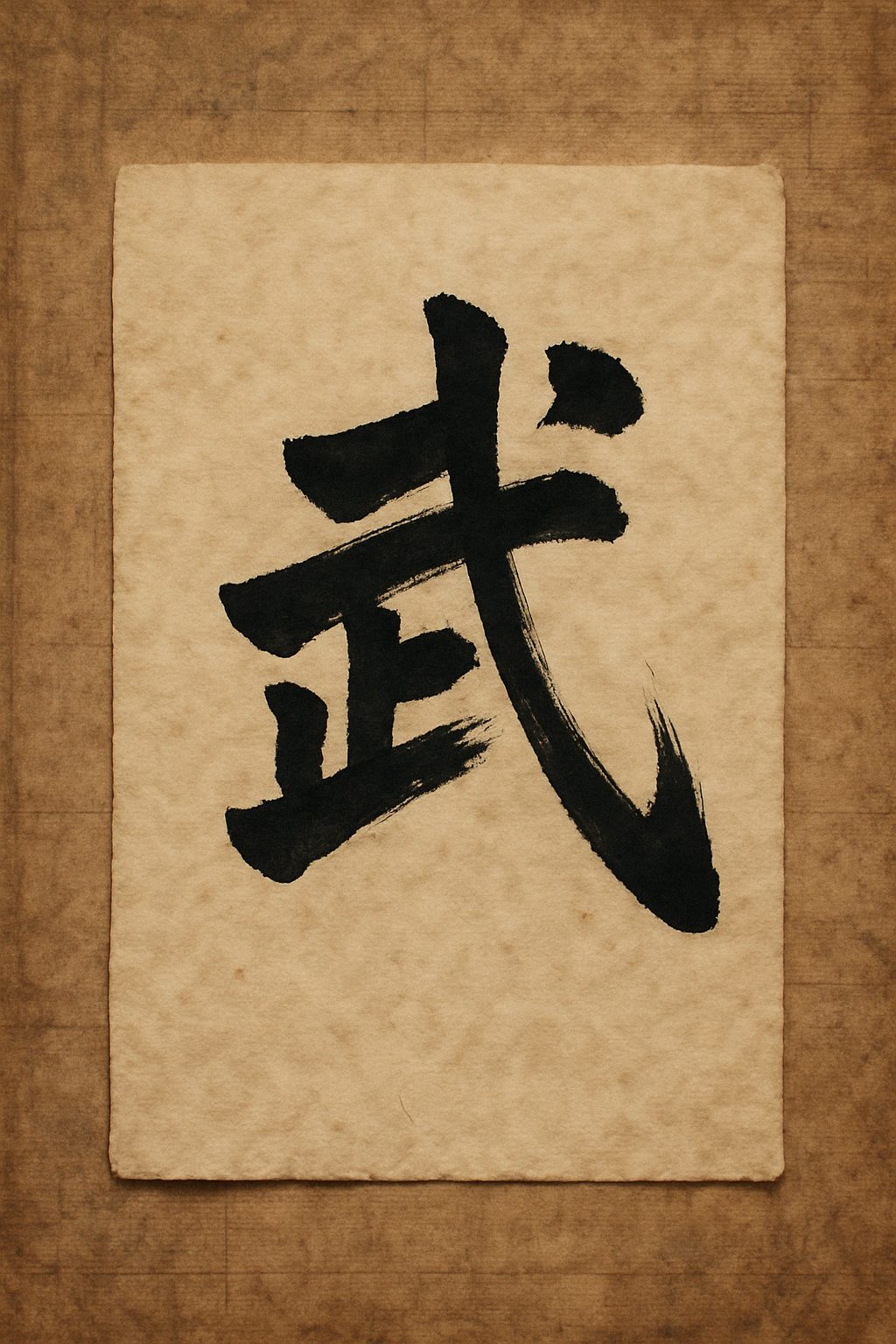 評論
評論  評論
評論  評論
評論  評論
評論