1. 作品概要|作家になろうとしなかった天才
あらためて夏目漱石を読み返すと、その作品の深さと洒脱さに驚かされる。以前「漱石は偉くなろうとしなかった唯一の作家」と自分でも書いたことがあるが、その印象はいまだに揺るがない。
たとえば、弟子の芥川龍之介は生涯をかけて文体を模索したが、漱石はむしろ“なろうとして”作家になったのではない。『吾輩は猫である』は、39歳という遅いスタートで発表された処女作であり、まったく作家らしい「成功ルート」を意識していない。それにもかかわらず、この作品は今なお読まれ続けている。
新潮文庫の解説によれば、本作は正岡子規主宰の雑誌「ホトトギス」に掲載されたところから始まり、その人気によって連載形式で続いていった。つまり、偶然と必然が交差するかたちで、漱石文学はここに産声を上げたのだ。
2. 作家と暮らし|貧しさの中の知性と観察力
朝日新聞の専属作家として地位を確立していく漱石だが、本人にはその“成功”に対する自負はなかったようだ。むしろ日常の記述には、慎ましく質素な生活ぶりがにじむ。
「貯金がない」と率直に語り、家のつくりも粗末であると描写する。そんな家を、主人公の“吾輩”――つまり猫――が気ままに歩き回る。その視点で人間社会の滑稽さや矛盾を軽やかに描いていくスタイルが本作の魅力である。
猫がまるで作家の分身のようにふるまう場面もあれば、純粋に外部からの観察者として描かれることもある。特に登場人物たちの掛け合いが落語のように滑稽で、時代を超えてユーモアが伝わってくる。
電気もテレビもない時代。それでも火鉢を囲み、朝日を吸い、談笑する生活の描写には、日本人独特の渋味と風流が確かにある。
3. 猫の最期|滑稽と無常の境界線
本作のラストで猫が死ぬ――この事実を知らない読者も多いのではないだろうか。連載形式のため一話ごとは短いが、最終話は“特別編”のように長く、登場人物が勢揃いする宴会のような賑やかさを見せる。
そのどたばたが収まり、日が暮れ、火鉢の中には吸い殻が散乱し、猫はふとビールを飲んでみたくなる。そしてふらついた末に水瓶に落ちてしまう。
もがきながらも、やがて「無駄なあがきは止そう」と観念し、「南無阿弥陀仏」を唱えて静かに沈んでいく……そのラストは、まさに“無常観”の象徴であり、漱石の死生観が静かに、しかし力強く滲んでいる。
4. 感想|滑稽さの奥にある死と人生の深み
『吾輩は猫である』の結末は、ユーモア一辺倒の作品ではないことを教えてくれる。人の死が日常に近かったこの時代、作家自身も常に死を意識しながら生きていたことが読み取れる。
この作品は文庫で500ページ以上にもなるが、その分厚さに見合うだけの知的興奮と、笑いと、しみじみとした人生観が詰まっている。「誰が評価しようがしまいが、これは傑作だ」――と感じられる稀有な一冊だ。
漱石から学んだことは多い。漢詩の深さ、日本的風流へのまなざし、肩肘張らぬユーモア、そして死に対して淡白であるという境地。処女作である本作を起点に、『道草』『倫敦塔』『一夜』と読み進めることで、漱石という人物の核心が見えてくるように思う。

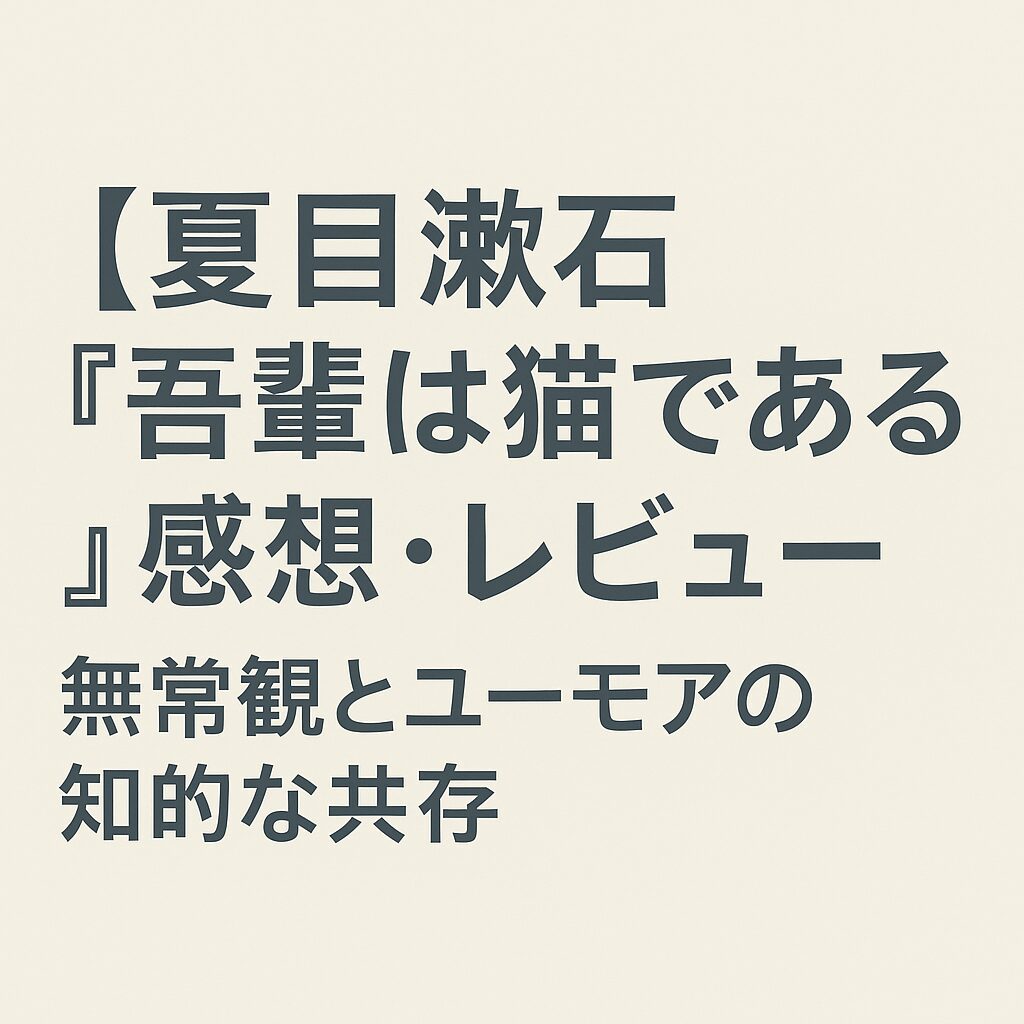

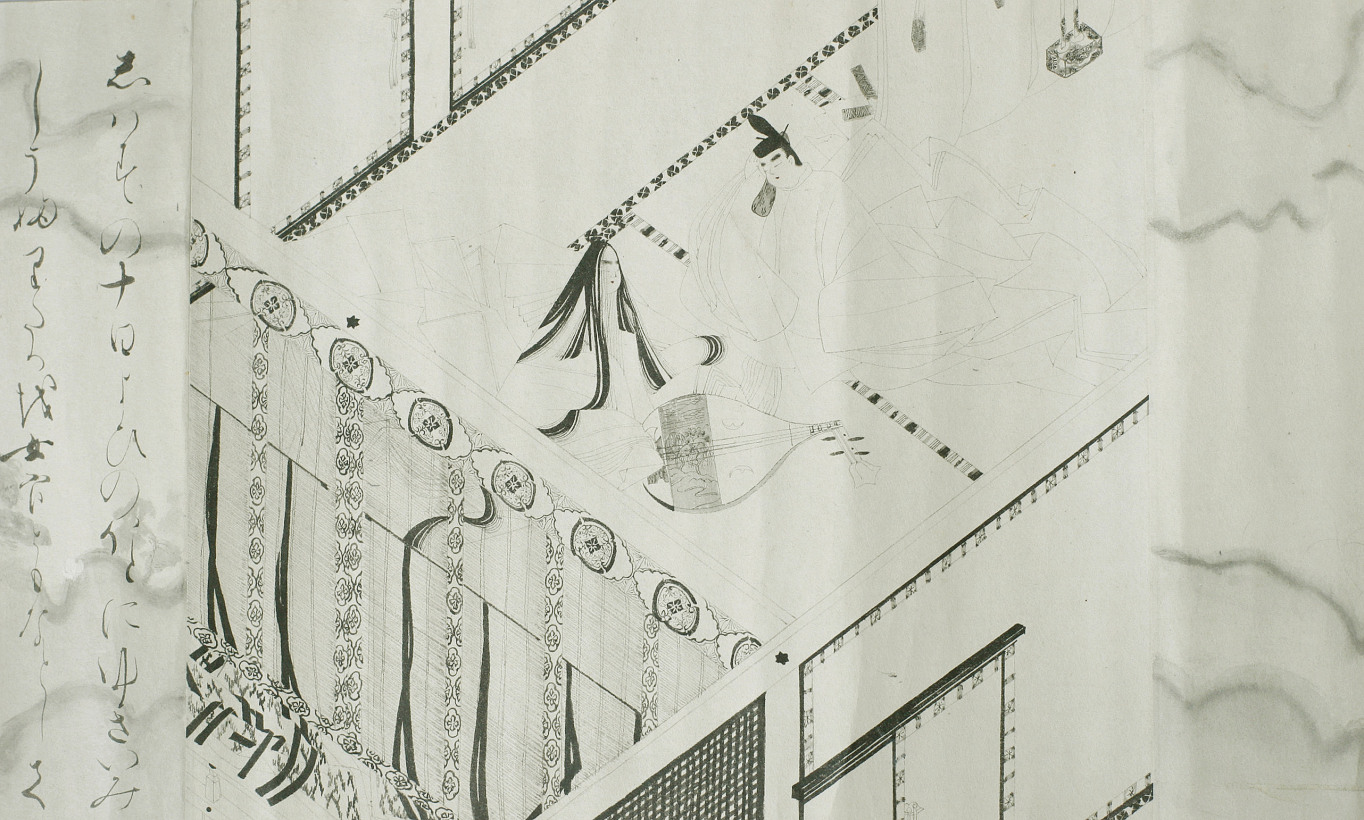
コメント