【一級建築士】設計製図試験のリアル体験記|最後の壁をどう越えたか
一級建築士の設計製図試験について、ネット上には優れた解説や勉強法が多数あります。ここでは筆者自身がかつて経験した、リアルな体験談を記しておきます。
試験の情報というより、苦しい時期を乗り越える一つのエピソードとして、これから挑む方々の励みになれば幸いです。
ストレート合格は可能か?
筆者は2014年度、総合資格学院の設計製図講座(フルコース)で合格しました。学科は前年に通過したものの、その年の製図試験では不合格。学科免除の権利を活かし、翌年に再挑戦しました。
ストレート合格は簡単ではありませんが、実際に合格している人もいます。学科合格当日の夜には即座に合否判定が出され、該当者には自動的に製図講座が案内されるため、「ひと息つく」時間もほぼなし。約2ヶ月で一気に仕上げなければなりません。
1回目:まさに手探り
初めての製図試験は、正直言って無我夢中でした。宿題をこなすのが精一杯で、学科のときに作っていた「合格ノート」も今回は書き込みがバラバラ。質問をまとめる余裕すらなく、何が分からないのかも分からないまま時間が過ぎていきました。
模試や課題に対しては講師からランク(A〜Eなど)がつけられ、合格圏は上位2ランク程度。筆者はその中でも下位ランクで、本番も歯が立たなかった記憶があります。
2回目:環境と戦略を整える
2年目はフルコースを再度申し込み、早期から製図に取り組みました。講座は雪の残る早春からスタートし、周囲には2〜3回目の受験者も多く、彼らの知識量には驚かされました。
筆者は3回目に持ち越すのを避けたく、心身の準備に万全を期しました。学科を突破している時点で「合格への片足をかけている」と信じ、集中力を切らさぬよう努めました。
地方受講のメリットと工夫
1回目は川崎校へ通い、南武線や自転車での移動、雨天時の製図板運びなどで体力を消耗。一方、2回目は仙台校に車で通い、移動の負担が激減したことで学習効率が大きく向上しました。
設計事務所の手伝いをしつつ、勉強時間を優先的に確保。毎回の課題に加えて2〜4枚の追加図面を描き、講師の添削を受けました。疑問点は「合格ノート」に記録し、すべて質問。地方校だったためか、講師の熱心さも印象に残っています。
もし本気で合格を狙うなら、地方校への移籍も選択肢ですが、職を辞してまでの覚悟は慎重に。安定した職があるなら、それを大切にすべきです。
まとめ:設計製図試験に勝つためのポイント
◆ 作図スピードは「描いた枚数」に比例します。読むより手を動かす。これは鉄則。
◆ 製図道具選びも重要です。書きやすいシャープペン(0.3mm〜0.9mm)を用途別に3種類ほどに絞ると良いでしょう。おすすめはペンテルの「グラフギア」シリーズ。高品質でコスパも◎。
◆ 定規はテンプレート一体型の「VANCO三角定規」がおすすめ。時短に直結し、筆者の受験時(H26年度)は試験会場でも問題なし。
◆ 柱は図面全体の“骨格”。0.9mmで太くはっきりと描くことが大切。
◆ 記述は「丁寧に」が命。字が綺麗かどうかより、伝える誠意を込めて書くこと。
過酷な夏、努力を続けるすべての受験生に、心からエールを送ります。体を壊さず、最後までやり切ってください。
関連記事リンク
▶【一級建築士】試験 勉強法と合格体験談〜40代で挑んだ記録

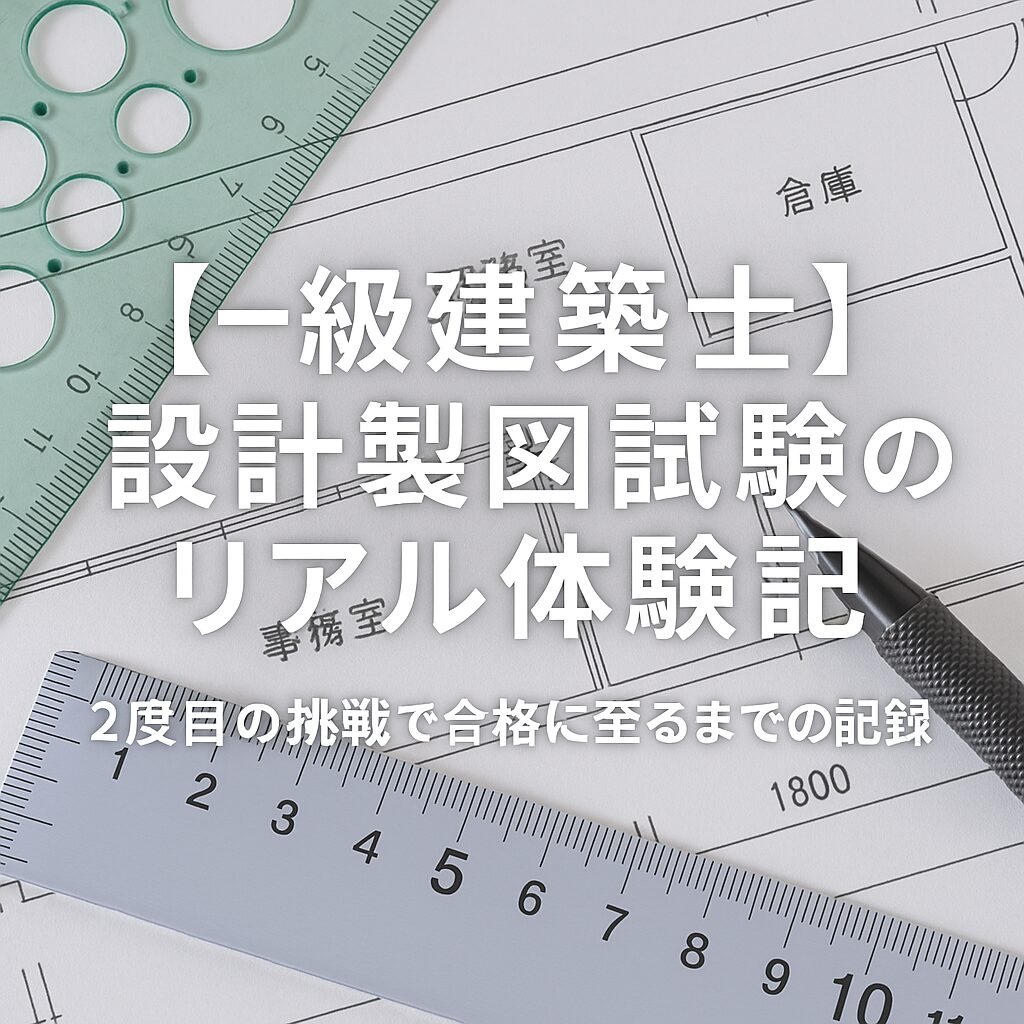


コメント