谷崎潤一郎『文章読本』レビュー|小説家による究極の文章マニュアルとは
1934年に発表された谷崎潤一郎の『文章読本』は、日本文学の巨匠による“文章の書き方”を論じた名著である。芸術的な文章を目指す人だけでなく、日々のブログ執筆やライティングに携わるすべての人にとって示唆に富んだ一冊だ。
構成と全体像
『文章読本』は以下の三部構成で展開されている:
- 一、文章とは何か(言語と文章/実用と芸術/古典と現代/西洋と日本)
- 二、文章の上達法(文法より感覚/読むこと・書くことの実践)
- 三、文章の要素(用語/調子/文体/体裁/品格/含蓄)
目次を見ただけでもその実践的かつ理論的な構えが伝わってくる。では順に内容を追ってみよう。
一、文章とは何か
谷崎は、実用文と芸術文という区分をいったん提示しながら、結論として両者に本質的な差はないと語る。文章の目的は、読み手に内容を正確に伝えること。小説であれビジネス文書であれ、伝達という点で目的は共通しているという。
この視点はシュルレアリスムや難解な詩文とは異なり、いわば文筆業としての「職人」の視点である。詩的な象徴や神秘よりも、構造と機能を優先する実務的な立場が色濃い。
二、文章の上達法
文章が上達するために必要なのは“感覚を研くこと”であり、そのためには「読むこと」「書くこと」を徹底して繰り返すことが重要だと説く。読み書きの習慣を幼少期から身につけることは、寺子屋式教育のように実利的かつ効果的なのだ。
これは現代のブロガーにも通じる。最初は500字書くのに苦労しても、続けるうちに自然と文体がこなれていく。谷崎の教えは、すべての書き手に通用する普遍的な方法論を含んでいる。
三、文章の要素
谷崎は、文章を構成する要素として以下の六点を挙げる:
- 用語の選び方
- 調子(リズム)
- 文体(口調・文語の使い分け)
- 体裁(見た目、構造)
- 品格(上品さ・下品さ)
- 含蓄(無駄を削ぎ落とすこと)
特に「含蓄」についての指摘は厳しい。谷崎は、無駄な形容詞や重複表現が文章を弱めるとし、初心者ほど繰り返しに陥りやすいと警告する。
この姿勢は、限られた読者の集中力やデータ容量を前提とした現代のウェブライティングにも通じる。いかに短く、いかに密度の高い言葉を届けられるか──それが本質である。
まとめと私見
『文章読本』は、文章術というよりも「文章を仕事にする者の心得」と言うべき書である。谷崎の語り口は平易で実直、だがその背後には文豪としての鋭い審美眼と職業倫理がにじみ出ている。
なお、川端康成や三島由紀夫も同題で文章論を残しているが、谷崎版はとりわけ“職人的リアリズム”に根差した内容となっており、文筆の現場で働く人間には一読の価値がある。
最後に一つ。もし「文章とは何か」と問われたなら、私はこう答えたい──
文章とは、大衆のためのものではなく、選ばれし者にだけ通じる秘密の伝達手段である。

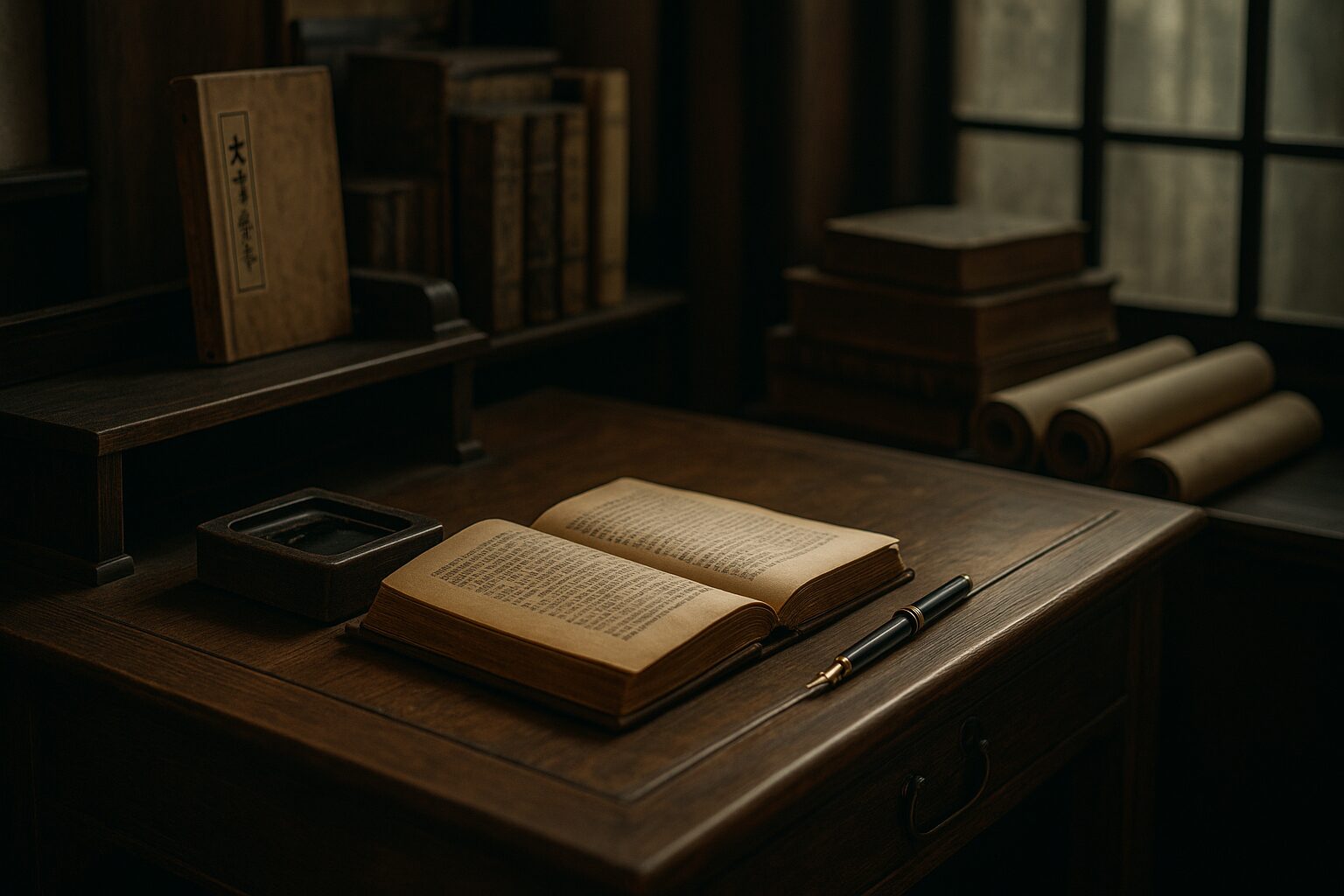


コメント