コペルニクス『天体の回転について』岩波文庫版(第1巻)書評
岩波文庫版と書誌情報
ポーランドの天文学者ニコラウス・コペルニクスの『天体の回転について』は、もともと全6巻から成る大著である。しかし岩波文庫に収録されているのはその第1巻のみである。翻訳は科学史家・矢島祐利氏によるもので、初版は1953年(昭和28年)に刊行されたsekibang.blogspot.com。文庫版としては2000年代に増刷もされているが、旧漢字・旧仮名遣いが使用されており、現代語に慣れた読者には読みづらく感じられるかもしれない。それでも翻訳そのものは平易で明快な日本語でまとめられており、旧字にも慣れれば飽きずに読み進められる。なお第1巻以外の巻を読むには講談社学術文庫やみすず書房から刊行されている完訳版などにあたらなければならないが、いずれも価格が高く一般読者には購入が容易ではないことに留意したい。
第1巻付随の解説
岩波文庫版第1巻には、訳者による充実した解説が付随しているsekibang.blogspot.com。この解説では、コペルニクスの生涯や当時の学問的背景、さらに宇宙論の歴史からコペルニクス説の発展に至るまでが通史的に紹介されている。たとえばアリストテレス以来の地球中心的宇宙観から、コペルニクスによる太陽中心説への転換がどのように起こったのか、数学的・幾何学的手法を駆使した理論構築の経緯が丁寧に解説される。またコペルニクスがポーランド王国下で聖職者として学んだ経緯や、後輩レティクス(Georg Joachim Rheticus)の下で地動説の公表準備が進められたことなど、伝記的な要素も盛り込まれている。解説の末尾にはコペルニクスが教皇パウルス3世に宛てた献呈書簡も掲載されており、そこでは「突然このようなことを言えば驚かれるかもしれませんが……」と控えめに新説を紹介する様子が窺えるsekibang.blogspot.com。このように第1巻の巻末解説は量も質も豊富で、『天体の回転について』を理解する上で大変参考になる内容となっている。
第1巻の主題と哲学的背景
第1巻の本文は、主に地球と宇宙全体の形状や運動法則について論じている。冒頭から宇宙は球形であること、地球もまた球形であることを前提とし、地球中心説で説明困難だった現象(たとえば惑星が異なる季節で見かけ上大きさを変える理由など)を新しいモデルで解明しようと試みるsekibang.blogspot.com。文章には幾何学的な図形や理論が多用され、抽象的かつ哲学的な議論が展開されるため、理論の骨格はしっかりしているものの、現代の感覚ではやや堅苦しくも感じられる。一方で、旧来の理論を否定しつつ新しい説を提示する手法には緊張感があり、宇宙観の大転換を目の当たりにしているような興奮がある。文章全体に学術的で整然とした口調が保たれており、翻訳文も落ち着いた「である調」で記されているので、知的好奇心をくすぐられる読書体験が得られる。
発表までの葛藤
コペルニクスはこの画期的な理論を長らく秘匿しており、生前の1543年にようやく公表に踏み切った。自身の死期を悟ったコペルニクスは、晩年に助手のレティクスらの説得を受けて執筆を完成させたが、発表には大きな慎重さが払われたsekibang.blogspot.com。特に当時は教会の権威が強かったため、公刊にあたり教会批判を避ける必要があった。このため出版時には編集者アンドレアス・オジアンデルス(Osiander)が無署名の序文を書き加え、新説をあくまで数学的仮説にすぎないものとして位置付けている(これもコペルニクスの意思ではなく、やむをえない措置であったと言われる)。その結果、世間からは「慎重すぎる」「もっと早く発表すべきだった」といった声も上がったという。しかし後世から振り返れば、この慎重なリスク管理がなければ地動説は葬られていた可能性もあり、コペルニクスにとっては苦渋の選択であったといえる。
後継者への影響
コペルニクスの地動説は、その後の哲学者・科学者たちに大きな影響を与えた。ルネサンス期の思想家ジョルダーノ・ブルーノは、コペルニクスの宇宙観を取り込みつつさらに宇宙無限論を唱え、既成の宗教観に大きな衝撃を与えた。またデンマークの天文学者ティコ・ブラーエ(Tycho Brahe)は、より精密な観測機器を使ってコペルニクスの体系に代わる独自の宇宙モデル(地球中心だが他の天体は太陽のまわりを回る二重中心モデル)を提案し、間接的に地動説の検証に貢献した。さらにヨハネス・ケプラーはコペルニクスの太陽中心説を土台にして、惑星の楕円軌道運動の法則を発見し、その理論的枠組みを完成させた。ガリレオ・ガリレイは望遠鏡観測によってコペルニクス説を実証的に支持し(木星の衛星発見、金星の位相変化など)、科学革命への道を大きく切り開いた。以上のように、コペルニクスの著作はそれ単体でも卓越しているが、その真価は続く研究者たちへの触媒作用にもあったと言える。
天文学と数学:読解の難しさと筆者の印象
中世以来、天文学は「数学の一分野」とみなされていた。その流れをくむコペルニクスの議論も、多くの部分で数学的・幾何学的手法を前提としている。たとえば地球や天体の形状を球体や円錐といった幾何図形で説明し、その位置や運動を算術・幾何学的に示そうとする試みが多く見られる。このため現代の読者にとっては、専門的な数理的議論が随所に登場し、理解の難しい箇所も少なくない。筆者個人としても幾何学図形の連続した論証には多少難儀したが、それでもコペルニクスが宇宙を秩序立てて数学的に把握しようとする真摯さは感じ取ることができた。つまり、知的な面白さと同時に、噛み砕いて読むには粘り強さが要求される内容である。なお岩波文庫版には各章末に簡潔な訳者注が付されており、専門用語や用例について適宜補足されている点が助けになる(数学的用語を丁寧に説明した挿図もある)。
読みやすさと結論
以上のような難点はあるものの、全体として本書第1巻は思いのほか読みやすいと感じられる。訳文は平易な表現に努めており、過度に専門的な用語は少ない。また解説篇や巻末付録が充実しているため、理解の手がかりが多いのも心強い。筆者も天文学や数学の専門家ではないが、旧字体に戸惑いながらも、物語を追うように最後まで読むことができた。従って、この文庫版第1巻は専門知識のない一般読者にも十分に手が届く内容であると言ってよいだろう。コペルニクスが「宇宙は数学的に記述できる」という近代科学の扉を開いた歴史的な著作であることを考えれば、本書は天文学史や科学史に興味を持つ読者にとって、貴重な第一歩となる一冊である。

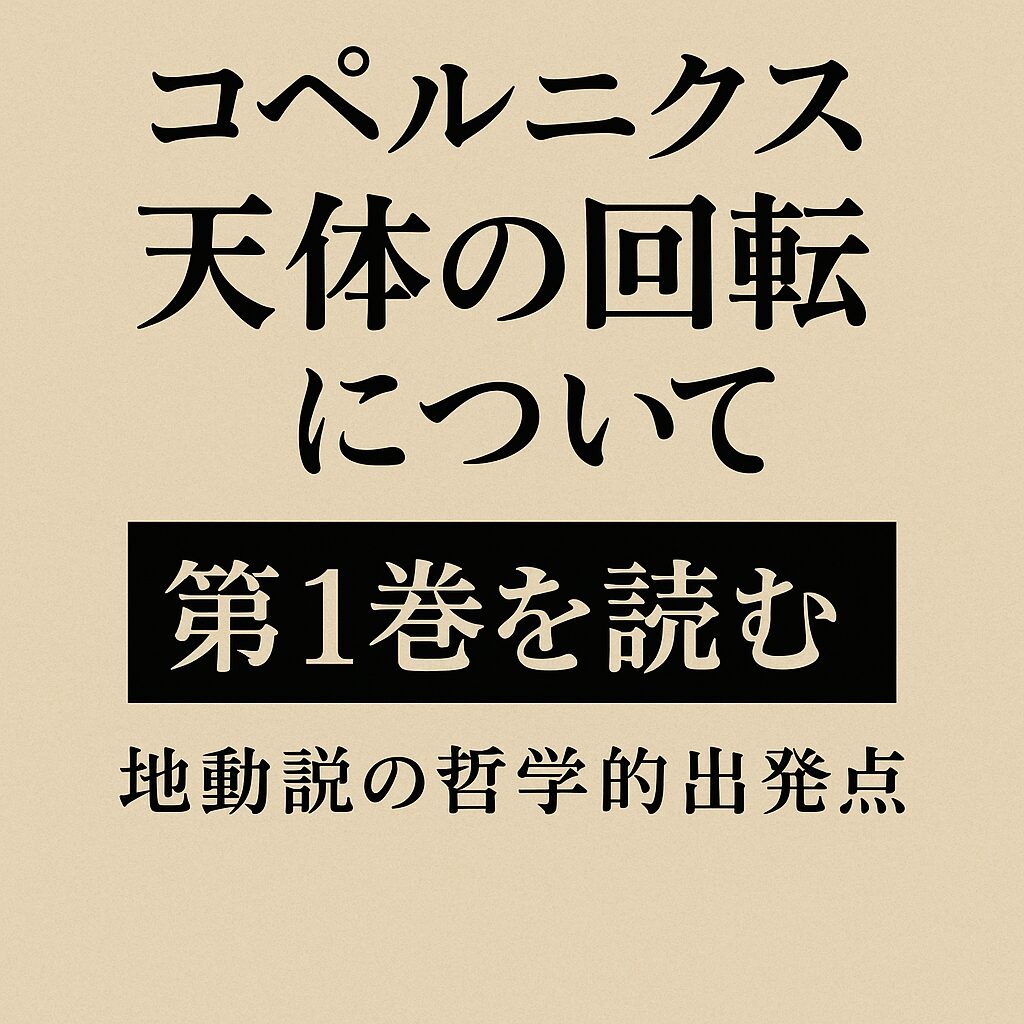

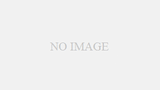
コメント