【夏目漱石】短編「ケーベル先生」紹介・感想〜徒然なる夕暮れの静かな語らい
ケーベル先生の書斎を訪ねて
わずか10ページほどの掌編でありながら、深い余韻を残す作品だった。読後に心の奥から静かにこみ上げるものがあり、こうして筆を取っている。
主人公と安倍君——同級生か旧友か——は、ケーベル先生の書斎を久しぶりに訪れる。前回来たのがいつだったかも定かではない。それは時間の流れが曖昧になるほど、穏やかな午後の光景であった。
筆者自身も、小学一年の頃に担任の先生の家を訪ねた記憶がある。あの特別な感覚が蘇る。だが、ケーベル先生は西洋から日本に渡ってきた大学教授であり、すでに18年もの間、日本を離れず暮らしているという。
先生は一日中書斎にこもり、読書に耽る生活を送っている。楽器に向かうのも気が向いたときだけ。書斎には外国趣味の装飾もなく、煤けた家具と、時の止まった空気が流れている。
美学と日暮し
二人の学生は「美学を学びたい」と先生を訪ねたはずだったが、その日語られたのは、菊や椿、鈴蘭、果物など、ささやかで愛らしい話題ばかりだった。
「その時、夕暮れの窓際に近く日暮しが来て朗らかに鋭い声を立てたので、卓を囲んだ四人はしばらくそれに耳を傾けた」
この一節を読んで、私は野鳥かと思ったが、日暮しとはヒグラシという蝉の一種だった。哀愁を帯びた声は、静けさをさらに際立たせる。

カラスと蝙蝠と幻想文学
話はやがて、かつて先生が放し飼いにしていたカラスの死へと移る。とても寒い朝、枝の上で凍えて亡くなったのだという。そこからエドガー・アラン・ポーやホフマンの話、さらに蝙蝠の話へと流れる。
先生は「蝙蝠の翼は悪魔の翼である」と西洋的な見方を示す。主人公はその言葉に、悪魔の絵を連想し、私もまた『マルドロールの歌』の挿絵を思い出した。
蝙蝠の翼が悪魔的というのは納得できる。だが、ロートレアモンはその翼のはためきを慰めとして描いている。私が思い浮かべたのは、キクガシラコウモリ(rhinolophus)の可愛らしい姿だった。

静寂と雑音の間で
こんなふうに、流れるままに思索を巡らせながら、友と語り合う時間。もはや現代では失われた贅沢なのかもしれない。
電気のない時代。彼らは宇宙線や電磁波など気にすることなく、安心して「今」を生きていた。
私たちは美しいものを見ればすぐに撮影し、SNSへ。面白いものを見れば即ツイートし、話題にしようとする。だが、もし太陽フレアや宇宙線でインフラが崩壊したとしたら? 私たちの「美しさ」や「感動」は、どこに残るのだろうか。
静かなる終わり
この短編の最後の一行は、まさかのエドガー・アラン・ポー『大鴉』の”Nevermore”で締められていた。
まさか漱石の作品でポーに出会うとは。三島由紀夫の『葡萄パン』に『マルドロールの歌』が登場したときと同じような、意外性と共鳴を感じた。

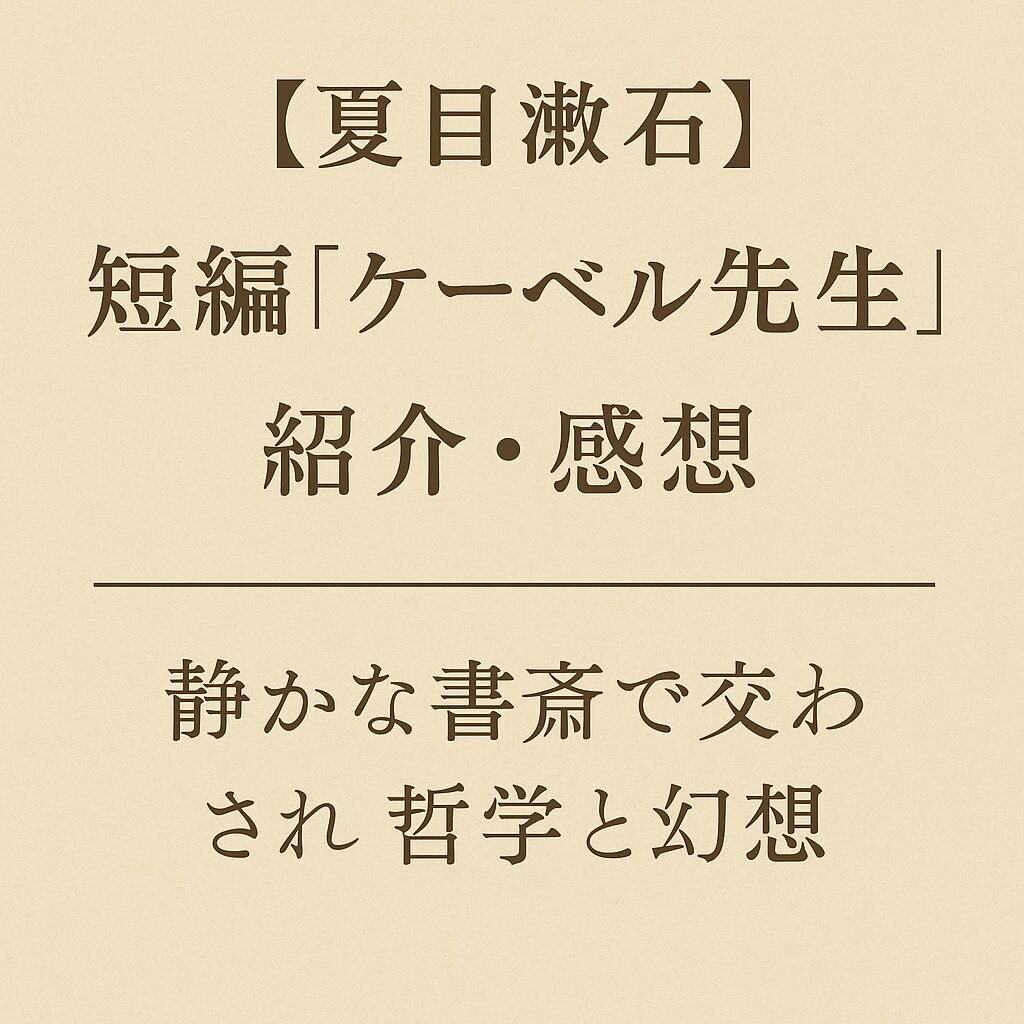
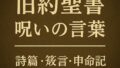

コメント