経緯──高校時代と今
この短編を初めて読んだのは、高校生の頃だった。当然ながら、その時の私はこの作品を十分に理解していなかった。十七歳と五十歳とでは、人生経験が違うのは当たり前だ。未熟な高校生は、難しい作品を解説に頼り、あっさり答えを受け入れてしまうものである。
さて、『伴大納言絵詞』は、応天門炎上の経緯を描いた絵巻物だが、その冒頭には、火事に駆けつける検非違使たちが描かれている。この検非違使──平安時代の警察官のような役人──が芥川龍之介『藪の中』にも登場する。
ゴイサギ→醍醐天皇→菅原道真→応天門→芥川龍之介という流れでたどり着き、改めて『藪の中』を再読してみた。驚いたことに、この短編には古語辞典に載っていそうな古典的な言い回しがたくさん出てくる。まるで現代に蘇った古典文学のようだ。
芥川の作品は、古典を現代風にアレンジしたものなのか?──そんな発想は高校時代には思いもよらなかった。『藪の中』は、検非違使が人殺し事件を取り調べる形で、読者自身に真相を探らせる構成になっている。いわば、探偵小説風の趣もある短編だ。
あらすじ
藪の中で一人の男の死体が発見される。胸を一突きにされて即死しており、現場には縄と櫛だけが残されていた。検非違使の取り調べによって、3人の人物がこの事件に関わっていることがわかる。
関係者は、殺された男(26歳)、その新妻(19歳)、そして盗賊・多襄丸。藪は馬も入れないほど深く、現場近くに馬が放置されていたが、これはあまり重要ではない。焦点は次の3つの可能性に絞られる。
❶妻が夫を殺したのか?
❷盗賊・多襄丸が夫を殺したのか?
❸それとも夫が自害したのか?
❶は、清水寺で懺悔した妻自身の証言。❷は、捕らえられた多襄丸本人の自白。❸は、霊媒師によって呼び出された死者の霊の告白である。
こうして三つの異なる証言が提示され、事件の真相は”藪の中”──つまり解明不能のまま読者に委ねられる。
真実はどこに?
高校時代の私は、解説に書かれていた「作者の懐疑主義的態度」といった説明を鵜呑みにしていた。だが、改めて読むと、より深い問いが立ち上がる。
❶妻の証言──盗賊に辱められた恥ずかしさから、目撃者である夫を刺殺して自らも死のうとしたが、死にきれなかった。
❷多襄丸の証言──妻が盗賊の妻になることを望み、その条件として決闘の末、夫を殺した。しかしその間に女は逃げた。
❸死者の霊の証言──妻と盗賊は逃げ去り、取り残された夫は悲しみから自害した。ただし死の直前、誰とも知れぬ者が近づき、刀を抜いたという。
死者の証言には仏教的な「中有」(死と再生の間の闇に迷う魂)の描写があり、物語はそこに沈んでいく。
私の推理──第五の真実
五十歳になった今、私はこう考える。
まず、霊魂そのものは真実を語るかもしれないが、霊媒師は信用ならない。私は現実社会で数々の詐欺を見てきた経験から、そう断言できる。
生き残っているのは、捕らえられた盗賊と妻だけだ。懺悔に訪れた妻の証言は、同情を引くための作り話かもしれない。
では、多襄丸はどうか?世間では彼を殺人犯と見なしているし、本人もそう語っている。だが、もし彼が、女をかばうため、自ら罪をかぶる覚悟を決めたとしたら──。
そう考えると、これはただの謀略ではなく、かすかな「慈悲」がテーマに浮かび上がる。芥川龍之介には『蜘蛛の糸』のように、悪人にすら救いを見出そうとする作品もあるのだ。
(もっとも、多襄丸は「23合目で斬り合って倒した」とまで具体的に語っており、細部が作り話にしてはリアルすぎるが)
まとめ──藪の中の読書
『藪の中』は単なる「視点の相違」を描いた作品ではない。事実は三つある。そのうちどれがもっとも真実味を持つか、読者自身が考えるべき作品である。
高校時代の私のように、安易に解説に頼るのではなく──ぜひ、自分自身の考えでこの傑作と向き合ってほしい。

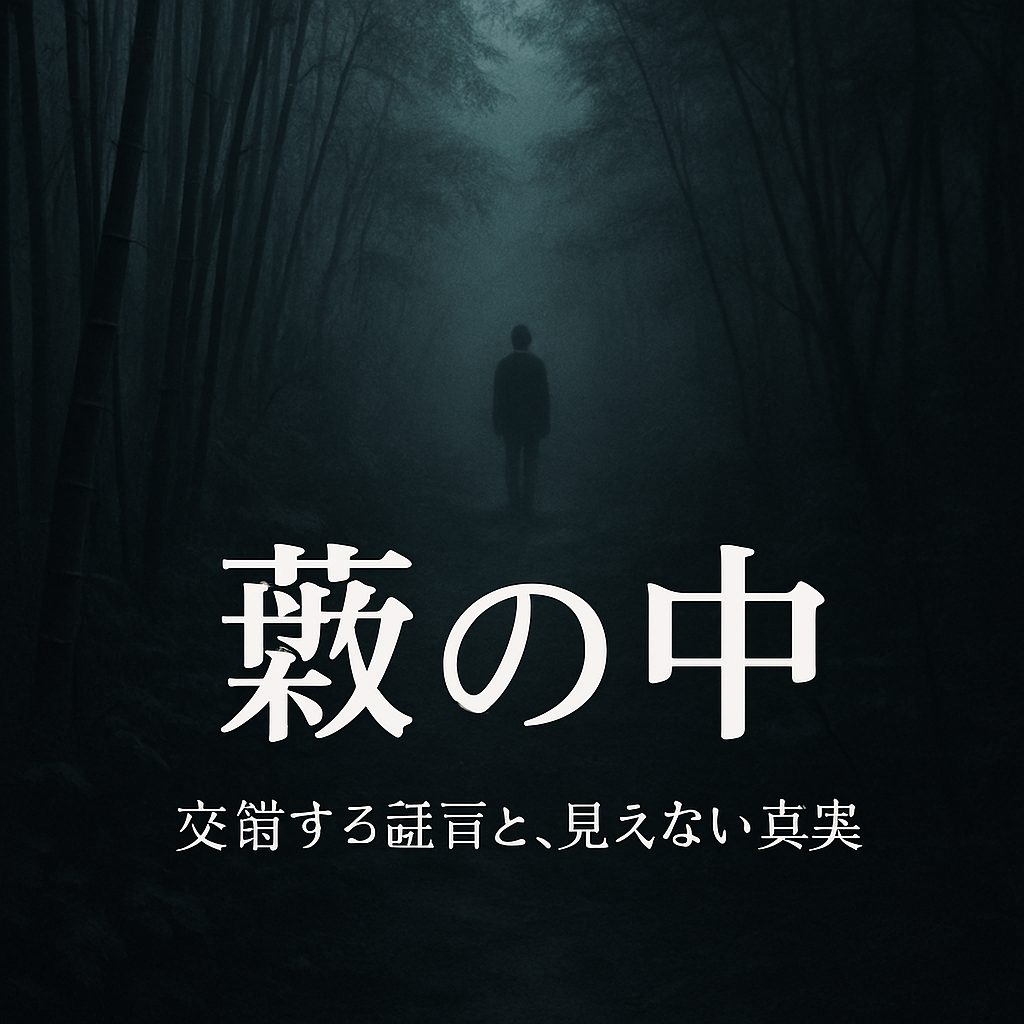
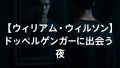

コメント