はじめに
「かぐや姫」の物語──日本人であれば、誰しもが幼い頃に一度は耳にしたことのある昔話だろう。それが『竹取物語』である。この物語の印象は、文字を覚える以前、言葉として私たちの耳に届いた最も古い記憶の一つかもしれない。
『竹取物語』は平安時代初期に成立したとされ、日本文学史上初の「物語(フィクション)」とされている。随筆でも歌物語でもない、短編小説的な形式をとったこの作品は、文学的にもきわめて意義深い。今回取り上げる岩波文庫版は、初心者にも配慮された丁寧な注釈付きであり、古文が苦手な筆者でも通読できた点が特筆に値する。
作品の美とことば
岩波文庫版を通じて本文、注釈、解説をすべて読み進めると、子供の頃の断片的な記憶が鮮やかによみがえると同時に、「あれ、こんな話だったっけ?」という新鮮な驚きもあった。とくに日本語の美しさ──音律、言い回し、語感の繊細さには、改めて感銘を受けざるを得なかった。
ラテン語の聖書やフランス語の小説、英語詩を読むのと同様に、筆者はこの古典日本語作品を「翻訳するように」読み解いていった。その結果、「かぐや姫」という物語が、なぜ1000年以上にわたって愛されてきたのかが、感覚的に理解できた気がした。
あらすじの再発見
竹を取り生計を立てていた翁が、ある日光り輝く竹の中から三寸ばかりの美しい女の子を見つける──この導入は誰もが知る部分だが、実際に読み直してみると意外に忘れている細部が多い。
少女はすぐに大人びた美しい姿に成長し、近隣の人々の間で評判となる。そして6人の貴公子が求婚するが、かぐや姫はそれぞれに不可能な課題を与える。結果として誰一人として課題を果たすことはできず、命すら落とす者も現れる。
帝との交流と別れ
やがて、帝もかぐや姫の美しさに魅了され、彼女を后に迎えようとする。しかし姫は「宮仕えするくらいなら死を選ぶ」とまで言い放ち、帝の求めを断る。その後、帝と姫は文を交わすだけの関係を保つ。
やがて、かぐや姫の本当の出自が明かされる。彼女は月の世界から来た存在であり、地上での時が終わるとともに月へと帰らなければならないのだった。姫が昇天する日、帝は兵を遣わして迎えの者たちを阻もうとするが、月の者たちには抗えず、姫は地上を離れる。
羽衣と記憶の喪失
「天の羽衣」を身にまとうと、かぐや姫は人間としての記憶をすべて失ってしまう。それは美しい別れでありながら、切ない断絶でもある。姫は翁に形見を、帝には歌と「不死の薬」を託して、静かに月へと昇っていく。
地上に残された者たち
物語は昇天で終わらない。帝は「不死の薬」を前にして、「姫と会えぬ不死に何の意味があるか」と嘆き、それを燃やすよう命じる。その場所が「富士の山」とされ、今なおその煙が絶えず立ちのぼっている──という詩的な結末が語られる。
この終幕が、いわゆる“おとぎ話”の枠を超えた余韻をもたらす。地上に残された者の痛みと、その痛みを昇華する詩情が、読者の心に深く刺さる。
感想と現代への響き
子どもの頃に接した『竹取物語』には、おそらく求婚者たちの試練などは省略されていたのだろう。実際に読んでみると、それらは独立した短編のような面白さを持っている。そして何より、かぐや姫の昇天の場面──月への帰還は、静謐でありながら壮絶な別れのドラマである。
地上の人間は、その美しさに手を触れることはできない。ただ見るだけ、思うだけ。その切なさが、帝の人生を変え、我々の心にも深い印象を与える。月という到達できない対象への憧れ、それがこの物語に永遠性を与えているのだ。
『竹取物語』は単なる昔話ではない。それは、日本人の美意識、自然観、そして“あはれ”の感情を見事に結晶化させた文学的傑作である。

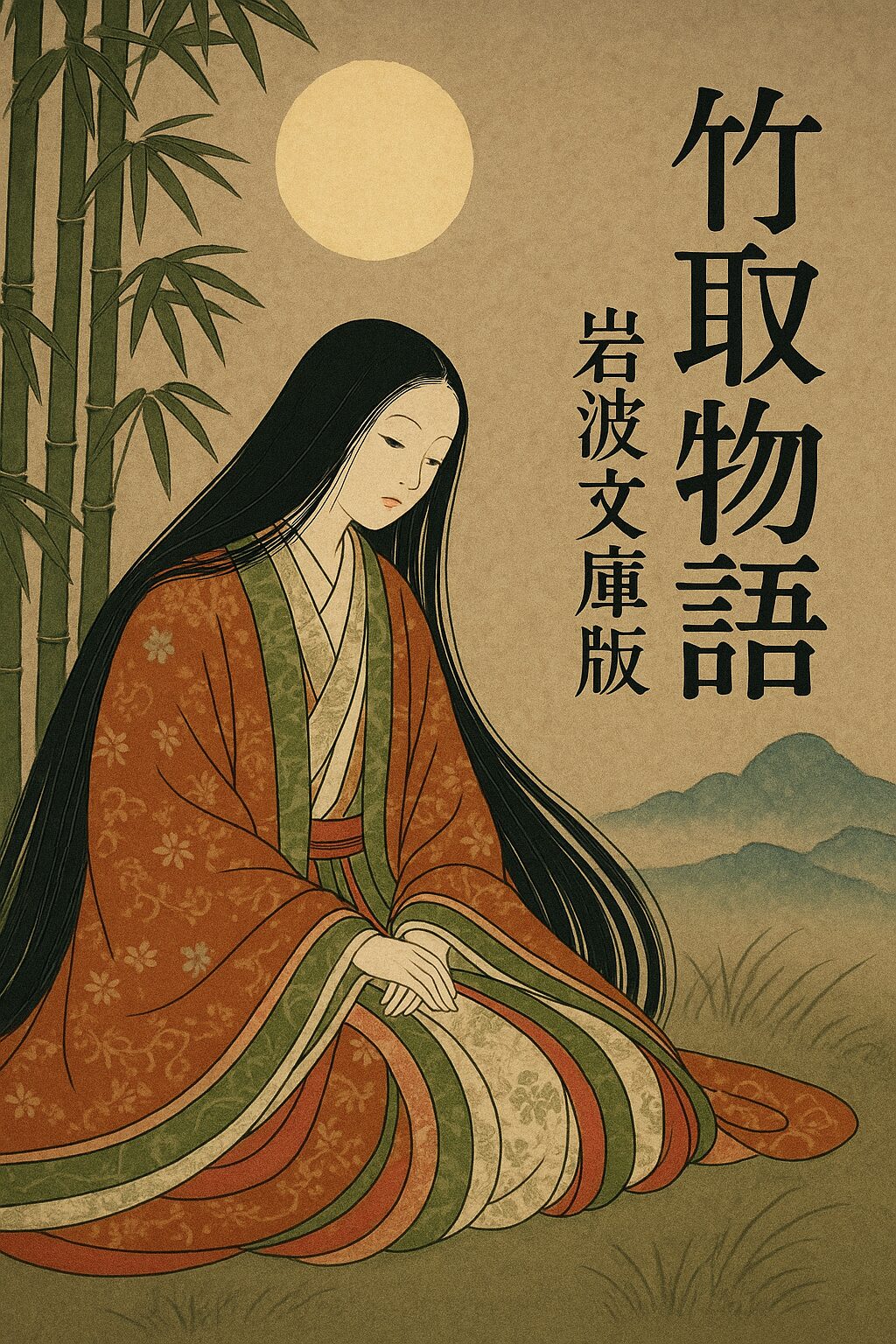


コメント