【一級建築士】設計製図試験リアル体験記〜40代からの挑戦
建築士法にはこう書かれている――「建築士は,常に品位を保持し,業務に関する法令及び実務に精通して,建築物の質の向上に寄与するように,公正かつ誠実にその業務を行わなければならない」。
本記事は、筆者が40代にして挑んだ一級建築士試験(特に製図)の個人的な記録であり、同じく過酷な試験に挑む皆様の参考と励みになればという想いから綴ったものである。
一級建築士試験の難易度
一級建築士試験は極めて難関である。学科試験に合格しても、その後には6時間半にも及ぶ設計製図試験が控える。
しかも製図試験は点数基準ではなく、相対評価。上位から順に合格が決まるため、どれだけやっても「ここまでで十分」というラインが存在しない。
学科で免除が3年間得られるとはいえ、再びあの勉強量と費用をかける余裕など誰にでもあるわけではない。だからこそ、1回で合格するための執念が必要だ。
挑戦する年齢について
筆者のように40代で挑むのは、体力・集中力・時間の確保と、いずれも非常に厳しい。理想は大学卒業後すぐに受験し、20代で取得すること。遅くとも30代前半までに合格しておきたい。
40代での受験は、相当な覚悟が必要である。
学校選びの重要性
筆者は「総合資格学院」に通った。学費は高額だが、講義の質や教材、合格へのサポート体制は圧倒的である。
とくに設計製図に関しては、オプション講座などでさらなる強化も可能であり、時間とお金の投資に見合う結果が得られたと実感している。
学科の勉強法
筆者は大学を出ておらず、二級建築士と実務経験からのチャレンジだった。東京の建設会社で働きながら、川崎の総合資格に通学。
スタートアップ講座からDVDで受講し、年明けから本格講義。とにかく「予習・復習・弱点補強」の繰り返し。得意不得意をはっきりさせて、重点的に取り組むべき。
構造が苦手だったが、最終的には本試験でほぼ満点を取るまでに。模試は本番と思って取り組み、高得点を目指すべき。学科は「点を取れば受かる」明確な試験だ。
学科本試験と製図への移行
筆者は専修大学・生田キャンパスで受験。学科は合格したが、「環境・設備」でギリギリの脚切りラインだったことから、危機感を強くした。
その年の製図は不合格。体調を崩して会社を辞め、実家のある宮城県の総合資格学院仙台校へ転籍。ここから再挑戦が始まる。
製図試験対策と地方校の強み
地方校では受講生が少ないため講師のサポートが手厚く、仙台校は特に合格率が高かった。筆者は図面を100枚書くよう言われ、それを実行。
質問はすべて「合格ノート」に記し、毎回講師に確認。仙台育英での本試験会場は馴染みある受講生ばかりで、安心感があり緊張がなかった。
本試験の罠と奇跡の合格
本試験当日は「簡単すぎる」と思ったが、それが落とし穴だった。設問を勘違いして記述を修正するうちに、図面の見直し時間を失った。
帰宅後にミスを思い出して絶望しながらも、講師の助言で神社にお参り。結果、ギリギリ合格できた。
最後に:使用アイテム紹介
役立ったアイテムの一つが「VANCOの三角定規」。テンプレート付きでスムーズな操作が可能。筆者も本試験で使用し、作業時間短縮に大いに貢献した。

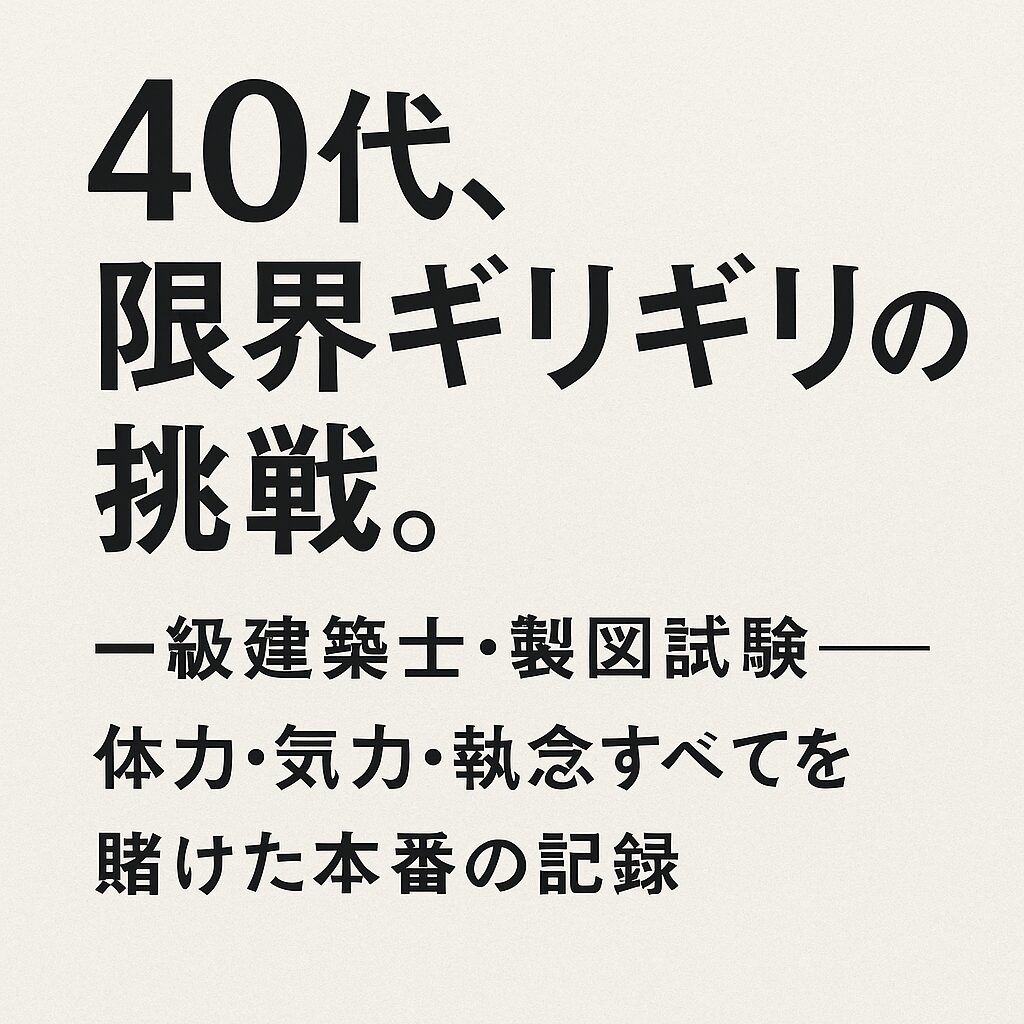
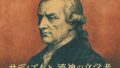

コメント