澁澤龍彦『快楽主義の哲学』と奇妙な三角形
澁澤龍彦(1928–1987)は、日本のフランス文学者にして評論家。晩年には小説も執筆した。世間の注目を集めた裁判沙汰の末、マルキ・ド・サドを翻訳・紹介した人物としても知られている。
出会いと衝撃
私が初めて澁澤龍彦の本に出会ったのは18歳のとき。友人に勧められて読んだのが、河出文庫から刊行されている澁澤龍彦のシリーズだった。
『エロスの解剖』『異端の肖像』『妖人奇人館』『東西不思議物語』など、まさに異彩を放つ著作群。音楽で言えばパンク・ロックのような衝撃だった。常識や模範解答のような価値観をぶち壊し、まずは「行動せよ」と命じてくる。読者に問いかけるのは「お前は何を欲しているのか?」という根源的な問いだった。
偏見の打破
社会の規範、将来の不安、世間体、流行。そういったものが、澁澤の語る激しい欲求の前では、ただの幻想に過ぎないと思わされた。登場するのは、魔術師、ローマ皇帝、革命家、犯罪者といった魅力的な異端者ばかり。
澁澤を通じて、私は古今東西の文化や黒魔術、フリーメイソンのような秘密結社にまで関心を抱くようになった。従来の日本文学にありがちな、内省的で自滅的な作風とはまったく違う世界がそこにはあった。
三島由紀夫との交錯
最近、ふと図書館で借りた『金閣寺』をきっかけに三島由紀夫作品に没頭していった。読み進めるうちに、マンディアルグが三島を称賛していたことや、『サド公爵夫人』を仏訳したことを知る。さらには1979年、マンディアルグが劇団とともに来日していたことなどが重なり、一層興味が増した。
そして調べていくうちに、澁澤龍彦が三島由紀夫の思想形成に深く関わっていたことを知った。澁澤は三島のために翻訳を行い、奇書や稀書を紹介していたという。マンディアルグを日本に紹介したのも澁澤であり、ここに「澁澤龍彦 ⇔ 三島由紀夫 ⇔ マンディアルグ」という奇妙な思想の三角形が浮かび上がる。
内容と所感
『快楽主義の哲学』は、意外にも「です・ます」調で書かれており、議場で講義を聴いているような落ち着いた語り口が新鮮だ。だが、時折尖った口調が顔を出し、若き日の著者の情熱も感じさせる。ユーモアや皮肉も効いており、軽快で読みやすい。
中盤では、歴史上の快楽主義者が次々と登場し、現代の「生命保険」や「マイホーム」といった価値観を滑稽に映し出す。澁澤の広大な知識の海の中では、そうした言葉たちは異様なほど矮小で風刺的に響く。
まとめ
1965年にカッパ・ブックスとして出版された本書は、今読むとやや古臭さもある。たとえば、「遊びがそのまま職業となるような未来は訪れるか」という問い。今ではYouTuberやネットビジネスの登場で、それは現実となっている。
また、大学→就職→結婚→マイホーム→定年という人生設計を「退屈」とする記述も、今では“夢の終身雇用”すら過去の話になりつつある。
とはいえ、澁澤がサドの無神論やソクラテス批判を軸に語る快楽主義は、三島の軍国的な理論と同じく、極端でありながら強烈な個性を放っている。普遍性はないかもしれないが、だからこそ強く響く。
この哲学の影は、三島由紀夫の最期──あの割腹自殺の背後にも、どこか黒い影として揺らめいているように思えてならない。

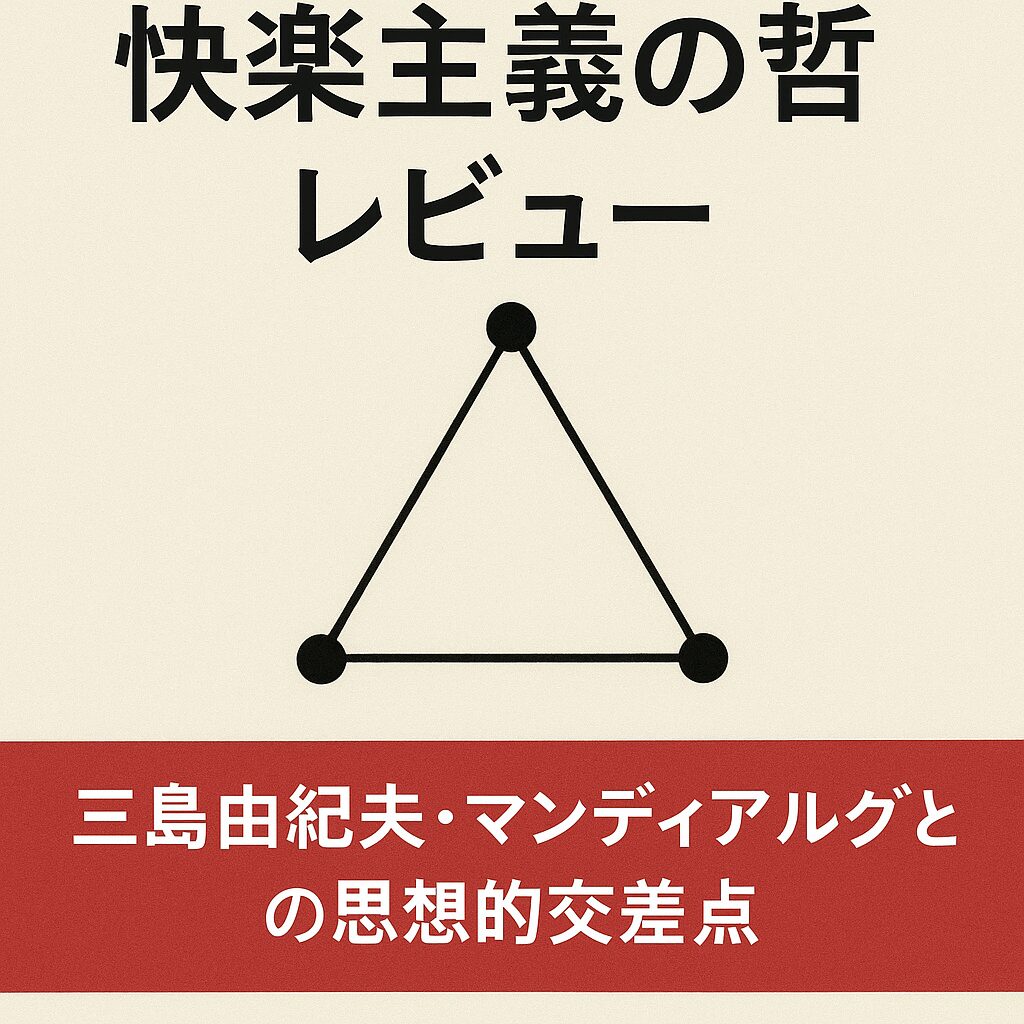


コメント