【『エジプトの死者の書』】 E.A.ウォリス・バッジ著『アニのパピルス』 〜 太陽神ラー讃歌に寄せて
「エジプトの死者の書」
E.A.ウォリス・バッジ (E.A. Wallis Budge) によって編纂された書物が『エジプトの死者の書』と呼ばれている。特に保存状態の良好な「アニのパピルス」のテキストは広く知られている。バッジはエジプトの聖なる象形文字であるヒエログリフを翻訳し、本書には豊富な解説や研究成果、ヒエログリフ原文と英訳の対訳、および通訳文が収められている。
「エジプトの死者の書」に収められたこれらの呪文は、ピラミッドの壁面や棺、神殿の柱だけでなく、パピルスにも書き残されている。ツタンカーメン王の黄金のマスクやミイラ製作の技術に見られるように、古代エジプトの文明と知識は、すべて死後の復活という単一の目的を念頭に編まれていたと考えられる。
E.A.ウォリス・バッジ
本稿で参照している書物は、ハードカバー装丁の英文書籍である。その正式な題名は『The Hieroglyphic Transcript and Translation into English of the Ancient Egyptian Papyrus of Ani, The Book of the Dead, with a Comprehensive Introduction and Commentary by E.A. Wallis Budge』である。この書物は1994年にニューヨークのGramercy Books社から出版されている。
エジプト文明
エジプト文明は約5000年にわたる長い歴史をもち、西暦2000年あまりで数えられる現代文明と比較するとその期間は数回分に相当する。したがって、アニのパピルスが制作された時期は、エジプト文明において言えばむしろその最盛期あるいは末期に相当すると考えられる。
また、宇宙は常に変化と運動を続け、太陽は変わらず一つである。したがって、太陽崇拝を論じる際には、古代エジプト人が認識していた宇宙観と現代人が認識している宇宙観との間に本質的な相違はないことを確認しておく必要があるだろう。
スカラベ
古代から様々な文化で太陽は崇拝の対象とされてきた。太陽は生命や自然現象の根源とみなされ、文字を持たない社会でもすべての出来事を導く存在であると信じられていた。ヨガにおいても太陽への賛歌を表現するポーズが存在することが知られる。
古代エジプト人は太陽神を「ラー(Ra)」と呼び、讃歌や礼拝を捧げた。また、糞転がし虫(スカラベ)を神聖視し、これをケプリ(Khepri)として崇めた。ケプリは巨大な甲虫が太陽の円盤を転がす姿で表され、アクセサリーや装飾品としても用いられた。
この象徴においては、太陽の円盤はスカラベが幼虫を育てる糞を丸めて転がすものとして表現される。
さらに、太陽神は一日の時間帯に応じて三つの主な名で呼ばれた。太陽が昇る東方の領域はBehka(ベフカ)と呼ばれ、沈む西方はManu(マヌ)と称された。神話ではラーは船に乗って天空を渡り、真昼には「ラー・ヘル=フティ」(Ra Heru-khuti)として高天に位置し、夕刻には「テム・ヘル=フティ」(Temu Heru-khuti)へと変容するとされている。
夢について
人間は一日のうちかなりの時間を睡眠に費やす。中には人生の半分近くを眠って過ごす人もいるとされる。睡眠中には高い確率で夢を見たり、夢を見てもそれを忘れることもある。たとえ夢を見なかったとしても、睡眠中の脳は活動を続けており、さまざまな思考を行っている。
太陽が昇ると人は目覚めて活動を始めるが、一般に太陽が東方(Behka)の領域にある午前中は、夢の印象に心が左右されやすい。この現象はしばしば「スカラベの転がす糞」に例えられる。つまり、睡眠中の経験(夢)が午前中の気分や出来事に影響を与えるのである。たとえば、不快な夢で目覚めた場合、それが現実でなくてもその日の実生活に影響を及ぼすことがある。
やがて太陽は南中点を経て西方へ沈み、夜が訪れる。現代では労働や生活の都合によりデジタル時計で時間を管理することが一般的になっており、太陽の位置で時間の経過を知る機会は減少している。


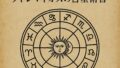

コメント