【EXTREME NOISE TERROR】令和の耳を震わせるグラインド・コア──騒音と調和の狭間で
かつて「おすすめ洋楽選集」のような記事を月1で更新していたことがある。しかし、iTunes Affiliateのリンク作成は面倒で、成果もほとんどなし。アクセスも伸びず、自分で書いていても面白くない──そんな負のループだった。
それでも音楽が好きだ。TwitterやFacebookで気軽に曲を共有し、同じ音楽を愛する誰かに届けばと思っていた。つまり、哲学・詩・小説といったこのブログのカテゴリも、堅苦しいだけのものではない。筆者がこのような発信をしている背景には、青春期にパンクバンドをやっていた経験があるからだ。
パンクとは何か?──それは「既存の価値観の破壊」である。
●参考:【おすすめ洋楽】2018年6月・iTunesライブラリから厳選(異ジャンル)
古代音楽への憧れ──『ハルモニア論』を読みながら
『アルマゲスト』『テトラビブロス』などで知られるプトレマイオスが著した『ハルモニア論』は、古代ギリシャにおける音楽理論の粋である。だが、読んでみると驚くほどちんぷんかんぷん。少しでも理解を深めようと、iTunesで”Ancient Greek”と名のつくアルバムを探して聴いてみた。
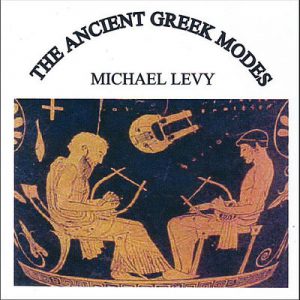
The Ancient Greek Modes / Michael Levy
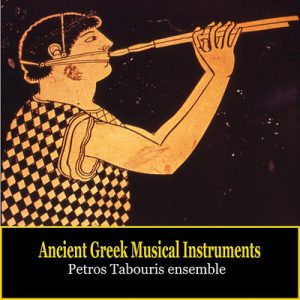
Ancient Greek Musical Instruments – Music of Ancient Greece
これらの音楽は、キタラ、リュラ、アウロスといった古代楽器で演奏されており、プトレマイオスの音楽論の具現といえる。
●関連記事:プトレマイオス『ハルモニア論』の学術的意義|音楽・宇宙・哲学をつなぐ古代の知性
ピュタゴラスの響き──「調和=比例」の哲学
『ハルモニア論』ではピュタゴラス学派の教義──「万物は数である」が根底に流れている。音楽は単なる感覚的な楽しみではなく、数学的・幾何学的な構造物なのだ。
ピュタゴラス派は秘密主義で知られ、教義を漏らした者は死刑に処されたという逸話まである。にもかかわらず「テトラクチュス」(1+2+3+4=10)崇拝などが伝わっているのは、誰かが密かに漏らしたのだろうか?
とはいえ、東西南北の方位が4、黄道が12、指が5本──こうした数の意味は、誰しもが直感的に持っているとも言える。
グラインド・コアの暴力性──EXTREME NOISE TERROR
さて、ようやく本題「EXTREME NOISE TERROR」である。その前に2組の伝説的バンドを紹介しよう。YouTubeから無料で聴ける。
Napalm Deathはデス・メタルの開祖的存在。EXTREME NOISE TERROR や Cannibal Corpse、Collapse などは、その流れを汲んだ後続組(と筆者は勝手に位置づけている)。
G.B.H.はパンク後期に登場したハードコアバンド。鋲ジャン&モヒカンのスタイルもあって、そのカリスマ性はDischargeと並び立つ。
EXTREME NOISE TERRORの魅力
初めて聴いたときは、「ナパーム・デスには敵わないな」と感じた。演奏もただ騒がしいだけ。だが、何度か聴いているうちに──その”騒がしさ”に、不思議な中毒性を感じるようになった。
ライブ映像を見た瞬間、衝撃を受けた。革ジャン姿でビリー・アイドル風ファッションの男が、地の底から響くようなデス声でシャウトしている。そのギャップがたまらない。
▼衝撃のライブ映像:
Extreme Noise Terror – Live in London 1989
「調和」から「拷問」へ──音楽の快楽とは何か
それにしても──なぜ私は、プトレマイオスやピュタゴラスの「調和」理論から、EXTREME NOISE TERRORやSWANSのような”ノイズ”へと飛躍してしまうのか?
●関連記事:SWANS(スワンズ)とは何者か?死にたい夜に聴くノイズロックの極致
答えはこうかもしれない。我々現代人は、視覚も聴覚も日々、過剰な情報に晒されている。望まぬ音を聞かされ、見たくもない映像を目にし続けている。
この環境下で、ノイズこそが快楽へと転化する。すなわち「感覚の拷問」こそが、ある種の解放をもたらす──そんな時代に生きているのだ。


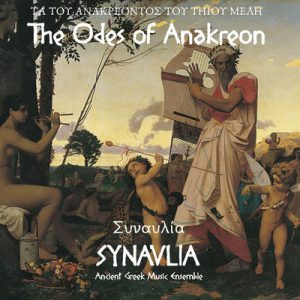

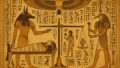
コメント