アウグスティヌス『告白』上巻(岩波文庫)レビュー|聖人の赤裸々な罪の告白と哲学的自伝
作品概要と読みどころ
アウグスティヌス(354–430年)は古代キリスト教を代表する教父にして、後世に多大な影響を与えた哲学者・神学者です。『告白』(上巻)では、自身の幼少期から青年期、壮年期を経てキリスト教への回心に至るまでの葛藤と迷い、母モニカの死までが描かれます。
若い頃に読んだときには、典型的な信仰告白書のようにも思えたこの作品。ですが改めて読み返すと、その印象は一変しました。これは単なる信仰の記録ではなく、知的探求と魂の遍歴を綴った、極めて深い哲学的テキストでもあります。
深まる葛藤と思索
本書は神への「祈り」の形式で書かれていますが、その実態は、自己の内面に対する徹底的な省察と懺悔です。アウグスティヌスは北アフリカ出身の雄弁家としてローマへ渡り、やがてミラノでキリスト教に回心するまでの道のりを、率直な言葉で綴ります。
当初はマニ教という善悪二元論を掲げる宗教に傾倒し、またプラトン哲学やヘルメス主義といった思想にも関心を示していました。彼が現代で言うところの“哲学沼”にハマっていたことは、その記述からも明らかです。
しかし、アウグスティヌスは次第に“理性”ではなく、“恩寵”によって人は変わるのだという確信へと導かれていきます。古代思想からキリスト教神学への橋渡し役としての彼の役割が、ここに表れています。
赤裸々な肉欲の告白
アウグスティヌスの『告白』が今日でも読者を惹きつける最大の理由のひとつは、彼が人間の弱さを包み隠さず綴っている点でしょう。とくに性欲の問題に関しては、驚くほど率直です。
彼は情婦と長く同棲し、婚約までしていたにもかかわらず、信仰のためにその生活を捨て去る苦悩を吐露します。婚約相手が10歳の少女であり、結婚適齢を待つ間にも別の女性と暮らしたエピソードなど、今日の感覚では倫理的に問題のある点も含まれていますが、それも含めて“人間アウグスティヌス”のリアルな姿です。
彼は、情婦たちが「本当に私たちなしでやっていけるの?」「あんなことやこんなことができなくてもいいの?」と引き留めたと記しています。どこか文学的な比喩に包みつつも、その裏には生々しい苦悩がありました。
ローマとコロッセウムの狂気
ローマでは剣闘士の試合が人々の熱狂を集めていました。友人のひとりが信仰を保ちつつ、渋々観戦に付き合わされたエピソードが語られますが、観客の叫びと血の熱狂の中で、信仰心すらもかき消されていくさまが印象的です。
それは単なる娯楽以上に、人間の暴力性や衝動、群集心理の危うさを描いた場面でもあり、現代のSNS文化やメディア社会にも通じる警句のようにも読めます。
母モニカとの別れ
アウグスティヌスの回心を最も願っていたのは敬虔な母・モニカでした。彼女は息子が信仰に立ち返ったことを見届けて安らかに亡くなります。
『告白』(上巻)はこのモニカの死で幕を閉じます。静かな悲しみとともに、信仰によって生き方が根本から変えられていく様子は、宗教を信じるか否かを超えて、読む者の心に強く迫るものがあります。
結語:罪と赦し、そして普遍的人間ドラマ
『告白』は、聖人アウグスティヌスの神への懺悔録であると同時に、普遍的な人間の内面を描いた傑作です。学識ある者の思索と、ひとりの人間の苦悩が交錯する文章に、時代を越えた共感を覚えます。
信仰の有無にかかわらず、「弱さと葛藤」「転機と救い」というテーマは、誰にとっても深く響くものでしょう。



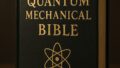
コメント