【詩人・中原中也】心の友だった詩、今もなお胸に残る理由
中原中也──学校でも習う詩人だが、その名前の響きからしてどこか印象に残る。中が二つもあるし、どこか風変わりで親しみやすい。悩みの多い思春期から青春時代、私はずっと彼の詩を「心の友」として読んできた。
なぜか心に残ってしまう彼の詩。それがなぜなのか、言葉にしようとすると難しい。でも今回は、原点回帰シリーズとして、かつての自分を支えてくれた「中原中也」をもう一度たどってみたい。
詩とは何か──中也から教わったこと
詩とは何か? そんな問いを立てた瞬間、堅苦しい「詩論」になってしまいそうだが、中原中也に関してはやめておこう。私にとって詩は、中也だった。義務教育の只中、未成年の私は彼の言葉を通して「詩ってこういうものなんだ」と自然に思えたのだ。
誰にも話せない悩みを抱えていた時代。誰かに聞いてもらいたくても、相手がいない。そんな時、生きている人ではなく、ずっと昔に亡くなった人こそ、最高の聞き手になることがある。中也は、そんな“話し相手”だった。
飾らず、正直で、どこか無防備。それが詩人・中原中也の魅力だった。彼の詩は、まるで山の清水のように澄んでいて、真っすぐに心に染み込んでくる。この人だけが自分の気持ちを理解してくれる、そう本気で思っていた。
中原中也と“無常”の詩
彼の詩には、常にどこか「悲しみ」が漂っている。それは説明のつかない感覚だが、仏教で言うところの“諸行無常”に近いかもしれない。
すべてのものは移ろい、やがて失われる──その事実そのものが中也にとっての「悲しみ」だった。生と死が交差する生成消滅の世界で、彼の視線はいつも「過ぎ去っていくもの」に注がれている。
それはノスタルジーではなく、どこか永遠化された記憶。「アイオーン」、すなわち時間の流れから自由な“常に在るもの”に近い。
彼は思い出を、まるで宝物のようにそっと取り出し、詩にして慈しむ。それは過ぎ去ったはずの時間が、いまだ彼の中に生きている証なのだ。
詩の技巧と日本語の美しさ
中原中也の詩は、日本語の美しさを実感させてくれる。「余白」までもが詩を語る。文字の配置ひとつで印象が変わるため、印刷の仕方や紙質、書体までもが作品の一部になる。
岩波文庫の大岡昇平編など、詩ごとに紙を分けているものは特にいい。ページをめくるたび、一つひとつの詩と丁寧に向き合えるからだ。
逆に、ネットで横書きにされていたり、フォントが妙にお洒落だったりすると、なんだか違うな、と感じてしまう。中也の詩は、そういう“空気感”込みで読むものだと思う。
繰り返しの魔法、そして突き抜けた言葉
方言っぽさや古風な表現を混ぜるのも中也の得意技。そして、もっとも特徴的なのは「繰り返し」だろう。同じ言葉を何度も使うことで、詩にリズムと情緒が生まれる。
時には意味が崩壊したような一節が差し込まれ、唐突に戯けたことを言い出す。その“壊れ方”に心を突き動かされる読者も多いのではないだろうか。
彼は「型」にハマることを拒んだ。だからこそ、読む者の心にズドンと突き刺さるのだと思う。
再び彼に会いに行く
あの頃、夢中になって読んだ中也の詩。久しぶりに古本を手に取り、黄ばんだ紙を捲ると、詩人の声がよみがえってくる。まるで彼が黄泉の国から語りかけてくるようだ。
そして私はまた、あの頃の気持ちに戻っている──。

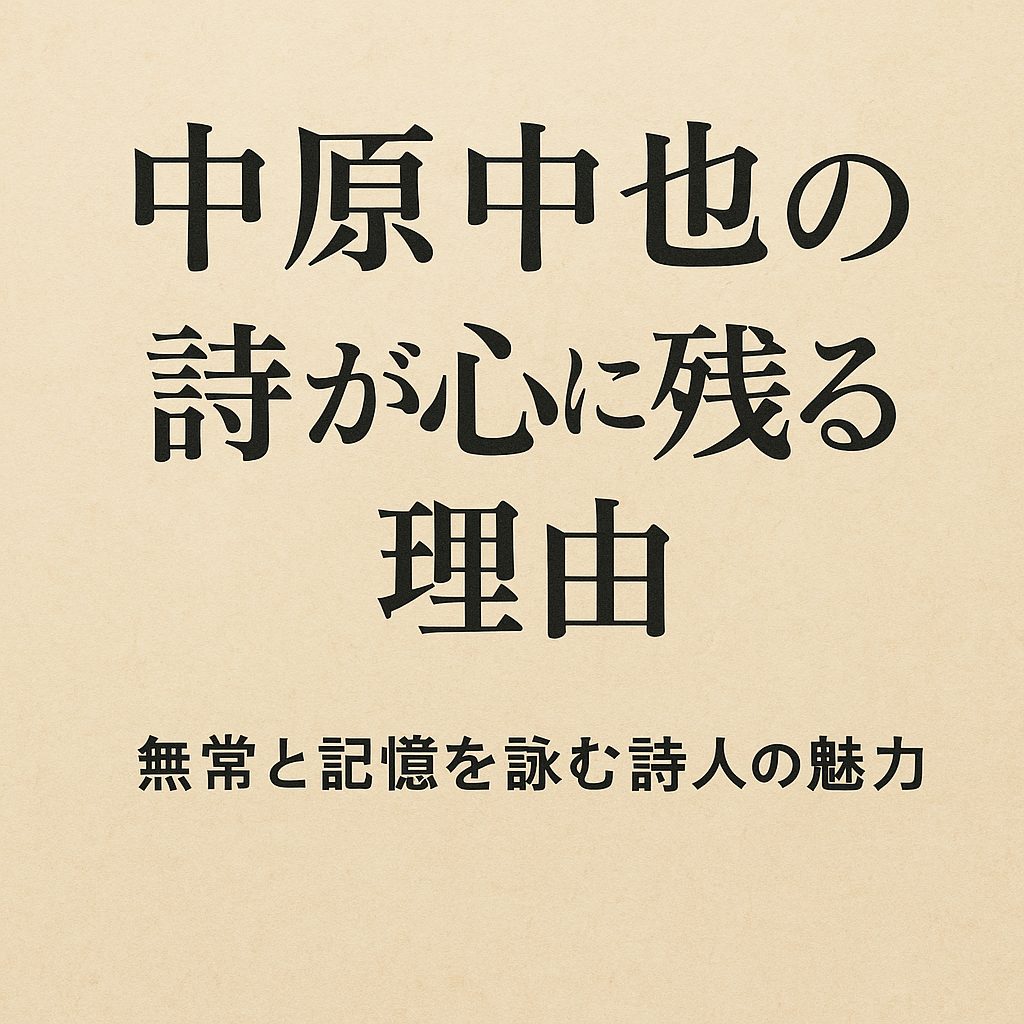


コメント