【数】について 〜 ピュタゴラス派・プラトン派を気取った古代エジプト人のごとく
序論
古代において「数」という概念は、単なる計算の道具に留まらず、世界の本質を読み解く鍵として神聖視された。本稿の筆者はカバラ(ユダヤ神秘思想)には関心も知識も持ち合わせていないため^[注釈1: カバラとはユダヤ教の神秘主義思想であり、文字や数に秘められた象徴的意味を読み解く伝統である]、主として聖書と古代ギリシア哲学の知見にもとづいて「数」への讃美を試みる。以下では、ピュタゴラス派とプラトン派の数に関する思想を概観しつつ、古代エジプト人になったつもりでその英知に思いを馳せ、論理的に「数」の持つ意義を考察したい。
ピュタゴラス派における数の神聖性
古代ギリシアの哲学者ピュタゴラス(ピタゴラス)とその学派は、「万物の本質は数である」という命題を掲げ、数そのものを宇宙の根源(アルケー)とみなしたmindmeister.jp。ピュタゴラス派にとって、数は単なる数量ではなく万物を構成する原理であり、物事の背後に秩序と調和をもたらすものであったとされる。「テトラクテュス」と呼ばれる三角形の点の配列(1から4までの自然数の総和である10個の点を三角形状に配置した図)は彼らにとって神聖な象徴であり、10という数が完全性を示すものと考えられていたja.wikipedia.org。ピュタゴラス派はまた、音楽の和音が簡単な整数比(たとえばオクターブは2:1、完全五度は3:2)の関係にあることを発見し、これにより自然界の調和も数的比例によって説明できると考えた。このようにピュタゴラス派は数に霊妙な力と説明原理を見いだし、宇宙は数的法則によって秩序づけられていると説いたのである^[注釈2: アリストテレス『形而上学』I巻5章には、ピュタゴラス派が「万物は数に他ならない」と唱えた旨の記述が見られる]。
プラトンと数理的イデア
ピュタゴラス派の思想は、のちの哲学者プラトンにも大きな影響を与えた。プラトンはイデア論を提唱し、可感的世界の背後に永遠不滅のイデア(真の実在)が存在するとしたが、その中には数学的な対象、すなわち数や幾何学的形態も含まれるja.wikipedia.org。彼にとって数的真理は感覚に頼らず理性によってのみ把握される不変の真理であり、イデア界に属する崇高な存在であった。プラトンの著作『国家』における教育論では、算術や幾何学といった数学の修養が魂を高次の認識へと導く重要な段階と位置付けられている。また対話篇『ティマイオス』では、宇宙の魂が調和ある数比によって構成されたと述べられているsaitoutakayuki.com。例えば、創造主は宇宙を構成する際に1,2,4,8および1,3,9,27といった比例関係を用いて世界霊魂の調和を築いたとされる(それは音階に通じる比例でもあった)。このようにプラトンは数的構造を宇宙論や存在論に組み込み、数を秩序と理法の象徴として讃えている^[注釈3: プラトン対話篇『ティマイオス』において、デミウルゴス(創造神)は世界魂を構成するのに調和的な数比を用いたと語られる(たとえば1:2:4:8および1:3:9:27の比例数列)]。
聖書に見られる数の象徴と秩序
ピュタゴラス派やプラトン派のような体系的数理哲学とは異なるものの、古代のヘブライ・キリスト教的伝統においても「数」はしばしば特別な意味を担ってきた。聖書の記述には、世界創造が6日間で行われ7日目に休息が与えられたことや(創世記2章2–3節)、イスラエルの部族の数が12であること(創世記35章22–26節)、弟子の数が12であること(マタイによる福音書10章1–2節)など、重要な場面で特定の数が登場するja.wikipedia.org。これらの数字は象徴的な秩序や完全性を表すものと伝統的に解釈されてきた。例えば「七」は神による創造の完成や聖別を象徴し、「十二」は民のまとまりや完全な集合体を暗示する数とされる^[注釈4: 聖書において「七」は完全・神聖を表す(例:一週七日、黙示録における七つの封印)、また「十二」はイスラエル十二部族やキリストの十二使徒に見られるように公的な集団の完成数とみなされる]。このような数の象徴は聖書本文そのものでは明示的に哲学化されてはいないが、後世の神学者たちは数に潜む意味を読み解こうと試み、世界が**「尺度と数と量によって」整然と造られたという知恵文学の言葉(『知恵の書』11章20節)に普遍的な秩序原理を見出すこともあった。すなわち、ヘブライ的伝統においても数は神意にもとづく秩序と調和を読み取る手がかり**となりうるものとして尊ばれてきたのである。
結論:数への讃美と古代的思惟
以上見てきたように、ピュタゴラス派の数学的宇宙観からプラトンの哲学的数理念、そして聖書に垣間見える数の象徴性に至るまで、古代の思想家たちはそれぞれの立場から「数」に特別な意義を見出してきた。数は人間の理性が捉えうる秩序そのものであり、混沌とした現象世界に隠された調和を言語化する原理である。ピュタゴラス派にとっては数的関係こそが宇宙を支配し、プラトンにとっては数的真理がイデア界の一端をなす。そして聖書的伝統において数は神の創造の秩序を示す符号とも読める。まさしく「数」は時代と文化を超えて宇宙の言語として機能し、人間に知的秩序と美をもたらしてきたのである。
古代エジプト人に扮した気分で振り返れば――エジプト文明は太古より天文学や幾何学の知識で名高く、その叡智はピュタゴラスらギリシア人にも影響を与えたと伝えられる。もし彼らがピュタゴラス派やプラトン派の思想に触れていたなら、自らの数学的伝統に誇りを持ちつつ深い共感を覚えたに違いない。数への讃美は、東西を問わず古代人の知的営為に通底するテーマであり、数のもたらす秩序と調和に対する畏敬の念は普遍的なものだったのである。現代に生きる我々もまた、彼ら古代の英知に学び、数という概念に秘められた美と論理に思いを致すとき、悠久の時を超えて真理の一端に触れることができるだろう。
注釈
-
カバラと数秘 – カバラは中世以降のユダヤ教神秘主義思想であり、ヘブライ語の文字や単語に対応する数値(ゲマトリア)を用いて聖典の隠された意味を解釈する手法で知られる。本稿ではカバラ的数秘術には立ち入らない。
-
ピュタゴラス派の「万物は数」 – アリストテレス『形而上学』第I巻5章によれば、ピュタゴラスとその門下は万物の究極原理を数に求め、「数によりあらゆるものが構成される」と考えていた(アリストテレス『形而上学』Α5, 985b)。
-
プラトンの宇宙構成における数比 – プラトン『ティマイオス』(35b–36d)では、創造神が世界魂を調和ある比例数で構成したと述べられている。具体的には1, 2, 4, 8と1, 3, 9, 27という二つの比率数列を組み合わせて調和的な中比を作り出し、魂全体を幾何学的に区分したとされる。この数的構成は音楽の調和(完全四度や五度の比など)にも対応している。
-
聖書における数の象徴性 – 聖書本文には数の象徴に関する教義的解説はないが、その後の伝統において解釈が与えられてきた例として、「七」は創造の完成を表す完全数とされ(週の七日制やレビ記の七年ごとの安息年など)、また「十二」は神の民の完全な構成を示す数と考えられている(イスラエル十二部族、イエスの十二使徒など)。中世の神学者はさらに、神が「全てを数と尺度と量によって整えられた」(前掲『知恵の書』11章20節)ことに宇宙の秩序原理を読み取った。

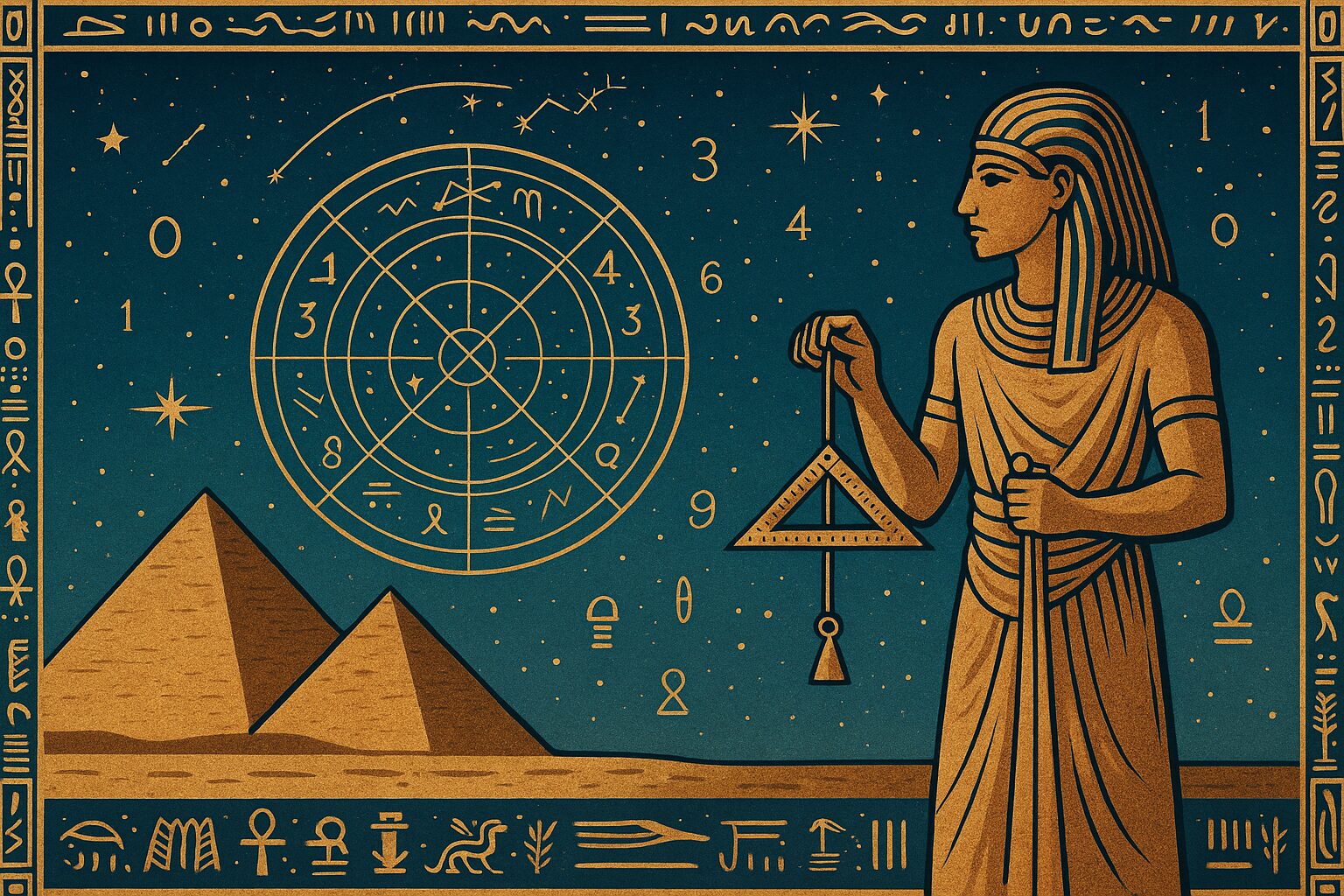


コメント