アラトス『星辰譜』レビュー|夜空を詩に綴った古代の星座ガイド
紀元前3世紀、マケドニアに生きた詩人アラトス(またはアラートス)。プラトンやアリストテレスより少しあとの時代に、彼は神話と天文学が交差する時代背景のなか、空の星々を詩で描いた。
彼の代表作『現象(ファイノメナ)』は、現在の星座の原型となる44の星座を詩としてまとめた作品であり、後にヒッパルコス、プトレマイオス、アラビアの「知識の館」を経て、現代の星座早見盤にまで受け継がれている。
今回紹介するのは、その唯一の邦訳版『星辰譜』(京都大学出版会・西洋古典叢書『ギリシャ教訓叙事詩集』収録)である。
星座早見盤、覚えていますか?
“星座早見盤”と聞いて、懐かしさを覚える人も多いだろう。小学校の理科の授業で使った記憶はあっても、テストが終わればそのまま引き出しの奥へ――そんな扱いだったのではないか。
あるいは子どもが学校で使っているのを見て、「そういえばこんなのあったな」とふと思い出す。やがて夜空を見上げることもなくなり、いつの間にか大人になっていく。
けれど星座は、古代バビロニアの時代からずっと変わらず、美しい配置で夜空に輝いている(と思う)。人生に迷ったときや、失恋でもしない限り、夜空をゆっくり眺めるなんてことは――もうほとんどないのではないだろうか。
しかも見上げたとしても、どれがどの星かなんて、まずわからない。それだけ星空は複雑で、豊かな構造を秘めている。
詩で語られる“44の星座”
アラトスの『星辰譜』では、夜空に浮かぶ星座たちが神話とともに描かれ、空の構成が一つ一つ詩的に紹介されていく。テレビもスマホもなかった時代、農業は季節の変化を読むことと密接に結びついており、星座を知ることは生きるための知識だった。
星座はまた、航海に出る船乗りたちの命綱でもあった。星の動きは羅針盤であり、天気予報であり、時間を測る手段だった。農業があって社会・仕事があり、家族があって労働・休息があったのだろうか。技術は情報に源を求める――今も昔も変わらない。
この作品の前半は、天空にある星々の位置と名前を描き出し、後半では月の形、鳥の動き、蛙の鳴き声など、地上の現象から天候や季節を読み取る術を教えている。たとえば「燕が低く飛ぶと雨」「蛙が鳴けば気温が下がる」など、どこか懐かしさを感じさせる民間伝承も多く登場する。
しかし本作の最大の魅力はやはり、古代人がどのように夜空を見ていたのか、その“空を見る感性”が詩として鮮やかに記されている前半部分にあると言えるだろう。
夜空を見上げるということ
アラトスはヒッパルコスやプトレマイオスのような天文学者ではなかったが、詩人としての繊細な感性をもって星々の動きと季節の移ろいを描いた。
『星辰譜』は、忙しい日常に追われ、空を見上げることすらなくなってしまった私たちに、失われた「星座を見る感覚」を呼び覚ましてくれる一冊である。
ただし夜や早朝に一人で空を見上げていると、近所の人にちょっと不審がられるかもしれない。周囲に人がいないことを確認してからが無難かもしれない。それほどまでに、私たちは“空を見上げる”という行為から遠ざかってしまっているのだ。
関連リンク・参考文献
- 📘 プラトン『ティマイオス』覚書――宇宙と魂をめぐる幾何学的神話
- 📘 アリストテレスの宇宙論|天動説と形而上学
- 🔭 【天体観測】肉眼ではじめて見る「木星」
- 🔭 【天体観測】「双眼鏡」を使った天体観測〜感動の星たち
📚 書籍リンク
※京都大学出版会『ギリシャ教訓叙事詩集』所収

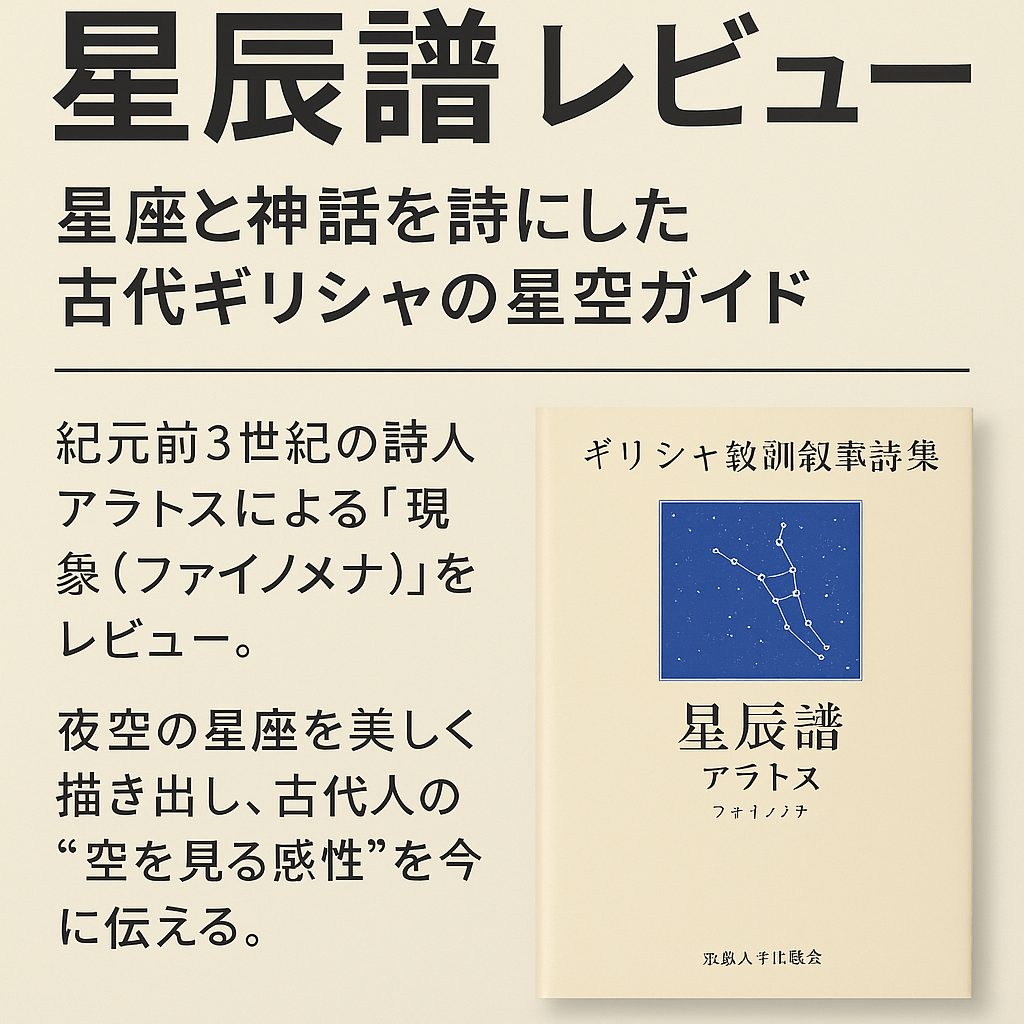


コメント