三島由紀夫『太陽と鉄』レビュー|葉隠と筋肉の哲学、美と死の交差点
死と美のあいだに
『太陽と鉄』——三島由紀夫が自決のわずか3年前に著したこの評論は、まさに彼の“遺言”のような一冊です。そこには彼の死生観、美意識、肉体と精神、文と武の両道にかける情熱が、剥き出しのまま綴られています。
念のため二度読みました。いや、それくらい読む必要のある本です。
ちなみに今、澁澤龍彦の『快楽主義の哲学』も併読していたのですが、レビューは別記事にしました(こちら→ 澁澤龍彦『快楽主義の哲学』と奇妙な三角形)。
両者ともに極端で、自意識と哲学の混成カクテルのような本。たとえるならば、『太陽と鉄』と『快楽主義の哲学』を混ぜてステアすれば、ジンとビールの「ブルドッグ」ができあがるでしょう。
内容:筋肉の哲学書
まず、本書は小説ではありません。私も図書館でうっかり小説だと思って借りましたが、実際は筋トレと思想が合体した独白的エッセイです。
全体の半分以上は、己の身体を「鉄」(=ダンベル)で鍛え上げた日々の自慢話。しかしそれがただのナルシシズムでは終わらない。
三島は「肉体は言葉を持つ」と主張し、筋肉質な身体にこそ真の文体が宿ると語ります。つまり、彼にとって身体とは“哲学を刻む彫刻”なのです。
クライマックスは、自衛隊でF104戦闘機に乗せてもらった体験談。文字通り「天空に昇る」ような境地を得て、彼はこのとき自らの“頂点”に到達したようです。
葉隠の再解釈として
『太陽と鉄』は、三島が愛読した『葉隠』を自分なりに現代に読み替えたような書でもあります。
武士道的精神、特に「大高慢であれ」「皮膚にこそ武士の価値が現れる」といった思想が、彼の肉体礼賛と通底しています。
彼はかつて、自決の際に自らの血で「武」の字を書くつもりだったそうです。実現はしなかったものの、文と武の両道を志した者としての象徴的行為でしょう。
文は花を咲かせる行為であり、武はその花を潔く散らすこと。そう語る彼の思想は、そのまま最後の行動に反映されています。
読者への鞭打ち
正直に言えば、多くの読者は途中で腹が立って投げ出すかもしれません。
「何を偉そうに」と思ってページを閉じたくなる。しかし、そこをこらえて読まなければ、バルコニーで演説しようとした彼にヤジを飛ばした自衛隊員と同じになってしまう。
私自身も、メタボ気味の中年です。読了後、思わず軽い筋トレを始めてしまったほど。
なぜなら「精神の怠惰は太鼓腹に現れる」「怠け者は想像力を言い訳にする」などと、これでもかと突き刺してくるからです。ぐうの音も出ません。
太陽と供犠
三島は、太陽に捧げる生贄のように、自衛隊のバルコニーで自らの血と内臓を自然に捧げました。
マヤ文明の人身供儀を思わせるこの比喩は、単なる思いつきではなく、本書の構造的核心です。
鉄(筋トレ)と太陽(理想)は、彼にとっての農耕具であり、彼の肉体という「畑」を耕すものでした。
F104と未完の戦争
本書の最も輝かしい場面は、F104戦闘機に搭乗した瞬間でしょう。
若き日に兵役検査で落ち、戦争に行けなかったという挫折。それを彼はこの空中飛行で取り戻したかったのかもしれません。
彼は“戦わなかった世代”の罪悪感を一身に背負い、F104で一瞬の“特攻”を擬似体験したのです。
まとめ:強すぎる思想、でも正直効く
この本は、筋肉と死を通じて人生を考え直せと迫ってくる。強引でファシズム的な論理展開もあるが、それゆえに読む側の“怠惰”を突いてくる。
筋肉を持たぬ人間だけが、マッチョを嘲笑する。そう三島は言いました。
まったくもって耳が痛い。痛いが、それでも一読の価値は間違いなくあります。

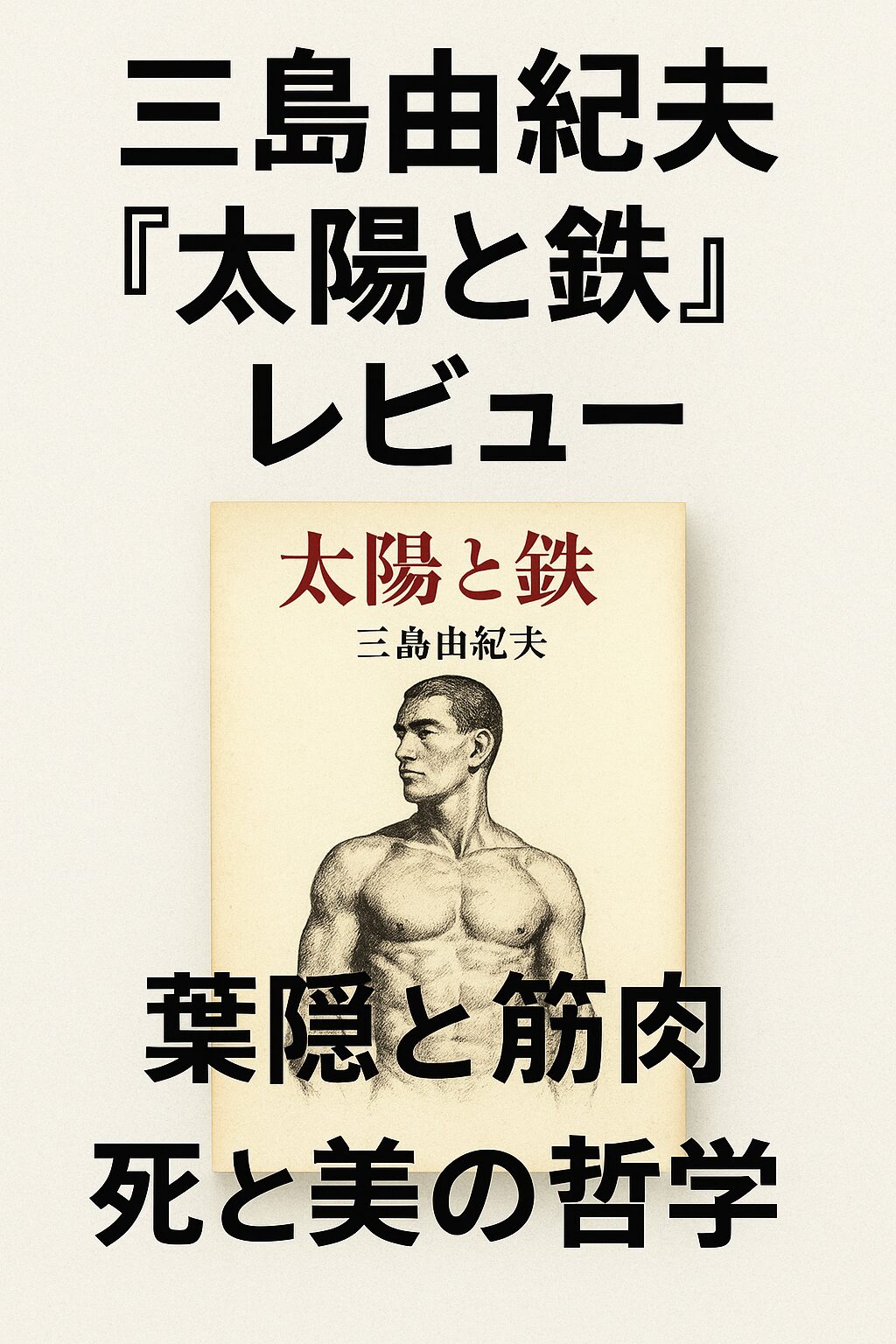


コメント