舩坂弘『英霊の絶叫』レビュー|三島由紀夫と「武士道」の宗教性
「武士道」という名の宗教
日本人の「死生観」を宗教ではなく「武士道」に求めるのは、一見暴論のようでいて意外に的を射ている。葬儀では仏教に倣い、ハロウィンやクリスマスではキリスト教に倣う。時に新興宗教の教義にも身を委ねる日本人は、実のところ明確な信仰を持たない人々である。
しかし、「死に方」に美学を求める日本人の根底には、宗教ではなく「武士道」という無名の教義が浸透している。死を選ぶことにすら価値を見出すその思想は、西洋のキリスト教的倫理観──自殺は罪──とは根本的に異なる。
もし「武士道」を一つの宗教とするならば、それは教祖も教義も経典も持たぬ、死を崇高とする戦士の宗教である。人を救わず、ただ美と強さと誇りのために生き、潔く死ぬことを良しとする。
アンガウルの地獄絵図──日本版『プライベート・ライアン』
本書は太平洋戦争末期、パラオ諸島のアンガウル島で玉砕戦を生き延びた舩坂弘の壮絶な記録である。三島由紀夫による序文を伴い、まさに「武士道の証明」とも言える戦争文学の一書だ。
通信が遮断され、補給も絶たれた中、斬り込み隊による夜襲、自爆、銃剣突撃──生き延びる術を捨てた戦士たちは、まさに死ぬために戦っていた。硫黄島以上に凄絶で、比類なき極限状況が描かれる。
五体を損じながらの自爆行動
著者自身も五カ所に致命傷を負いながらも、洞窟に潜み、最期は米軍司令官のテントへ特攻するべく、身体に手榴弾を巻きつけて匍匐前進を開始する。3日間にわたる潜行の末、首を撃たれて倒れ、一度は「戦死」と認定された。
蘇生と捕虜収容所
奇跡的に蘇生した舩坂は、捕虜として米軍の病院に収容される。キリスト教国家のアメリカ人は彼を勇敢な戦士として手厚く看護し、虐待せずジュネーブ条約を遵守した。
ここで出会ったのが、非戦闘員として従軍していた通訳クレイショー。クレイショーはキリスト教的倫理観に基づいて「生」を重んじ、舩坂は「死」を選ぶ武士道を説く。二人の思想は真っ向から対立する。
しかし、通訳はこう言った──「神サマニマカセナサイ」。それは、死は己で決めるものではなく、神の領域であるという信念だった。
桜のように散る者たち
舩坂は戦後も、自爆を企て続け、クレイショーに何度も止められる。収容所内の韓国人から、ラッキー・ストライク10本と引き換えにマッチを手に入れる場面などは、悲惨さの中に奇妙なユーモアが光る。
やがて舩坂は帰国。玉砕した千名以上の英霊の中で、奇跡的に生き残った存在として、この記録を書き残すことになる。
三島由紀夫と「関ノ孫六」
本書を読んだ三島由紀夫は深く感銘を受け、無償で序文を執筆し、添削まで施した。後に、舩坂から贈られた日本刀「関ノ孫六」は、三島が自決の際に用いた介錯刀となる。
舩坂は語る──「英霊たちが私を生かした」。ならば、同じように「武士道」では測れぬ何かが三島に刀を贈り、死を選ばせたのではないか。
まとめ
これは戦記ではあるが、単なる残酷描写の羅列ではない。自爆のために命がけでマッチを手に入れる場面には、戦中の人間的滑稽さと哀しみが同居している。
『英霊の絶叫』──それは、死を突き詰めることで生の本質を照らし出す書であり、今という空虚な日常を奇跡と思わせる力を持っている。


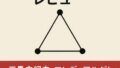

コメント