GABAN® スパイス&ハーブ主要ラインナップ紹介
世界の料理で活躍するGABAN®ブランドのスパイス&ハーブ製品を、家庭用青ラベル(純粋スパイス)と緑ラベル(ドライハーブ)に分けてご紹介します。産地や殺菌法・粉砕法にこだわり、純度100%の胡椒をブランドの原点に幅広い専門スパイスまで、高品質なラインナップが揃っていますgaban.h-spice.jp。各スパイス・ハーブの風味と用途、そして採取や製法について、レポート風に詳しくまとめました。
- 青ラベル – 純粋スパイス製品 (No.001–021)
- アニス (No.001)
- オールスパイス (No.002)
- カイエンペパー (No.003)
- カラフルペパー (No.004)
- カルダモン (No.005)
- ガーリック(にんにく) (No.006)
- キャラウェイ (No.007)
- クミン (No.008)
- グリーンペパー (No.009)
- クローブ (No.010)
- コリアンダー (No.011)
- サフラン (No.012)
- シナモン (No.013)
- ジンジャー(しょうが) (No.014)
- スイートバジルシード (No.015)
- スターアニス(八角) (No.016)
- セージ (No.017)
- セボリー (No.018)
- ターメリック(ウコン) (No.019)
- タイム (No.020)
- チリパウダー (No.021)
- 緑ラベル – ドライハーブ製品 (No.042–058)
- イタリアンパセリ (No.042)
- イタリアンハーブミックス (No.043)
- エルブ・ド・プロバンス (No.044)
- オレガノ (No.045)
- 香菜(パクチー)〈コリアンダーリーフ〉 (No.046)
- スイートバジル (No.047)
- スペアミント (No.048)
- ペパーミント (No.055)
- セージ (ハーブ) (No.049)
- タイム (ハーブ) (No.050)
- タラゴン (No.051)
- バジル (ハーブ) (No.052)
- パセリ (葉) (No.053)
- ブーケガルニ (No.054)
- ペパーミント (ハーブ) (No.055)
- マジョラム (No.056)
- レモングラス (No.057)
- ローズマリー (No.058)
青ラベル – 純粋スパイス製品 (No.001–021)
青ラベルは**純度100%**のスパイスシリーズですgaban.h-spice.jp。代表的な21種類のスパイスについて、それぞれの特徴と使い方を解説します。
アニス (No.001)
甘やかな独特の香味を持つ、世界で最も古くから使われているスパイスの一つですh-spice.jp。古代エジプトではすでに利用され、中世ヨーロッパにも広まりました。アニス特有のエキゾチックな甘い香りは、フェンネルやスターアニスと共通する成分アネトールによるものですh-spice.jp。料理よりも酒類(ギリシャのウゾやフランスのペルノーなど)や菓子の風味付けに使われることが多くh-spice.jp、種子を乾燥させホールまたは粉末で使用します。種子は未熟なうちに収穫・乾燥され、形状はフェンネルやクミンとよく似ていますh-spice.jp。
オールスパイス (No.002)
クローブ、ナツメグ、シナモンを合わせたような香りを持つことから「オールスパイス」の名が付いた香辛料ですh-spice.jp。クローブと同じフトモモ科の樹木になる未熟な実を乾燥させたもので、芳香と辛みを兼ね備えていますh-spice.jp。ホールは肉料理やシチュー、ピクルス、マリネ液などに用いられ、特に北欧のニシン酢漬けには欠かせませんh-spice.jp。パウダーはお菓子やジャム、果物(グレープフルーツなど)に振りかけてもおいしく、サラダドレッシングの隠し味にも使われる万能スパイスですh-spice.jp。16世紀後半以降に西欧に登場した比較的新しいスパイスですが、和名では三香子とも呼ばれますh-spice.jp。
カイエンペパー (No.003)
唐辛子を細かく挽いた真っ赤な極細粉で、日本では**「カイエンヌペッパー」として流通する辛味スパイスですh-spice.jp。英語で”hot”と形容される鋭い辛さ**が特徴で、口に入れるとカッと熱くなる刺激がありますh-spice.jp。単に辛いだけでなく独特の香りで料理の旨みを高め、世界中で胡椒以上に広く利用されていますh-spice.jp。原産地の中南米では紀元前から栽培され、コロンブスがヨーロッパに伝えて以降わずか100年で世界中に普及した歴史がありますh-spice.jp。粉末状なので辛みが素早く行き渡り、肉や野菜の辛味付けに重宝しますh-spice.jp。日本でも古くから親しまれ、一味唐辛子などの形でも利用されてきましたh-spice.jp。
カラフルペパー (No.004)
ブラックペパー、ホワイトペパー、グリーンペパー、ピンクペパーをミックスした4色のペッパーです。ブラックペパーは胡椒の未熟果実を果皮付きで乾燥させた刺激的な辛さと香り、ホワイトペパーは完熟果実の果皮を除いて乾燥させた穏やかな辛味と香りを持ちますh-spice.jp。グリーンペパーは未熟な緑色の実を塩漬けや酢漬けで保存したり、フリーズドライ製法で乾燥させて緑色と爽やかな風味を残したものでh-spice.jp、料理に彩りも与えますh-spice.jp。ピンクペパーはウルシ科の植物の実で辛みはほとんどありませんが、彩りとして混合されていますh-spice.jp。カラフルペパーは料理の仕上げにミルで挽いて振りかけると、色合いの美しさと様々な胡椒の風味を一度に楽しめますh-spice.jp。
カルダモン (No.005)
爽やかな芳香とピリッとした辛味、ほろ苦さを併せ持ち、「スパイスの女王」と称される高価な香辛料ですh-spice.jp。エスニック料理によく合う独特の風味で、サフランやバニラに次ぐ高級スパイスでもありますh-spice.jp。ショウガ科の多年草のさや状の果実をまだ緑色のうちに収穫し乾燥させ、中の黒い種子をスパイスとして利用しますh-spice.jp。使用時はさやごと潰すか、種子を取り出してすり潰して使い、少量でも香りが強いので入れ過ぎに注意しますh-spice.jph-spice.jp。カレーやひき肉料理の風味付けに欠かせず、甘い菓子やパン、チャイなどの飲み物にも用いられますh-spice.jp。中東ではカルダモンのさやや種子を煮出した湯で淹れるカルダモンコーヒーがもてなしの飲み物として知られていますh-spice.jp。
ガーリック(にんにく) (No.006)
世界中の料理に欠かせない代表的な香味野菜で、スパイスというより調味野菜ですが、乾燥ガーリックも広く利用されますh-spice.jp。独特の強い香りと辛味を持ち、生のにんにくは肉や魚の臭みを消す効果がありh-spice.jp、西洋料理や中華・韓国料理などで下味や風味付けに多用されますh-spice.jp。乾燥スライスやパウダーは手軽に使え、手や器具に匂いが付きにくい利点がありますh-spice.jp。生にんにくは加熱すると辛味が和らぎ香りも甘く穏やかになるためh-spice.jp、炒め油で香りを出す(アーリオ・オーリオ)ほか、アイオリソースやバーニャカウダなど各種ソースにも大量に使われますh-spice.jp。保存時は乾燥品が湿気を吸いやすいため注意が必要ですh-spice.jp。
キャラウェイ (No.007)
ディルに似た爽やかな香りとほのかな甘み、ほろ苦さを持つセリ科の種子スパイスですh-spice.jp。古代ギリシアではキャラウェイ入りのパンが作られていた記録があり、非常に歴史の古いスパイスでもありますh-spice.jp。地中海沿岸原産の二年草で、2年目に咲く花の実を褐色になるまで茎ごと乾燥させ、種子を利用しますh-spice.jp。ザワークラウト(キャベツの発酵漬物)には欠かせない香り付けでありh-spice.jp、肉や魚よりも野菜・果物、チーズ、パンや焼き菓子によく使われますh-spice.jp。例えばライ麦パンに練り込んだり、果物の焼き菓子やシロップ煮に少量加えたり、野菜を茹でる湯に入れて風味付けすることもありますh-spice.jp。また、北欧のアクアビットやオランダのキュンメルといった蒸留酒の香り付けにも用いられていますh-spice.jp。
クミン (No.008)
「カレーのいい匂い」の中心となる香りを持ち、日本人にも馴染み深い代表的スパイスですh-spice.jp。古代から利用される歴史ある香辛料で、現代では西欧よりインド・中東、メキシコ、東南アジア、アフリカなどエスニック料理に不可欠ですh-spice.jp。セリ科一年草の細長い種子を乾燥させたもので、形はキャラウェイに似ていますh-spice.jp。ホールのクミンはインド風カレー作りで最初に油で炒めて香りを引き出す重要なスパイスで、野菜炒めに加えても風味が一変しますh-spice.jp。パウダーはカレーパウダーの主原料であり、料理全般に広く使われますh-spice.jp。肉料理との相性が良く、西洋ではソーセージやミートローフに加えたり、ピクルス・チーズ・パンにも使われますh-spice.jp。クミンを炊き込んだクミンライスはカレーや各種エスニック料理によく合う定番ですh-spice.jp。
グリーンペパー (No.009)
胡椒の未熟な実を緑色のまま乾燥させたものがグリーンペパーです。胡椒(ペッパー)は「スパイスの王様」と称され、中世ヨーロッパで金と同価値で取引されたほど珍重された歴史がありますh-spice.jp。グリーンペパーは色を保つため未熟果を塩漬けや酢漬けにしたり、近年ではフリーズドライ製法で乾燥されますh-spice.jp。ブラックペパー(未熟果の乾燥)ほどの強い刺激はなく、緑の彩りと爽やかな香りが特徴です。ホールのまま肉のパテやひき肉料理に加えられることも多く、欧米で一般化したのは1950年代以降と比較的新しいスパイスですh-spice.jp。現在ではブラック・ホワイト・グリーン・ピンクの4色胡椒を混ぜた「カラフルペパー」などとしても親しまれ、サラダやソテーに挽きかけて見た目と香りを楽しみますh-spice.jp。
クローブ (No.010)
バニラに似た甘さを感じさせながらも刺激的で爽やかな極めて香りの強いスパイスですh-spice.jp。肉の臭みを抑える効果があり、その強い芳香ゆえに中世西欧では魔除けにも使われたと伝えられますh-spice.jph-spice.jp。フトモモ科の熱帯性常緑樹の花のつぼみを乾燥させたもので、蕾が開花する前に摘み取らないと香りが極端に弱くなる繊細な素材ですh-spice.jp。料理ではホールのクローブを玉ねぎに刺してポトフなどの煮込み料理に加えたり、塊のハムに刺してローストするなどして使いますh-spice.jp。パウダーは挽肉を使うハンバーグやミートボールの隠し味に少量加えたり、焼き菓子や果実のデザートに利用されますh-spice.jp。甘いものとも相性が良く、焼きりんごにホールを刺して香り付けすることもありますh-spice.jp。なお使い過ぎると香りが強すぎるため、ポトフなら3~4本程度に留め、ホール使用後は食前に除くようにしますh-spice.jp。
コリアンダー (No.011)
コリアンダーシード(乾燥種子)は甘くまろやかで柑橘を思わせる香りとほのかな辛みを持ち、古くから世界各地で愛用されてきたスパイスですh-spice.jp。地中海原産のセリ科一年草で、成熟した種子を十分に乾燥させて使用しますh-spice.jp。クミンと並んでカレー粉の主要原料であり、カレー調合やピクルス、ソーセージ、シチューなどに欠かせませんh-spice.jp。クセが少なく使いやすい風味のため、クッキーや焼きリンゴといった菓子類にも合い、生の桃や洋梨にパウダーを振りかけて甘みを引き立てる使い方もありますh-spice.jp。一方でパクチーなどと呼ばれる生の葉(香菜)は強い独特の青臭い香りがあり、同じ植物由来ですが風味は大きく異なりますh-spice.jp。西欧では伝統的にコリアンダーシードのみ利用され、香菜の葉はほとんど使われませんh-spice.jp。
サフラン (No.012)
サフランは紫色のクロッカスの花の雌しべを乾燥させた世界一高価なスパイスですh-spice.jp。ほのかで上品な芳香を持ち、料理に美しい黄金色の着色を与えますh-spice.jp。10gのサフランを得るのに1500輪以上の花が必要で、摘み取りから雌しべ3本の手作業での採取・乾燥まで伝統的手法で製造されるため非常に高価になりますh-spice.jp。収穫は秋に花を一つひとつ手摘みし、雌しべを取り出して直火であぶるようにゆっくり乾燥させますh-spice.jp。水に溶けやすい色素クロシンを含み、少量を湯に浸して色・香り・味を十分に抽出してから使うのがポイントですh-spice.jp。代表的料理のスペインのパエリヤや南仏のブイヤベース、イタリアのミラノ風リゾットには欠かせず、ターメリックでは代用できない独特の風味がありますh-spice.jp。はちみつと湯で抽出したサフランを混ぜて作るサフランソースをヨーグルトやアイスにかけると、手軽に高貴な香りを楽しめますh-spice.jp。
シナモン (No.013)
ほのかな甘みと独特の芳香、わずかな辛味を持つ樹皮由来のスパイスで、世界で最も古くから知られる香辛料の一つですh-spice.jp。紀元前2000年以上前、古代エジプトではシナモンを求めて航海に出た記録も残っていますh-spice.jp。原料はクスノキ科の常緑樹の樹皮を乾燥させたもので、香り高いセイロン種(真のシナモン)とカシア種(中国桂皮)の2系統が代表的ですh-spice.jp。日本で古来「ニッキ」として使われたのはカシア種で、厳密にはシナモンと種類が異なり香味も若干違いますh-spice.jp。パウダー状のシナモンは砂糖と混ぜてシナモンシュガーとして紅茶や菓子に使われ、アップルパイやかぼちゃ・サツマイモの甘煮など甘い料理に欠かせませんh-spice.jp。ホールはシナモンスティックとも呼ばれ、ミルクティーに加えてシナモンティーにするほか、エキゾチックな香りを活かしてインドや中近東の煮込み料理にも使われますh-spice.jp。
ジンジャー(しょうが) (No.014)
生姜と同じ植物由来のスパイスで、乾燥ショウガを粉末や粒状にしたものですh-spice.jp。生の生姜は日本や中国、東南アジアで料理に広く使われますが、西洋では古くから乾燥ジンジャーを菓子など甘いものに利用してきましたh-spice.jp。たとえば中世以来クリスマス時期に作られるジンジャーブレッドマン(生姜風味のビスケット)はジンジャーのお菓子の代表格ですh-spice.jp。またジンジャーエールやジンジャービールなど飲料にも古くから生姜の風味が活かされていますh-spice.jp。熱帯アジア原産のショウガ科多年草の地下茎を乾燥させたジンジャースパイスは、ピリッとした辛味と爽やかな香りが特徴です。西洋では料理そのものへの利用は少ないものの、ジンジャークッキーやプディングなどで好まれ、日本でも紅茶に入れてジンジャーティーにするなど親しまれていますh-spice.jph-spice.jp。
スイートバジルシード (No.015)
バジル(シソ科一年草)の種子で、水に浸すと表面がゼリー状に膨らみ体積が30倍にもなるユニークな素材ですh-spice.jp。東南アジアでは古くからデザートの材料として用いられ、ココナッツミルクなどに浸してぷるぷるの食感を楽しみますh-spice.jph-spice.jp。日本では江戸時代に目に入ったゴミを洗い流す用途に使われ、「目箒木(めぼうき)」の和名が付いたという逸話がありますh-spice.jp。イタリア料理には種子は使われませんが、現在は健康食品やドリンクの添加素材としても注目されています。バジルシード自体にはクセのない風味で、甘いシロップや飲み物に加えて食感を楽しむのが一般的ですh-spice.jp。
スターアニス(八角) (No.016)
中国料理で古くから使われるスパイスで、八角形に広がった星型の実が特徴的ですh-spice.jp。甘みのある芳香はフェンネルやアニスにも似ており、16世紀末に中国からヨーロッパへ伝わった際、区別のため「Star Anise(星型アニス)」と命名されましたh-spice.jp。シキミ科の常緑高木の果実で、果実が熟しきる前に収穫して天日乾燥させますh-spice.jp。木1本から収穫できるまで6年かかりますが、その後100年以上実を付けるともいわれますh-spice.jp。料理では豚肉や鴨肉の煮込み、川魚の臭み消しなどに中国料理で広く使われ、五香粉にも必ず配合される要のスパイスですh-spice.jp。杏仁豆腐ではシロップの香り付けに用いられますh-spice.jp。ヨーロッパでは料理より菓子やジャムの香り付けに使われることが多く、日本でも豚の角煮に八角を1片入れて独特の風味を付けることがありますh-spice.jp。
セージ (No.017)
よもぎを思わせる野趣ある香りと爽やかなほろ苦さが特徴のハーブですh-spice.jp。肉の臭み消しに非常に効果的で、西欧では古くから肉料理の定番ハーブとして一般的に使われますh-spice.jp。シソ科の多年草で別名サルビアとも呼ばれ、灰緑色の葉は表面にビロード状の繊毛が生えて白っぽく見える独特の姿をしていますh-spice.jp。開花直前の柔らかい葉を刈り取り、色と香りが変化しないよう日陰で乾燥させて製品化しますh-spice.jp。香味が非常に強いので入れ過ぎに注意すべきスパイスで、煮込み料理では布袋に入れ、仕上がったら取り出すとよいという知恵もありますh-spice.jp。利用法としては、ソーセージに欠かせないハーブとして名高く、イタリアの仔牛料理「サルティンボッカ」では生ハムと共に必ず用いられますh-spice.jp。また豆料理やドレッシングに少量加えてアクセントにするのも効果的ですh-spice.jp。
セボリー (No.018)
和名を「木立はっか(木立ハッカ)」ともいう、ハッカのように爽やかな香りを持つスパイスですh-spice.jp。わずかな辛みも感じられ、ヨーロッパでは**「豆のハーブ」と呼ばれるように豆料理によく使われますh-spice.jp。日本ではあまり馴染みがありませんが、西洋では古くから利用され、古代ローマでは調味料としてだけでなく薬草としても栽培されていました。セリ科ではなくシソ科に属し、一年草のサマーセボリー(香りが良い)と多年草のウィンターセボリーがあり、一般にハーブ利用されるのは香り高いサマーセボリーですh-spice.jp。開花期に新芽を摘んで乾燥させますh-spice.jp。強い香味のため入れ過ぎは禁物で、適量を守らないとかえって料理の風味を損なうことがありますh-spice.jp。豆料理全般との相性が特に良く、豆のスープや煮込み、サラダなどに用いられますh-spice.jp。そのほか卵料理やドレッシング、マリネ液の風味付けにも使われ、酢に漬け込んでハーブビネガー**を作ることもできますh-spice.jp。
ターメリック(ウコン) (No.019)
やや土っぽい独特の香りとほろ苦さを持ち、料理を鮮やかな黄色に着色する用途でも使われるスパイスですh-spice.jp。カレーパウダーには欠かせない基本素材で、日本では生薬名「秋ウコン」、沖縄では「うっちん」としても知られますh-spice.jp。ショウガ科の多年草で、生姜や熱帯アジア原産です。同じショウガ科だけに地下茎の形状もよく似ていますが、辛味や香りは生姜ほど強くありませんh-spice.jp。収穫後、一度煮沸してから乾燥し、硬い皮を削り取って粉砕しますh-spice.jp。ターメリックの色素成分クルクミンは油に溶けやすく、少量でも鮮やかな黄色を発色しますh-spice.jp(サフランの色素は水溶性で性質が異なりますh-spice.jp)。料理ではライスに混ぜてターメリックライスにしたり、カレーの付け合わせやピクルスの色付けに使われますh-spice.jp。例えばご飯を炊く際にひとさじ加えれば鮮やかな黄色のターメリックライスができ、見た目も食欲をそそりますh-spice.jp。また、米国デンバーに移民した日本人が沢庵を恋しがり、大根のピクルスをターメリックで黄色く染めて代用した「デンバー漬け」という逸話も伝わりますh-spice.jp。
タイム (No.020)
爽やかな香りとほろ苦さ、ピリッとした辛味を持ち、魚や肉の臭み消しに優れた効果を発揮する西洋料理の基本ハーブですh-spice.jp。利用の歴史も古く、紀元前7世紀のバビロニアの園芸書に栽培法が紹介され、古代ギリシアではタイムが「勇気」の象徴とされていた逸話もありますh-spice.jp。シソ科の多年草で、花が咲き始めた頃に枝先を刈り取り、葉・茎・花ごと陰干しにして乾燥させますh-spice.jp。通常の乾燥品のほかフリーズドライ品もあり、後者の方が香りや色が良いとされますh-spice.jp。タイムの香りは特に魚介の生臭みを消すのに有効で、クラムチャウダーなどシーフードのスープには定番ですh-spice.jph-spice.jp。鶏肉のソテーやクリーム煮、魚のムニエル、肉の煮込み料理など幅広い料理に使われますh-spice.jp。また、ブーケガルニ(ハーブの束)にはパセリ・ローリエとともに欠かせず、煮込みやブイヨン作りに投入されますh-spice.jp。ホールのタイムをオリーブ油や酢に漬け込み、ハーブオイルやビネガーとして風味付けすることもできますh-spice.jp。
チリパウダー (No.021)
メキシコ由来の辛味調味料で、唐辛子(レッドペパー)にオレガノ、クミン、パプリカなどを配合して挽いたミックススパイスですh-spice.jp。組み合わせに決まりはありませんが、香辛料メーカー各社が独自ブレンドを販売していますh-spice.jp。元々は中南米料理で使われていたものを米国人が製品化し、アメリカ南西部発祥の料理であるチリ・コン・カルネ(肉と豆の辛口煮込み)に不可欠な調味料として広まりましたh-spice.jp。唐辛子そのもの(チリペパー)と名前が似ていますが別物なので注意が必要ですh-spice.jp。チリパウダーを使うとひき肉料理がたちまちメキシコ風の香りになりますh-spice.jp。タコスのスパイスミートを作る際や、チリコンカン、沖縄発祥のタコライス(ご飯にタコスの具材を乗せた料理)の味付けにも欠かせませんh-spice.jp。家庭でもひき肉炒めに加えるだけで手軽にエスニック風味が楽しめます。
緑ラベル – ドライハーブ製品 (No.042–058)
緑ラベルはハーブシリーズで、料理に彩りと香りを与える乾燥ハーブ製品です。代表的なハーブとハーブミックスについて、それぞれの特徴と用途を解説します。
イタリアンパセリ (No.042)
平たい葉を持つパセリの一種で、オランダ芹(オランダゼリ)とも呼ばれますh-spice.jp。通常の縮れ葉パセリ(パラマウント種)に比べて香りや風味がやや穏やかで、最近は日本でも料理の付け合わせに見かけるようになりましたh-spice.jp。地中海原産のセリ科二年草で、1年目の柔らかい葉を収穫して乾燥させますh-spice.jp。香り成分は不揮発性で口に入れて初めて香りを強く感じるという特徴があり、乾燥品も料理に散らすことで香味を引き立てますh-spice.jp。**ブーケガルニ(香草束)**に欠かせないハーブでもありh-spice.jp、乾燥イタリアンパセリはスープの浮き実やドレッシング、フライの衣のパン粉への混ぜ込みなど用途が広いですh-spice.jp。器に盛ったサラダやパスタの仕上げに振りかけるだけで料理を引き立てますh-spice.jp。
イタリアンハーブミックス (No.043)
オレガノ、タイム、バジル、パセリなどイタリア料理でおなじみのハーブをバランス良くブレンドしたハウス食品オリジナルのミックスハーブですh-spice.jp。フリーズドライ製法で香り高く仕上げており、パスタやピザ、スープ、サラダ、肉料理・魚料理まで多用途に使える万能調味料となっていますh-spice.jp。これ1つで代表的なイタリアンスパイスが手軽に加わるため、家庭でもお店のような風味を簡単に再現でき、料理に彩りも添えられますh-spice.jp。ピザトーストに振ったり、ミネストローネに一さじ入れるだけでも本格的なイタリアンの香りが楽しめますh-spice.jp。
エルブ・ド・プロバンス (No.044)
ハーブを多用する南フランス・プロヴァンス地方発祥のハーブミックスで、「エルブ(Herbes)」はフランス語でハーブを意味しますh-spice.jp。タイム、ローズマリー、セージ、バジルなど複数のハーブを組み合わせますが、決まった配合はなく家庭やメーカーによって異なりますh-spice.jp。卵料理や魚介料理、乳製品を使った料理などに南仏らしい独特の香りを添え、ラタトゥイユには欠かせないスパイスですh-spice.jph-spice.jp。ポトフなどの煮込み料理や肉・魚の臭み消しにも用いられ、これひとつで本格的な南仏風の風味が簡単に加わりますh-spice.jp。フランス料理で代表的なハーブがバランス良くミックスされているため、料理に振るだけでお店のような香りと彩りを演出できますh-spice.jp。
オレガノ (No.045)
バジルと並んでトマトと相性抜群のハーブで、特にピザソースやトマトパスタに欠かせないイタリア料理の定番ですh-spice.jp。シソ科ハーブの中でも香りが非常に強く、爽やかさの中にやや苦みを含む芳香が特徴ですh-spice.jp。地中海沿岸原産の多年草で、開花期に先端の柔らかい部分を刈り取り乾燥させますh-spice.jp。香りが強いので使用量は控えめにすると良く、煮込み料理では生葉だと苦味が出るためドライハーブの方が適していますh-spice.jp。ピザやトマトソースのほか、オムレツやドレッシングに少量加えて香味づけに使えますh-spice.jp。またビーフシチューやラム肉料理にも合い、チリパウダー(米国風唐辛子ミックス)にも欠かせない素材ですh-spice.jp。ドライの方が香り高いため、一般的には乾燥オレガノがよく利用されますh-spice.jp。
香菜(パクチー)〈コリアンダーリーフ〉 (No.046)
コリアンダーの生の葉部分で、中国では香菜(シャンツァイ)、タイなどではパクチーと呼ばれるハーブですh-spice.jp。青臭くクセの強い独特の香りが特徴で、好き嫌いが分かれますがエスニック料理には不可欠な存在ですh-spice.jph-spice.jp。タイ料理・ベトナム料理・中南米料理などでは薬味や香りづけに頻繁に使われ、料理の上に生葉をたっぷり乗せたり、スープに加えて爽やかな香りを移しますh-spice.jp。日本でも近年パクチーブームで生の香菜を使う店が増え、乾燥パクチー製品も登場していますh-spice.jp。一方、西欧料理ではこの生葉をほとんど使わず、同じ植物の種(コリアンダーシード)だけをスパイスとして利用する伝統がありますh-spice.jph-spice.jp。自宅でもプランターで容易に栽培できるハーブで、鮮度の高い生葉をサラダやカレーに添えてエキゾチックな香りを楽しめます。
スイートバジル (No.047)
イタリア料理でおなじみのバジリコ(バジル)で、爽やかな香りは日本の青じそにも似ており、日本人にも親しみやすいハーブですh-spice.jp。トマトとの相性が特によく、カプレーゼ(生バジル+モッツァレラ+トマトのサラダ)はイタリアを代表する前菜ですねh-spice.jp。原産は実は地中海沿岸ではなくインド・スリランカで、シソ科メボウキ属の一年草ですh-spice.jp。一般にハーブとして使われているのは数あるバジルの中でスイートバジル種で、開花直前の葉を収穫して香りと緑色を保つよう低温乾燥させますh-spice.jp。乾燥バジルには通常乾燥品とフリーズドライ品があり、後者の方が香りや色が良好ですh-spice.jp。利用範囲は広く、トマト料理以外にも魚介・鶏肉・ピーマン・豆類など様々な素材に合いますh-spice.jp。バジルペーストのジェノベーゼソース(バジル+にんにく+松の実+チーズ+オリーブ油)も有名で、イタリアのみならずタイ料理やベトナム料理にも欠かせないハーブですh-spice.jph-spice.jp。
スペアミント (No.048)
メントール様成分をほとんど含まないため甘くソフトな清涼感を持つミントですh-spice.jp。欧米で古くから親しまれてきた品種で、江戸時代にオランダから日本に伝来したことからオランダハッカとも呼ばれますh-spice.jp。シソ科ハッカ属の多年草で、その香りはペパーミントに似ますが穏やかで刺激が少なく、ほんのり甘い芳香が特徴ですh-spice.jp。乾燥スペアミントはキャンディーやチューインガムなど菓子の香料としても使われ、またミントティーなどハーブティーにすると爽やかな飲み物になりますh-spice.jph-spice.jp。料理では野菜や肉料理にも合い、特にラム肉にはミントソースが定番で臭みを和らげますh-spice.jp。ペパーミントに比べ刺激が弱い分、サラダやヨーグルトソースなど幅広い用途で使いやすいハーブです。
ペパーミント (No.055)
スペアミントと別種ミントとの交配から生まれた品種で、メントールを主成分とする強い清涼感を特徴としますh-spice.jp。和名は西洋ハッカで、スーッと鼻に抜ける香りと刺激がスペアミントよりもはるかに強く感じられますh-spice.jp。キャンディーやガムの定番フレーバーであり、メントールの爽快さから歯磨き粉やリキュールの香料にも使われますh-spice.jp。シソ科多年草で栽培しやすく、日本でも夏に繁茂します。葉を満開時に刈り取り、葉と花を十分乾燥させて製品化しますh-spice.jp。砂糖との相性も良いためミント菓子やカクテル(ミントジュレップ等)にもよく利用されますh-spice.jp。ただし香りが非常に強いため他のハーブとブレンドする際はバランスに注意が必要です。肉の臭み消し効果も高く、イギリス料理ではラム肉に添えるミントソースやミントゼリーが欠かせませんh-spice.jp。
セージ (ハーブ) (No.049)
※「セージ」は前出の No.017 青ラベルにて詳述。→ セージ (No.017)を参照。
タイム (ハーブ) (No.050)
※「タイム」は前出の No.020 青ラベルにて詳述。→ タイム (No.020)を参照。
タラゴン (No.051)
甘く独特な芳香がクセになるフランス料理でお馴染みのハーブですh-spice.jp。シソ科ハーブとは異なる香りで、フランスではエストラゴンと呼ばれ最もよく使われるハーブの一つに数えられますh-spice.jp。中世以降ハーブとして利用され始め、それ以前はもっぱら薬草でしたh-spice.jp。温暖な地域原産のキク科多年草で、繊細な風味を持つフレンチ種が商業栽培されますh-spice.jp(刺激的なロシア種も存在します)。開花直前の若葉を刈り取り陰干し乾燥しますh-spice.jp。鶏肉・卵・魚介(特にエビ)など繊細な素材に合い、フランスのエスカルゴ料理にも欠かせませんh-spice.jp。またバターソースやタルタルソースなど各種ソースに加えると風味がぐっと引き立ちますh-spice.jp。酢に漬け込んだタラゴンビネガーはドレッシング作りに重宝し、家庭でもワインビネガーにタラゴンをひと煮立ちさせれば簡単に作れますh-spice.jp。
バジル (ハーブ) (No.052)
※「バジル(スイートバジル)」は No.047 緑ラベルにて詳述。→ スイートバジル (No.047)を参照。
パセリ (葉) (No.053)
日本でも洋食の彩りとしてお馴染みの縮れ葉パセリですh-spice.jp。オランダから伝来したためオランダゼリとも呼ばれ、爽やかな香りで肉・魚料理の付け合わせに古くから用いられてきましたh-spice.jp。イタリアンパセリと同じ学名を持つ変種ですが、葉が縮れており香味も微妙に異なりますh-spice.jp。セリ科二年草で、日本では園芸種としても栽培されます。香り成分が不揮発性のため、生でかじると初めて強い香りを感じられ、口直しやブレスケアとしても利用されますh-spice.jp。乾燥パセリはホール状のものとフリーズドライ品があり、後者の方が色合いが鮮やかですh-spice.jp。ブーケガルニ(煮込み用の香草束)にはローリエ・タイム等と共に必須で、微かな苦みがスープやシチューの味を引き締めますh-spice.jp。また刻んでスープの浮き実、パスタやサラダの仕上げ、フライの衣のパン粉混ぜなど用途は広く、料理に振るだけで彩りと風味が増しますh-spice.jp。
ブーケガルニ (No.054)
フランスの煮込み料理に用いられる香草の束で、料理の香りを高め素材の臭みを取るために使われますh-spice.jp。パセリ(茎ごと)・タイム・ローリエ等数種類のハーブを糸で束ねたり、乾燥なら布袋に入れて使用しますh-spice.jph-spice.jp。組み合わせは特に決まっておらず、料理人の好みや料理の種類によって変わりますh-spice.jp。生のハーブなら束ねてそのまま煮込み、乾燥ハーブならティーバッグ状にして煮込み、十分香りが移ったら途中で取り出しますh-spice.jp。ポトフやロールキャベツ、カレーなどに加えると肉の臭みが和らぎ、複雑な香りがスープに移りますh-spice.jp。ブーケガルニを使うことで家庭の煮込み料理も一段と本格的な風味に仕上がります。
ペパーミント (ハーブ) (No.055)
※「ペパーミント」は No.055 緑ラベルにて既出。→ ペパーミント (No.055)を参照。
マジョラム (No.056)
繊細で甘い芳香とほろ苦さを持つハーブで、オレガノに近い香りですがより穏やかなのが特徴ですh-spice.jp。古代ギリシア・ローマ時代から利用され、オレガノと同様にイタリア料理でよく使われてきましたh-spice.jp。植物学的にはマジョラムとオレガノが同一種かどうか議論が続いているほど近縁で(ハーブ用途上は別物とされる)、オレガノをワイルドマジョラムと呼ぶこともありますh-spice.jp。地中海沿岸原産のシソ科多年草で、開花時に葉と茎の柔らかい部分を刈り取り乾燥させますh-spice.jp。肉・卵・チーズ・野菜など様々な素材に合い、特にトマト料理にはオレガノと同様によく使われますh-spice.jp。またセージと並んでソーセージの風味付けにも利用され、西欧ではスープやソース、ドレッシングの香り付けにも重宝されますh-spice.jp。
レモングラス (No.057)
その名の通りレモンに似た爽やかな香りを持つイネ科のハーブですh-spice.jp。東南アジアやインド原産で、熱帯では草丈2mにもなる多年草ですh-spice.jp。刈り取るだけでも良い香りが漂い、レモンと同じ香気成分(シトラール等)を含んでいますh-spice.jp。元々は東南アジアの料理で盛んに使われ、タイのトムヤムクンなど酸味と辛味の効いたスープには欠かせませんh-spice.jp。茎の根元が丸く膨らんだ部分を3~4ヶ月ごとに刈り取り、しっかり乾燥させて利用しますh-spice.jp。スープや煮込みの香り付けにホールのまま入れたり、刻んで肉・魚にまぶして臭み消しに使ったりと、タイ・ベトナム・インドネシアなど東南アジア料理には必須ですh-spice.jp。煮込んでも繊維が残るため、乾燥ホールは風味出しに使って途中で除去するか、極細かくして用いますh-spice.jp。またハーブティーにするとクセがなく飲みやすい爽快な風味のお茶になりますh-spice.jp。
ローズマリー (No.058)
松葉のような細い葉を持つ常緑低木ハーブで、甘い芳香と強いほろ苦さが特徴ですh-spice.jp。料理が出来上がった後も香りが残りやすく、肉の臭み消しに良いとされますが、日本人の場合はローズマリー自体の香味を楽しむ目的で使われることも多いようですh-spice.jp。地中海沿岸原産のシソ科の潅木で、日本でも園芸用に見かけますh-spice.jp。直立性やほふく性など幾つかのタイプがあり、丈夫で育てやすい植物ですh-spice.jp。通常乾燥品とフリーズドライ品があり、フリーズドライの方が香りと発色が良好ですh-spice.jp。加熱すると香りがやや飛ぶため、思い切ってたくさん使っても程よい風味に仕上がるというコツがありますh-spice.jp。利用法としてはラム肉やジビエ(野禽獣肉)にまぶしてローストするのが西欧では一般的で、鶏肉にもよく合いますh-spice.jp。またカブやジャガイモなど野菜とも相性が良く、特にオリーブ油と和えてローストしたローズマリーポテトは代表的な料理ですh-spice.jp。
以上、GABAN®ブランドの主要なスパイス・ハーブ製品を青ラベル(純粋スパイス)と緑ラベル(ハーブ)に分けてご紹介しました。各スパイス・ハーブの特色を活かし、日々の料理に彩りと香り、そして奥深い風味をぜひ取り入れてみてください。
【参考資料】 ハウス食品公式サイト GABAN®スパイス製品一覧・スパイス大辞典gaban.h-spice.jph-spice.jph-spice.jph-spice.jph-spice.jph-spice.jph-spice.jph-spice.jph-spice.jph-spice.jph-spice.jph-spice.jph-spice.jph-spice.jph-spice.jph-spice.jph-spice.jph-spice.jph-spice.jph-spice.jph-spice.jph-spice.jph-spice.jph-spice.jph-spice.jph-spice.jph-spice.jph-spice.jph-spice.jph-spice.jph-spice.jph-spice.jph-spice.jph-spice.jph-spice.jph-spice.jph-spice.jph-spice.jph-spice.jph-spice.jph-spice.jph-spice.jph-spice.jph-spice.jph-spice.jph-spice.jph-spice.jph-spice.jph-spice.jph-spice.jph-spice.jph-spice.jph-spice.jph-spice.jp



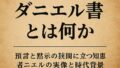
コメント