三島由紀夫『禁色』感想・紹介〜戦後文学と性愛の境界を問う長編小説
はじめに
『禁色』は三島由紀夫による戦後初期の代表的長編小説であり、その題名は平安時代において高位の官人しか着用を許されなかった「禁色(きんじき)」の衣装に由来します。ただし、本作においてはその象徴性を転じて、“禁じられた性愛”すなわち男性同性愛を主題とする小説として読むこともできるでしょう。発表は1951年から53年にかけて雑誌連載され、文庫版では600ページ近い大作です。
評価と読後感
この小説に対する評価は賛否両論です。フランスの作家マルグリット・ユルスナールは「文体がたるんでいる」「殴り書きのようだ」と手厳しい評価を残しており、また澁澤龍彦との対談で出口裕弘も「途中で挫折してしまった」と述べています。
筆者自身も、重厚な内容を期待して読了したが、その印象は芳しくありません。多くのページを占めるのは男色をめぐる遊戯と空虚な会話であり、芸術論や人生観が挿入されてはいるものの、それらは言葉遊びに近く、深みに欠けるように感じられました。
あらすじと内容
物語は老作家・俊輔と、絶世の美貌を持つ青年・悠一との出会いから始まります。青年は女性を愛せない同性愛者であり、俊輔は彼を操って、自らを裏切った女たちへの復讐を画策します。俊輔の庇護のもと、悠一は若い女性・康子と形式的な結婚をさせられ、社交界に登場していきます。
作中では、俊輔のかつての妻が情死し、その遺体が海で他人と癒着していた逸話や、悠一が康子の帝王切開に立ち会う場面など、視覚的に強烈な描写が挿入されます。これらの挿話は、死と性愛の結びつき、そして人間の肉体と精神の乖離を象徴的に示しているようにも思われます。
最終的に、悠一は俊輔のもとを去る決意をし、老作家は彼に全財産を遺して自殺するという結末を迎えます。この展開は、俊輔が追い求めた理想が崩壊する瞬間であり、同時に虚無を抱えた愛の終着点でもあります。
主題と文学的意義
『禁色』において三島は、男性同性愛を描きながらも、それを単なる性愛の問題にとどめず、美と道徳、快楽と罪、老いと若さ、権力と無力といった相反する概念のせめぎ合いとして構成しています。戦後社会において失われた価値体系と、その中での個の在り方を問う作品とも解釈できるでしょう。
ただし、それらのテーマが読者に十分に伝わるかどうかは別問題です。600ページという分量に対して、語りの密度や構成力が乏しく感じられる場面も多く、読者の忍耐を試すような構成となっています。現代的な視点から見れば、同性愛描写はもはや前衛的ではなく、むしろ時代の産物と感じられるかもしれません。
まとめ
『禁色』は、三島由紀夫の文学的野心と美学をある種の“実験”として結晶させた作品です。ただし、三島の他の名作──たとえば『仮面の告白』『金閣寺』『豊饒の海』シリーズ──と比べて、読者に強く訴えかける力はやや弱く感じられます。あえて読むなら、三島作品を網羅的に把握したい読者向けの一冊かもしれません。
文学としての歴史的価値を認めつつも、現代の読者にとっては冗長に映る可能性が高く、読み進めるには相応の覚悟が必要です。
▼三島作品レビューまとめはこちら
【三島由紀夫】作品レビューまとめ
▼当ブログ独自のおすすめランキングはこちら
【三島由紀夫】おすすめ小説ランキング

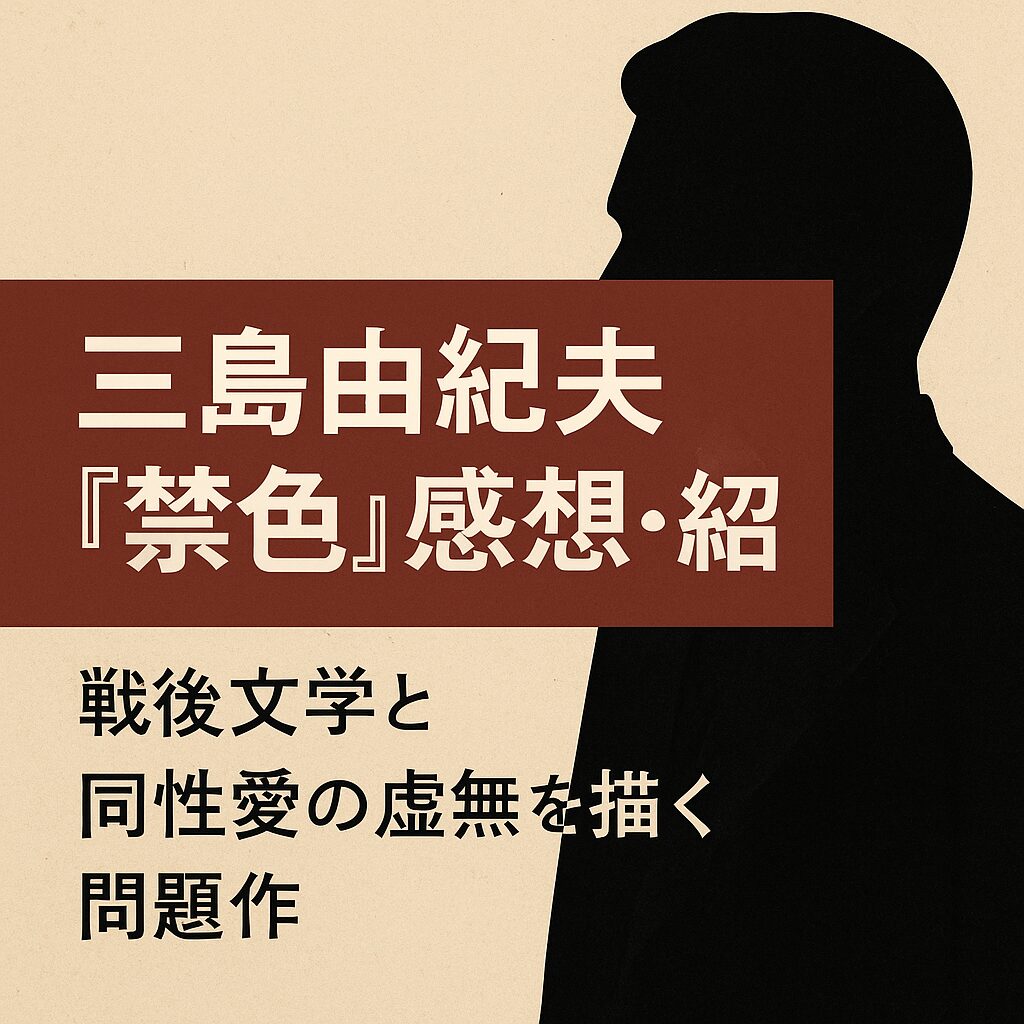


コメント