 疑似学術地帯
疑似学術地帯 『スッタニパータ』に見るブッダの理法と無明の構造
『スッタニパータ』における理法と輪廻の認識構造 ― 原始仏典に見る釈迦の思想原始仏典としての位置づけ『スッタニパータ』(Sutta-Nipāta)は、パーリ語経典『小部』(Khuddaka Nikāya)に収められた初期仏典のひとつである。...
 疑似学術地帯
疑似学術地帯  評論詐欺
評論詐欺  思考の化石
思考の化石  小説の闘牛場
小説の闘牛場 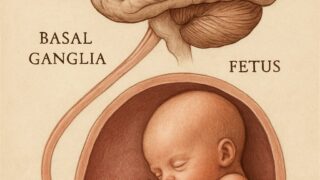 哲学的偏見
哲学的偏見  哲学的偏見
哲学的偏見  プラ保存箱
プラ保存箱  詩煩悩
詩煩悩  星を見てたころ
星を見てたころ  星を見てたころ
星を見てたころ