澁澤龍彦『サド侯爵の生涯』レビュー|サディズムと涜神の文学者、マルキ・ド・サドを読む
紹介
本書は1964年に初版が刊行され、補遺を加えて現在の形となった。筆者が手にしたのは中公文庫の第5刷(昭和58年)である。表紙や題名は一見地味だが、その中身は驚くほど刺激的で、400ページ弱に及ぶ圧巻の評伝だ。
「サディズム」の語源となった18世紀フランスの貴族・作家、ドナシャン・アルフォンス・フランソワ・ド・サドの波乱に満ちた生涯と、フランス革命を中心とした激動の時代背景を詳細に描いている。澁澤の博学が冴えわたり、随所に独自の美学と思想が織り込まれており、単なる評伝に留まらない深みを持つ。
三島由紀夫『サド侯爵夫人』との関係
本書は、三島由紀夫の戯曲『サド侯爵夫人』の直接的な着想源となった。戯曲の冒頭には「澁澤龍彦・サド侯爵の生涯による」と明記されている。さらに本作はアンドレ・ピエール・ド・マンディアルグの翻訳によりフランス語版が生まれ、1979年には劇団によって日本でも仏語上演された。思想・演劇・翻訳が交錯する稀有な文化的事件である。
三島由紀夫『サド侯爵夫人』を解説|不在のサドと6人の女たちによる倫理劇の傑作
思想と読書の糧
本書は単なる評伝ではなく、読者にとって魂の糧となる哲学書のような一面をも持つ。澁澤の筆は、血の滴る分厚いステーキのように豊かで滋味深い。思想とは読む者の精神を養うものであり、本書はその力を十分に備えている。
牢獄と創作──がんくつ王との類似
筆者は子どもの頃に読んだ『がんくつ王』の絵本を思い出した。牢屋に閉じ込められながらも信念を持ち続け、やがて脱出・復権を果たす物語である。澁澤の描くサド侯爵の姿にも、この「偉人」像と通じるものがある。
若き日のサドは性的嗜好に忠実すぎる生き方で波乱を巻き起こすが、その後、牢獄において長い試練を受けながら作家として開花していく。11年におよぶ獄中生活の中で、『悪徳の栄え』『美徳の不幸』『ソドム百二十日』といった大作が生まれた。
自由の塔と極限の創作
バスティーユの「自由の塔」と呼ばれる牢で、サドは幅12センチの紙片を12メートル繋ぎ、裏表に極小文字で『ソドム百二十日』を書き込んだ。この巻物状の原稿は、まさに命を懸けた創作行為であり、発見された時の驚きは計り知れない。
当時の獄中生活の記述も詳細で、囚人が犬を飼うような緩さと、30メートルの壁に囲まれた真っ暗な中庭など、現代では想像もできない異様さがあった。
ギロチンと恐怖政治
サドはフランス革命により牢を出るが、直後には恐怖政治の時代が訪れる。疑われただけで、弁護もないままギロチン送りとなる日々。人々の首が「キャベツを切るように」落とされる凄惨な描写には、革命の暴力性が鮮やかに浮かび上がる。
サドをめぐる女たち
妻のサド侯爵夫人ルネは、獄中の夫を長年支え続けたが、最終的には修道院に入って事実上離別した。また夫人の妹・ローネー嬢との恋や、晩年精神病院でのマドレーヌとのロリータ的愛情など、女たちとの関係はサドの人生の濃厚な要素である。
まとめ
補遺では、サドの晩年に発覚したジャンヌ・テスタル事件──キリスト像への涜神的行為や過激な儀式など──についても記されている。澁澤はそれらすべてを冷静に、しかし美学的に分析し、豊饒な文化と思想の宝庫として読者に提供する。
本書はまさに、血と魂と論理で綴られた異端の文学伝記である。

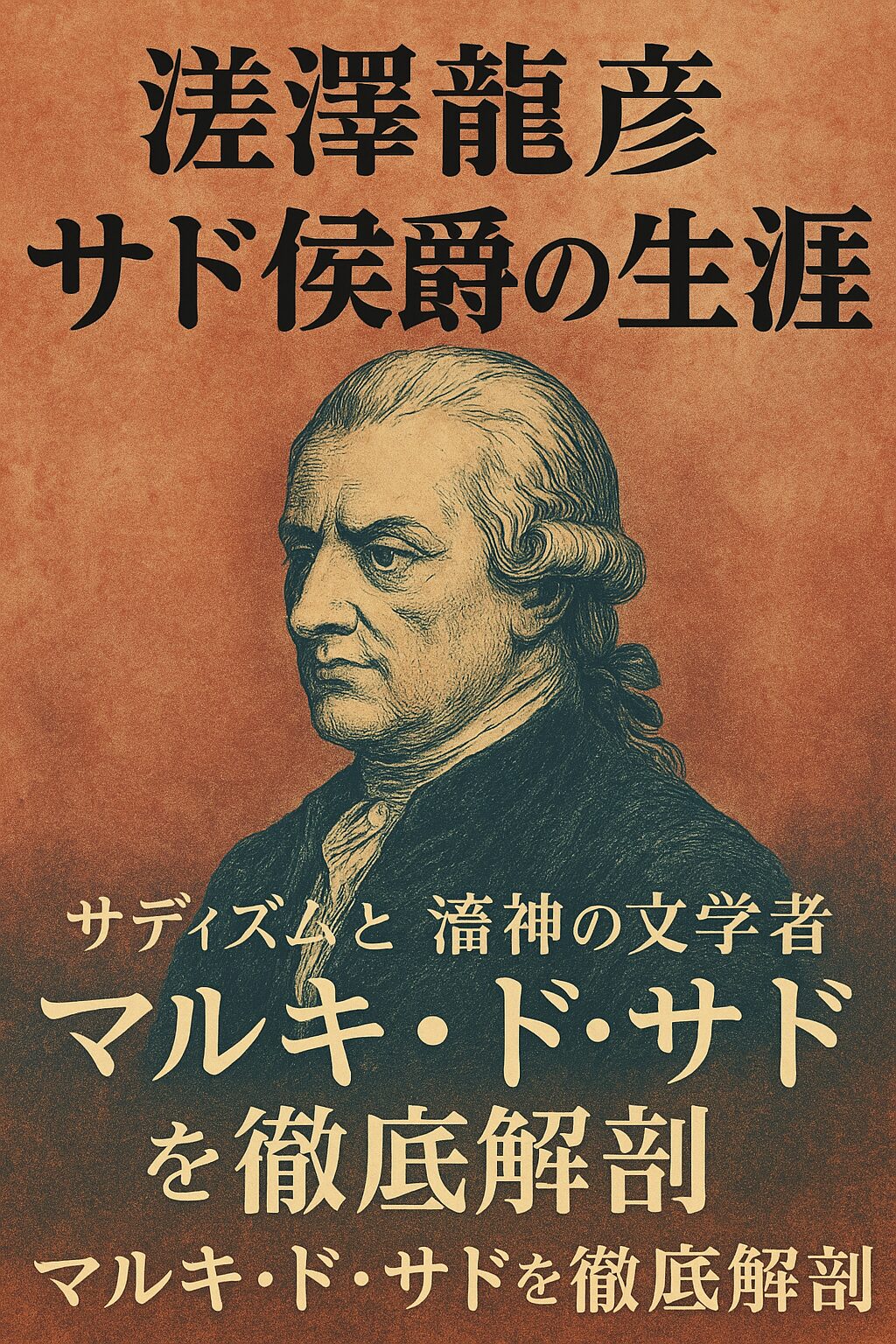

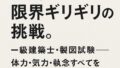
コメント