【アリストテレス】『自然学』紹介|「動くものはすべて動かすものによって動かされる」
場所と時間の哲学
「動くものはすべて動かすものによって動かされる」――アリストテレスが『自然学』で説く、あまりにも単純で根本的な理屈。加えて、「動かされるものはすべて〈場所〉および〈時間〉の中で動かされる」という明白な原理。この三つ、すなわち〈運動〉〈場所〉〈時間〉という、誰もが日常で感じている”当たり前”を徹底的に掘り下げてゆくのがこの書である。
アリストテレスは〈運動〉を、「生成」「消滅」「増大」「減少」「移動」の五つに分類する。そして運動とは、常に〈時間〉の中で、ある〈場所〉において生じるものとされる。こうした根本概念を考えるには、ゆったりとした時間と忍耐が必要だが、アリストテレスの議論には知的快楽と深い思索が待っている。
第一の動かすもの
『自然学』の名高い一節、「動くものはすべて動かすものによって動かされる」は、最終的に「第一の動かすもの」なる存在の導入へと至る。第一因としてのそれは〈動かすが、動かされない〉存在、すなわち〈不動の動者〉である。
もし第一の存在が何かに動かされているとすれば、その前にさらに動かすものが必要となる。こうした連鎖は無限に続かないため、アリストテレスは、運動と時間の彼方に〈非物体的〉で〈唯一〉なる第一動者が存在する、と結論する。複数あればそれをまとめるさらなる存在が必要になるからだ。
円運動と天界
アリストテレスによれば、〈永遠の運動〉は〈円運動〉である。なぜなら円のみが始まりと終わりを同一の点に持ち、循環するからである。そしてこの理論の帰結として、天界に存在する恒星の天体はこの円運動を行っており、それゆえに永遠に変わらないように見える。
実際には星々も変化し生成しているが、そのスパンがあまりに長いため、人間の時間感覚では「不変」と認識されるのだろう。その下に土星・木星・火星・太陽・金星・水星・月が順に配され、これらは目に見える変化を示す天体とされた。
アリストテレスは、恒星の天と7つの天界を〈不死なる神々〉とみなし、地球と月の間――「月下界」にあるすべてのものを〈可死的な存在〉とした。神々はただ円運動を繰り返す存在である。
●関連→【アリストテレス】哲学:ばっさり解説〜天動説と宇宙論
不思議な非物体
この書物は極めて不思議な哲学書でもある。「時間」とはなぜ一瞬たりとも止まらないのか? 「運動」はどこから来るのか? 「場所」とは何なのか? 「無限」と「有限」はどう異なるのか?
思考を深く進めると狂気に至りそうな問いが次々と湧いてくる。なぜ物は存在し、動き、そして変化し続けるのか。アリストテレスの答えは明快だ――〈不動で非物体、唯一の第一の動かすもの〉がある。
たとえば、10秒後に右手を上げるか左手を上げるか、それがすでに決まっているとすれば、右手を上げたならば、そうなる運命だったということである。起こることは必然として起こり、起こらぬことは起きようがない。
動かすものとしての食物
個人的な疑問として、「動くものはすべて動かすものによって動かされる」の原理が生き物にどう適用されるかを考えてみよう。
たとえば、人が右手に持った棒で石を打つとする。このとき石は棒に動かされ、棒は右手によって、右手は筋肉や神経、脳によって動かされている。さらにその神経や筋肉は、血液や酸素、栄養を媒介とした身体全体のはたらきに依存しており、つまるところ「食物」が生命運動の根源となっている。
自律神経系のように意志とは無関係に作動する身体のしくみは「運動」ではなく「現象」と言うべきかもしれない。そして〈現象〉とは、星々の運行によって動かされているとすれば――結局のところ、生き物もまた、生成・消滅・増大・減少という変化を強いられる、天界の運動に支配された存在なのだ。



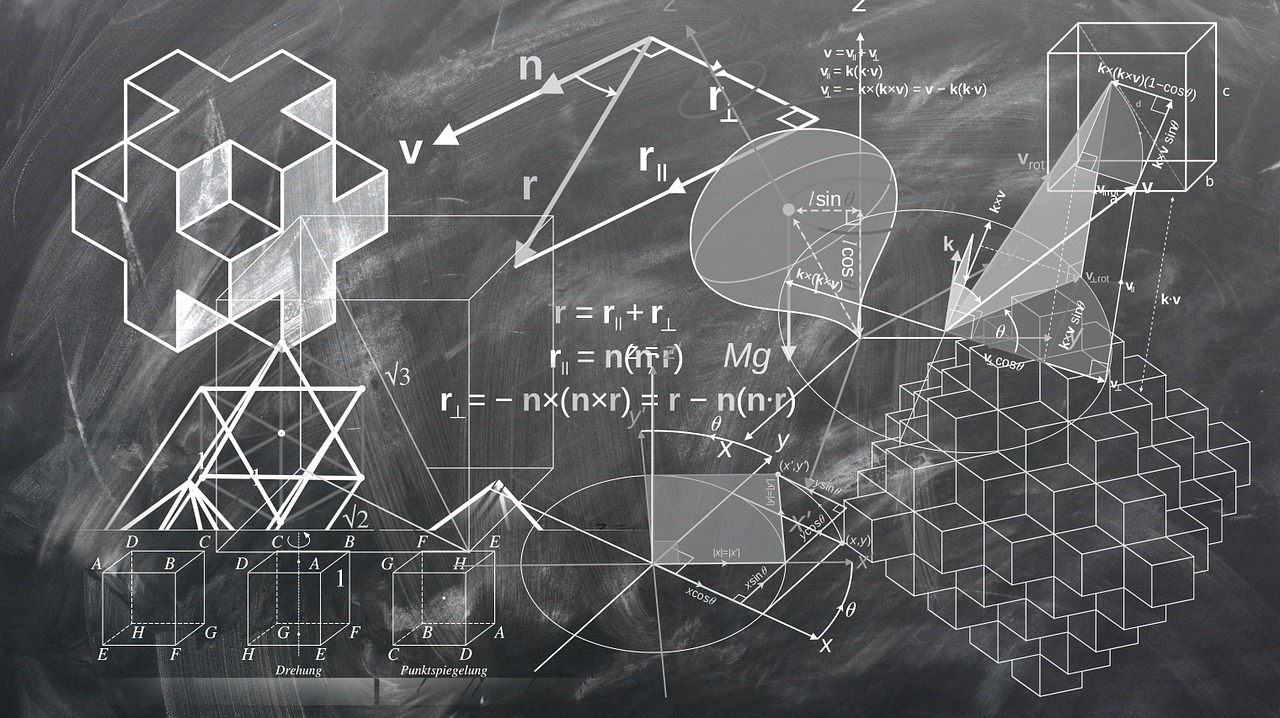
コメント