【エドガー・アラン・ポー】「早まった埋葬」レビュー|生きながら棺桶に入れられる恐怖
「死んでいる」と思われたまま埋葬される──現代の我々にとってはホラー映画の中の話だが、かつてそれは現実だった。
ポーの短編「早まった埋葬」は、そうした”生き埋め”への極端な恐怖を描いた、恐怖文学の中でもひときわ陰鬱な名作である。
本作は創元推理文庫「ポオ小説全集」第3巻に収録。ポーの代表的恐怖短編「赤死病の仮面」「告げ口心臓」などと並び、彼の内的恐怖と偏執が結晶化された一篇だ。
■ あらすじ|語り手の“過剰な恐怖”
語り手は、自身が抱える奇病──発作的な昏睡状態に陥る持病──のため、生きたまま葬られるという想像に取り憑かれている。
物語冒頭では、実際に誤って埋葬されてしまった人々の事例がいくつも語られる。納骨堂の中で蘇生し、扉に引っかかったまま立った姿勢で死亡した女性。埋葬された恋人の髪を切るために掘り返した墓の中で、蘇った死者が息をしていた話。あるいは、解剖中に電気ショックで蘇生し「僕はまだ生きている」と呟いた者──。
語り手は念入りに、自分の棺桶や墓に“脱出用の仕掛け”を施し、死後(あるいは仮死状態)に備えている。が、その不安は尽きない。
■ 墓穴の夢|悪魔が見せる幻視
彼の持病による昏睡の中では、しばしば夢が現れる。中でも印象的なのは、悪魔に連れられて墓地を巡る夢だ。
そこには、死者たちが安らかに眠るどころか、呻き、苦しみ、夢の中でも目覚められずにのたうっている。生ける屍のように。ポーが書く「死」は、決して穏やかな終末ではなく、意識の残った地獄である。
この場面は、ボードレールの詩「陽気な死者(Le Mort Joyeux)」を想起させるが、影響を受けているのはむしろボードレールの方であろう。
■ “生き埋め”の正体とは
ついに恐怖は現実となる──狩猟中に発作を起こし、気絶した語り手は、目を覚ますと暗く狭い空間の中にいた。
「ついに自分は棺桶の中に…!」と絶望し、錯乱のまま叫びを上げる。
だが、次の瞬間──
「おい、どうしたんだ!」と誰かに揺さぶられ、語り手は“仲間とともに停泊していた小舟の寝台”で目を覚ます。恐れていた”早まった埋葬”は、ただの幻覚と錯誤であった。
この経験により、彼は自らを蝕んでいた偏執から解き放たれる。
■ キリスト教と“土葬”の恐怖
火葬が主流である日本と違い、西洋のキリスト教文化圏では「土葬」が一般的だった。
死者は肉体を持って復活する──終末の日に神が全人類を裁くという「最後の審判」の思想が、死体を完全なまま埋葬するという文化を支えていた。
だがそれゆえに起こるのが、“埋めてから蘇生する”という恐怖。現代のような医学的判定が未熟だった時代、「仮死」を見抜くことは非常に難しかった。
■ まとめ|沈黙のうちに微睡ませておけ
この短編の終盤、ポーは次のような詩的な文で締めくくっている。
「それらの恐怖は、ペルシャの英雄アフラシアブが、オクラクサス河を流れ下る時に同行していた悪鬼たちと同じように、微睡ませておかねばならぬ。さもなければ、我々の破滅なのだ。」
つまり、この世には”目を覚まさせてはならない恐怖”が存在する。 それを眠らせておくためには、用心と祈り、そして幻想文学が必要なのかもしれない。

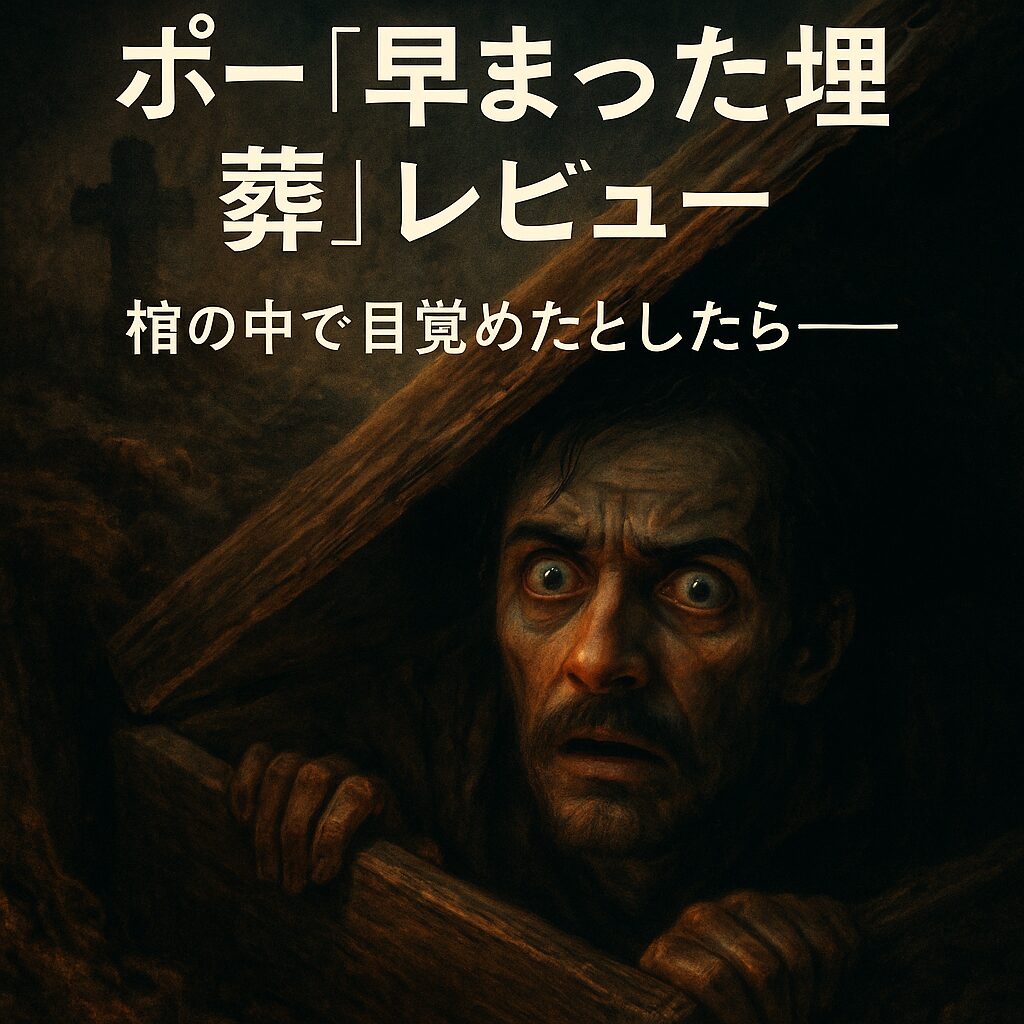


コメント