水の人工生成不可能性に関する一考察
―液体的存在の養殖不適性と現代技術の限界について―
要旨
本稿は、水(H₂O)という化学的に単純でありながら、極めて生産困難な物質についての工業的再現可能性を検討するものである。特に、「水の養殖は可能か」「水の工場生産は現実的か」という素朴ながら深淵な疑問に対し、諸技術的・資源的制約から導かれる否定的見解を提示する。なお、筆者は本件に関し、完全なる水道依存体制下にある。
1. はじめに
水は、生命維持に不可欠であると同時に、蛇口から出てくることによってその神秘性を著しく損なわれた存在である。本稿では、「そもそもこの水、我々は“作れる”のか?」という問いに対し、冷静かつ軽率に答えることを目的とする。
2. 養殖可能性の否定
まず、生物養殖の概念に照らして考察する。鮎や牡蠣などは繁殖・育成・収穫という工程を経ることで増産が可能である。だが、水は生物ではない。繁殖しないし、卵も産まないし、タマゴッチでもない。
結論として、水の養殖は言語的には可愛げがあるが、物理的には無理ゲーである。よって、液体を液体で養殖する試みは、哲学的な詩作としては評価できるが、産業的には全滅である。
3. 化学的生成の現実
水の分子式はH₂O。つまり水素と酸素を合体させれば生成可能である。
では、やればいいのでは?と問われるが、問題はその過程にある。
3.1 爆発的反応
水素と酸素の反応は爆発を伴う。これは化学の教科書にも載っているが、実際にやると家がなくなる。よって家庭内生成には不向きである。
3.2 水素の確保問題
水素ガスを生成・保存・運搬するには膨大なエネルギーが必要であり、「水を作るために原子力を使う」という逆転構造が発生する。結果として**“水作りのための水不足”というメタ構造**が誕生する。意味不明である。
4. 海水淡水化という現実逃避
一部の国家では、海水を飲用可能な真水に変換するプラントが存在する。
たとえばイスラエル、サウジアラビア、シンガポールなどはこれに積極的である。
しかし、これらは**「水不足を資本主義で殴ったら勝った(ただし予算が爆死)」**という事例であり、全世界が模倣できるとは限らない。
また、処理後に残る大量の塩についての対処が難しく、「水はできたが、海が怒っている」状態が生まれる。
5. 蛇口に潜む幻想
我々が水を「蛇口から出る当たり前の液体」として認識していること自体が、極めて高度な幻想に基づく文明錯覚である。
実際には、
-
雨(空の機嫌)
-
浄水場(人間の清潔妄想)
-
配管(都市の血管)
の3段階を経て、ようやく「ピュッ」と出ているに過ぎない。
そしてこのシステム、雨が降らなければただの銅管ショーである。カラの蛇口ほど空虚なものはない。
6. 結論
水は作れない。増やせない。育てられない。
よって、我々は今後も雲の気分とダムの残量に全力で依存して生きることとなる。
文明とは、結局のところ「蛇口が今日も笑ってくれていること」を当然だと思い込む集団催眠である。
水に感謝。蛇口には、期待しすぎるな。
参考文献(存在しない)
・『水道哲学入門』誰も書いてない
・『蛇口と人間』全3巻、未完
・『空が泣く日、我々は生き延びる』という妄想タイトルのポエム


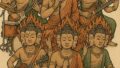

コメント