若くして逝った詩人
中原中也──日本近代詩に燦然と輝く、素朴な彗星。1907年、現・山口県湯田温泉に生まれ、30歳の若さで夭折した(1937年・昭和12年)。
「夭折」という言葉を私は中也の年表で初めて知った気がする。私が彼に出会ったのは高校の国語の教科書に載っていた「月夜の浜辺」だった。
早弁と中也
思春期の放課後、あるいは授業中。教師の話をよそに、私は「羅生門」や中也の詩を勝手に読んでいた。ときには早弁──昭和の一部で密かに流行した、授業中に弁当を広げてしまう反骨の遊び──をしながら。
中原の詩は、簡潔な言葉で、ごく身近な風景から深い情緒を汲み取る。それは、若き私の心にも静かに染み込んできた。「月夜の浜辺」はその代表格だった。
「月夜の浜辺」ウォークスルー
舞台は、澄んだ月明かりに照らされた夜の海辺。波打ち際には月光が反射し、静かな波音と“サクッサクッ”という足音だけが響く。死の気配も宗教的敬虔さもない、ただ孤独な散策者の世界。
そんな夜、詩人の足元に、不意に「ボタン」が一つ落ちているのを見つける。
そのボタンは、ありふれたプラスチック製か、あるいは割れやすい貝ボタンだったかもしれない。少し上等なシャツに使われる貝ボタンは、海から生まれ、また海へと還るかのように。
ボタンの素材の違いとともに思い起こされるのは──中也の繊細さもまた、貝のように脆く、傷つきやすかったのではないかということだ。
想像と接触
波に洗われ、ぽつりと落ちていた小さなボタン。それは見知らぬ誰かの袖からこぼれたもので、詩人にとっては偶然の出会いであり、密かな共鳴のきっかけだった。
中原中也の感受性は、ごく些細なものにも強く反応する。そのボタンには、誰かのぬくもりや記憶、失われた時間の気配が宿っていたのだろう。
そしてなにより、ボタンとは、人がもっとも繊細に指先で扱うものの一つ。毎日身につけ、留め、外す──その所作が、他者との距離感を思わせる。
中也は、知らぬ誰かと一瞬、時空を越えて触れ合ったように感じたのではないか。想像力の豊かさと、詩人の孤独がそうさせたのだ。


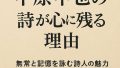

コメント