『サド侯爵夫人』の発表背景とテーマ
三島由紀夫の戯曲『サド侯爵夫人』(1965年初演)は、18世紀フランスのマルキ・ド・サド夫妻を題材とした作品です。三島は澁澤龍彦著『サド侯爵の生涯』を読んで着想を得ており、囚人生活を送る侯爵サドと献身的な妻ルネの関係にひかれましたja.wikipedia.org1000ya.isis.ne.jp。とりわけ、20年もの間一途に夫の無罪を信じ尽くしたルネが、老境にさしかかったサドの釈放を機に突然別れを告げる謎に強く心を動かされ、この「謎」を解明するために戯曲を書いたと三島自身は語っていますja.wikipedia.org。戯曲では、「無垢と怪物性、残酷と優しさ」という相矛盾する両義性をもつサド侯爵像を、6人の女性たちの議論劇を通じて浮かび上がらせる構成となっていますja.wikipedia.orgacademia.edu。特にサディズム(加虐性)とマゾヒズム(被虐性)、そして隠されたエロティシズムがテーマの核であり、権力・社会秩序に抗う個人の歪んだ情念を描き出す「残酷劇」(シアター・オブ・クルエルティ)として仕立てられていますacademia.edu。
構成・時代設定
舞台はパリ近郊モントルイユ夫人邸の豪華なサロンですja.wikipedia.org。全3幕構成で、第1幕は1772年秋、第2幕は1778年9月、第3幕は1790年4月(フランス革命勃発後9か月)と、時間が経過しながら物語が展開しますja.wikipedia.org。この時代背景を通じて、サド一家を取り巻く貴族社会の変遷と、ルネ夫人の信仰心・純潔観の揺らぎが描かれます。
登場人物と象徴性
登場人物は女性6人のみで、主人公サド侯爵(アルフォンス)は一度も舞台に姿を現しませんja.wikipedia.orgblog.goo.ne.jp。各女性は侯爵や時代精神の一面を体現する象徴的存在として描かれます:
-
ルネ(サド侯爵夫人):侯爵の妻。若い頃から「貞淑」を貫き、夫に尽くしてきた理想的な貞女。高潔な信仰心と理性を象徴するが、その裏で侯爵との複雑な結びつきがひそむ。
-
モントルイユ夫人:ルネの母。厳格で威厳ある貴族婦人。法・社会・道徳といった既存秩序を体現し、娘の忠節さを支配しようとする。実際には侯爵家を守るために権謀術数も辞さない。
-
シミアーヌ男爵夫人:敬虔なクリスチャン。常に「神」の視点から物事を語り、修道院の生活を理想視する。キリスト教的な純粋さと献身を代表し、ルネにも宗教的生き方を勧める。
-
サン・フォン伯爵夫人:奔放で好色な貴婦人。肉欲を体現し、庶民的な下品さすらはらんだ自由奔放さを見せつける。すべての情欲に背徳的に溺れるサド侯爵の欲望の鏡とも言える存在。
-
アンヌ:ルネの妹。年若く無邪気であり、情欲に素直に溺れる典型。無邪気・無節操そのもので、時代のモラルを超えて自在に生き、侯爵に肉体的に魅かれている。
-
シャルロット:モントルイユ邸の家政婦。貧しい出自ながら、庶民の現実的な目線を代表する。民衆の象徴として、他の貴婦人たちとは異なる率直さで侯爵の物語に介入する。
これら6人の女性の立場が、惑星の運行のように交錯・回転しながら、サド侯爵をめぐる一つの精密な数学的体系を成していくと言われていますja.wikipedia.org。登場人物間の対立と対話は、あらゆる道徳規範と人間性を総括した論理的な討論となっており、三島はこれを通じて侯爵とルネ夫妻の「愛と憎悪、忠誠と反逆」といった背後のテーマを浮き彫りにします。
サド侯爵の不在と演劇的効果
本作の大きな特徴は、主人公サド侯爵自身が舞台に一度も登場しないことですja.wikipedia.org。代わりに、6人の女性たちがそれぞれ自分なりのサド像を語り合うことで、観客の想像上に侯爵が浮かび上がりますblog.goo.ne.jp。この手法により、サド本人の行動や思想ではなく、周囲の女性たちが語る「評判」と「幻想」を通じて侯爵像が構築され、神話的な存在感が増します。女性たちは互いに激しい口論を繰り広げることで、侯爵に刻印された「悪徳」や当時の社会への批判を表し、またルネ夫人の究極の決断をよりドラマチックに際立たせています。
あらすじ
第1幕(1772年秋)
モントルイユ夫人邸のサロン。サド侯爵夫人ルネの母・モントルイユ夫人は、獄中の義理の息子アルフォンス(侯爵)の無罪を勝ち取るべく、敬虔なシミアーヌ男爵夫人と奔放なサン・フォン伯爵夫人を招き、裏工作を依頼しようとするja.wikipedia.org。当時侯爵はマルセイユで娼婦を虐待した事件で追われる身だった。そこへルネが帰宅し、モントルイユ夫人は離婚を勧めるが、ルネは忠節を貫き寝室へ去る。さらにルネの妹アンヌがイタリア旅行から戻り、侯爵と一緒だったこと、そして姉ルネもそれを知っていると告白する。怒りに震えたモントルイユ夫人は計画を取りやめ、アンヌに手紙を託し侯爵逮捕を王に嘆願させる。こうして侯爵は再び捕縛されてしまうja.wikipedia.org。
第2幕(1778年9月)
6年後、パリの同じサロン。アンヌから、侯爵の裁判で罰金刑となり事実上解放されるという知らせを聞いたルネは喜ぶ。実は5年前に自ら脱獄を助けて無罪を勝ち取ろうと奔走したが、モントルイユ夫人の策略で再逮捕されていたのだ。しかし祝杯も束の間、侯爵は再審で釈放直後に王宮の警官に捕らえられ、より厳重な牢に入れられてしまったという報が入る。その手口はすべてモントルイユ夫人の申請によるものだったと、サン・フォン伯爵夫人から聞かされるja.wikipedia.org。失望したルネは母を激しく詰問し、「どうして夫を自由にしてほしいのか」と問われる。「貞淑を教わったからだ」と答えるルネ。しかし、母は侯爵が脱獄していた間、ルネが侯爵の“生贄”となり汚らわしい行為に溺れていたと密偵から聞いていたことを明かすja.wikipedia.org。驚愕したルネは「あなた方親(父と母)は、偽善としきたりの愛で道徳を庇い、一切を蔑んでいた」と反論し、「(君主よ)アルフォンスは私だったのです」と告白する。これにより、ルネは母と対峙し、侯爵への忠誠と母の偽善との衝突が頂点に達する。
第3幕(1790年4月)
さらに12年後、フランス革命勃発後のパリ。貴族たちは逃亡の準備で騒然とする中、モントルイユ夫人は、「牢にいる侯爵こそ身内の免罪符」と考え、まだ生き延びている王の裁判決定が無効となれば侯爵は釈放されると見込む。一方、ルネは衝撃的な決意を告げる。夫の書いた小説『ジュスティーヌ』を読み、かつて「アルフォンスは私」だと言った自分は誤解だったことを悟る。「ジュスティーヌは私です」と宣言し、この世を悪徳に染める侯爵から離れ、修道院に入ると母に告げるのだja.wikipedia.org。ルネは侯爵を「悪徳の結晶を築く存在」と理解し、「神がおそらくその仕事を侯爵に委ねたのかもしれない」とさえ言う。そして残りの生涯を神に仕えると決意する。最後に、体を風変わりに損ねた老侯爵が訪ねて来ても、ルネは会わないようシャルロットに伝言を託し、「侯爵夫人はもう決してお目にかかることはありますまい」と告げさせるja.wikipedia.org。妻ルネのこの態度が、“最愛”の侯爵にとっても永遠に理解しがたい終焉の謎として残される。
翻訳・海外上演と評価
『サド侯爵夫人』は日本初演当時から高い評価を受け、三島自身の代表戯曲の一つとされています。発表当時、江藤淳や山本健吉ら評論家は、三島の文章表現の完成度や会話劇の妙を絶賛し、戦後演劇史上の傑作と評しましたja.wikipedia.orgja.wikipedia.org。国内外で上演され続け、とりわけフランスでの人気が高い作品ですja.wikipedia.org。三島の親友である米文学者ドナルド・キーンは英訳(『Madame de Sade』)を手がけ、世界に紹介しましたblog.goo.ne.jp。またアンドレ・ピエール・ド・マンディアルグによる仏訳を通じてフランスでも上演され、圧倒的な好評を博していますblog.goo.ne.jpja.wikipedia.org。ほかにもアラビア語、スウェーデン語、イタリア語、ドイツ語など多言語に翻訳され、国際的に演劇の名作として定着していますja.wikipedia.org。
三島作品との思想的共通性
『サド侯爵夫人』は三島文学に共通するテーマ──愛と死、情熱と破滅──を色濃く含む作品です。例えば、夫婦の忠誠と自殺を描く『憂国』(1966年)は極限の純潔と死を礼賛し、同様に『愛の渇き』(1950年)や『獣の戯れ』(1961年)では異常な愛欲と自己破壊が交錯します。『愛の渇き』では、家族的抑圧と禁断の情欲が激しい嫉妬と死へとつながり、『獣の戯れ』では男女三角関係が殺人へと発展します。いずれも『サド侯爵夫人』のように、倒錯したエロティシズムや暴力が究極の結末=死へとつながる構造をもち、現実を超えた“理想”や“秩序”の名の下で個人が破滅する様相を描いています。これら作品群に通底するのは、「生の歓喜」を死に至るまで追い求める欲望と、既存の道徳・権威への反逆という主題であり、『サド侯爵夫人』もまたそれらを象徴的に体現した戯曲と言えます。
参考資料: 上記内容は、三島由紀夫自身の跋文ja.wikipedia.orgや、翻訳・上演情報をまとめた資料ja.wikipedia.orgblog.goo.ne.jpなどに基づきました。作品の概観にはウィキペディアなどの解説ja.wikipedia.orgja.wikipedia.orgja.wikipedia.orgも参考にしています。
関連リンク集
【三島由紀夫レビューまとめ】代表作・思想・関連文献を網羅した総覧


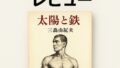

コメント