「ほっかほっか亭」と「ほっともっと」は違うのか?──“ほか弁”にまつわる記憶と分裂の真相
「ほか弁」と言えば、どっちだ?
「ほか弁」と聞いて、あなたはどのお弁当屋さんを思い浮かべるだろうか?
昭和世代なら「ほっかほっか亭」かもしれない。でも最近では「ほっともっと」の弁当をそう呼ぶ人も多い。
実はこの2つ、もともとは同じルーツを持つが、今ではまったく別の会社。にもかかわらず、外観や名前が紛らわしいせいで、多くの人が混同しているのが実情だ。
ふたつの「ほか弁」の分岐点
「ほっかほっか亭」は1976年に登場し、持ち帰り弁当チェーンの草分け的存在となった。
全国にフランチャイズ展開していく中で、中核を担っていたのが株式会社プレナスという企業である。
しかし2008年、プレナスは運営方針をめぐって本部と対立。
ついに独立して自社ブランド、**「Hotto Motto(ほっともっと)」**を立ち上げた。
結果として:
-
ほっかほっか亭:本部は「ハークスレイ」社が運営。現在も一部地域で営業中。
-
ほっともっと:プレナスが展開する新ブランド。従来の店舗をそのまま引き継いだ地域も多く、全国規模で急成長。
つまり、商品も運営会社もまったく別物なのに、どちらも“ほか弁”っぽい顔をしている。そりゃ、間違えるのも無理はない。
地元の「ほか弁」おじちゃんの記憶
僕が中学二年生の頃、地元に「ほっかほっか亭」がオープンした。
当時はまだコンビニもなく、セブンイレブンの1号店さえ近所にはない時代。
新聞に折り込まれた開店チラシを見て、近所の住民はこぞって足を運んだものだった。
人気メニューといえば、「のり弁当」「鮭弁当」「からあげ弁当」「ハンバーグ弁当」「幕の内弁当」くらい。
ラインナップは今よりずっとシンプルだったが、それがかえって良かった。
部活帰りの空腹や、日曜の遠足の朝。
そんなときによく買いに行ったのを覚えている。
弁当を作っていたのは、寡黙で働き者のおじちゃん。あの人がカウンター越しに差し出すアツアツの「のり弁」は、僕にとってちょっとしたごちそうだった。
やがて月日は流れ、僕は東京へ出て、また地元に戻ってきた。
別に驚きはしなかったが、おじちゃんがまだ店に立っていた。店舗は以前よりやや広くなり、立地も変わっていた。
しかも看板は「ほっともっと」に変わっていたけれど、彼の作る弁当は相変わらず美味しかった。
でも、ある日ふと気づくと、その姿は消えていた。
店はそのまま営業していたけれど、あのおじちゃんはいなかった。
時代とともに変わる「弁当屋」
おそらく、経営者が変わったのだろう。
もしかすると、スマホ決済やネット注文が当たり前になったこの時代に、昭和の手仕事が“時代遅れ”と見なされたのかもしれない。
あるいは、おじちゃん自身が静かに弁当業界から身を引いたのかもしれない。
理由はわからない。
でも、あの人が作ってくれた弁当と、その湯気の記憶だけは、今も忘れられない。
おわりに:「のり弁」と人生の湯気
「ほっかほっか亭」と「ほっともっと」、確かに今では違う弁当屋だ。
でも、僕にとってはどちらも“あの弁当屋”であり、“あのおじちゃん”のいる場所だった。
看板が変わっても、記憶の味は変わらない。

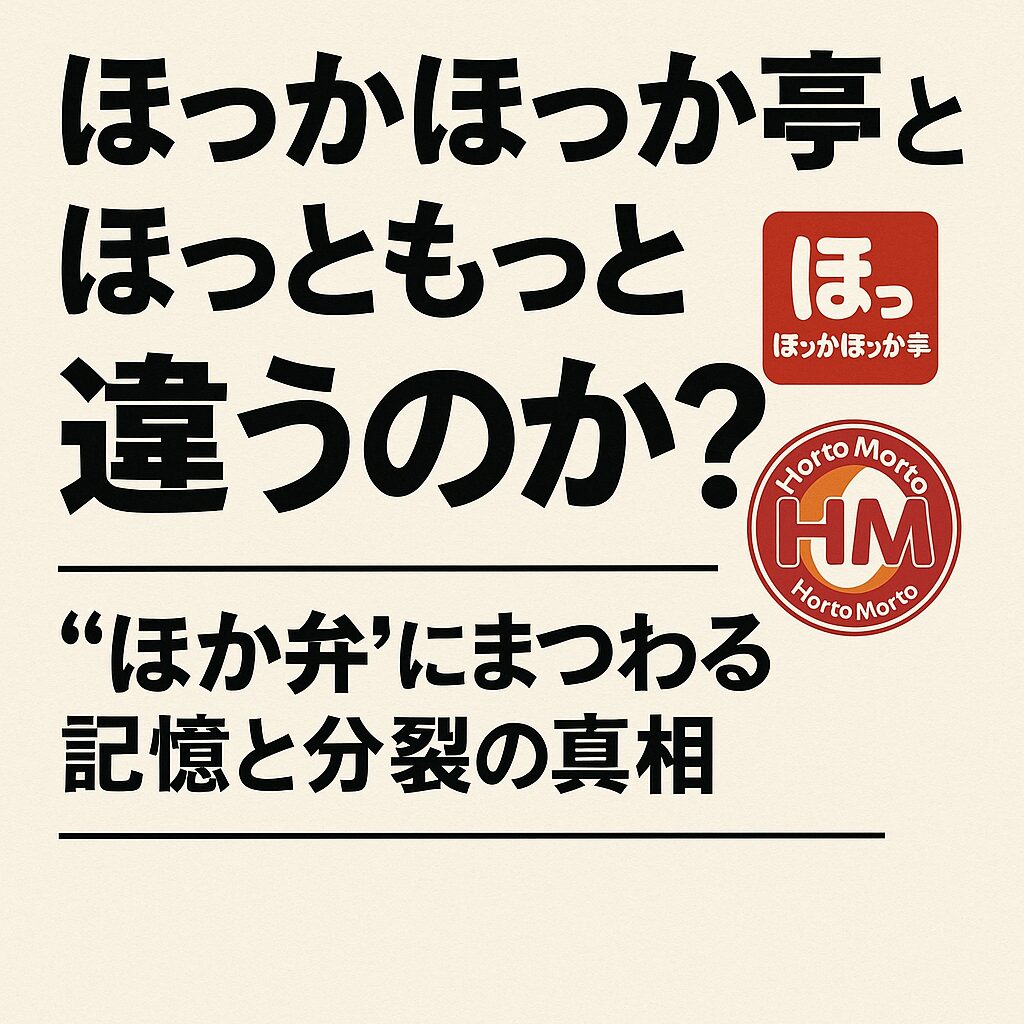


コメント