【正法眼蔵を読む】曹洞宗高祖道元禅師の遺言たる宗門の至宝
一、緒言
『正法眼蔵』なる書名は、仏教に親しまぬ者とて一度は耳にしたるものなり。されど、その実に手を取る者は稀なり。何故ならば、岩波文庫版にして全四巻、各々四百五十頁を超え、古語と漢語と禅語とが混淆し、注釈に注釈を重ねし煩瑣の極み、常人の耐ふべきところにあらず。
しかれども此の書こそ、我が国曹洞宗の高祖、承陽大師道元禅師が、宋国にて体得した仏祖の意趣を以て、帰朝後記し伝えたる唯一無二の大著なれば、その深奥を覗かんと欲する者にとりては、避けて通るべからず。
二、内容の大意
内容は一言にして曰く、「禅語録の註解」と見るべし。殊に中国の語録『碧巌録』を読破せし者には、道元の筆致がいかにこれに依るか明白なり。とは言え、ただの焼き直しにあらず、彼自身の霊感と体験を以て、仏祖の道を再解釈せんとする試みなり。
そは、かの聖徳太子が『法華義疏』を著して南無妙法蓮華経の心を我が国に示したるに類す。『普勧坐禅儀』『随聞記』などの諸書と併せ読むべし。曹洞宗の教義、儀礼、心法は、この一書に凝縮され、余の典籍を要せずとも事足りる。
三、翻訳と異文化の隔たり
然れども、道元の文体は漢文なり。その元はと尋ぬれば、インドの梵語を中国語に翻訳せし経典なり。漢訳仏典は儒家・道家の語彙を援用し、中国思想の影響を色濃く帯びたり。
よって日本にて読むとき、既に三重の翻訳の末の言葉なり。梵語→漢語→和語。陀羅尼などの真言はその音のみを残し、意味は遥か彼方に消え失せたり。
四、宝鏡三昧と道家の影
しかも、曹洞宗の根本典籍たる『宝鏡三昧』および『参同契』なるもの、いづれも中国人の著作にして、禅よりもむしろ道教・老荘思想の薫り濃厚なり。『易経』の語法、『道徳経』の文脈が散見されるも、道元はこれらを排し仏教のみを称する。
然れど彼が排す儒道の用語をして仏法の語とし、己の著述に用いたるは、あるいは無自覚のままに中国思想に依拠したる証左なり。これをして「仏教は名を借りた道教なり」と嘯くも、あながち過言にあらず。
五、結語──柏樹子の前に立ちて
我らが日々、通夜や葬儀の席にて耳にする念仏、読誦される経文、「南無阿弥陀仏」「摩訶般若波羅蜜多心経」の一語一句に至るまで、その奥に幾千年の翻訳と思想の重なりあり。
身近なる寺院、墓地、香の煙の向こうに、道元の『正法眼蔵』は今なお静かに在り。禅に曰く、「庭前の柏樹子」。この柏樹を見るためにこそ、かの達磨大師は西より来たりしという。
『正法眼蔵』は読むに難し。されど、それを読む心は、ただ坐して在ることに通ず。道元の詞に触れ、ただ一章でも読み終えたる時、己れのうちに微かなる柏樹の影を見出さん。

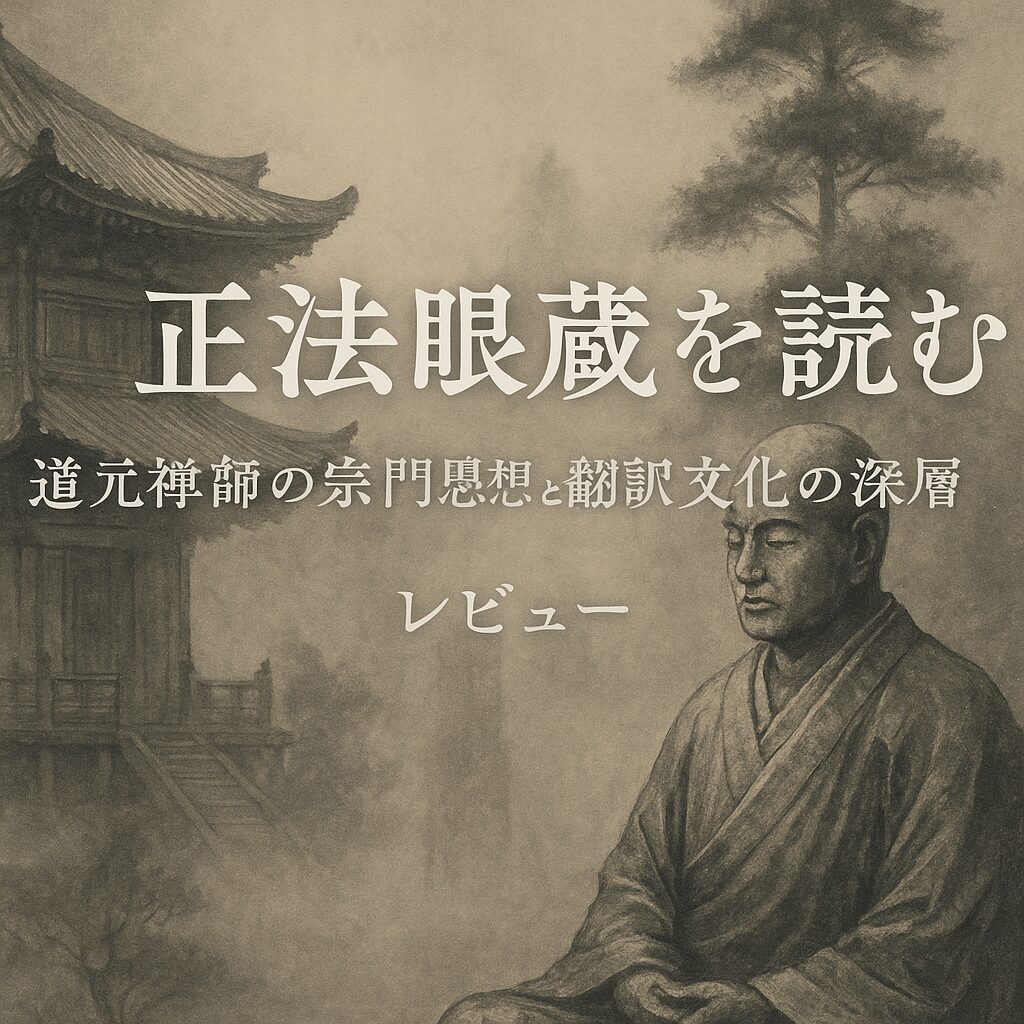

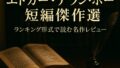
コメント