食卓に走る影――19世紀パリ、ネズミはごちそうだったのか?
序章:極限状況のフランス人と「非常食」
「パンがなければケーキを食べればいいじゃない?」――18世紀末、飢えに苦しむ民衆にマリー・アントワネットが放ったとされるこの言葉(実際には伝聞ですが)、フランス人の食にまつわる極限状況を象徴する逸話です。19世紀のパリもまた、革命と芸術の陰で深刻な食糧難に見舞われ、人々は通常なら口にしないものまで食卓に載せざるを得ない場面がありました。その代表例が「ネズミ」です。果たしてパリジャンたちは本当にネズミを食べていたのでしょうか?結論から言えば、**「はい、ただし本当に追い詰められた時には」**です。以下では、19世紀パリの歴史的背景や食文化的・地理的要因を踏まえ、この意外な事実をアカデミックに紐解いてみます。
歴史的背景:19世紀パリの食糧危機と政治的要因
19世紀のパリがネズミを食べるという極端な状況に至った背景には、飢餓と戦争、政治的混乱がありました。特に有名なのが普仏戦争中の「パリ包囲戦」(1870~1871年)ですatlasobscura.comobonparis.com。1870年9月、プロイセン軍に完全包囲されたパリでは、約4か月にわたり外部からの食料供給が遮断されましたatlasobscura.com。市内に蓄えていた家畜や穀物はすぐに底を突き、パリ市民は生き延びるために通常では考えられないものまで食べねばならなくなりますobonparis.com。まず馬肉や下水道で捕れた魚に手を伸ばし、それも尽きると犬や猫、ハトに至り、ついにはネズミにまで及びましたobonparis.com。事実、当時のアメリカ人目撃者ロバート・シベットは11月の市場の様子をこう記録しています。犬肉・猫肉と並んで「一山のネズミがトレイに並べられ」、貧しい婦人がその値段を尋ねていたのですatlasobscura.comatlasobscura.com。ネズミはもはや非常時のタンパク源として市民に受け入れられていました。実際、この包囲戦の間、ネズミは飢えた市民にとって貴重な食料の一つとなったと伝えられていますpolitico.eu。
もっと遡れば、フランス史には度重なる飢饉と暴動があります。18世紀末のフランス革命直前には小麦の不作でパンの価格が高騰し、都市部で飢餓が深刻化しました。このような食糧不足は政情不安の火種となり、革命や暴動へと繋がっていきます。19世紀パリでも人口増加による需要拡大と度重なる戦争で、一時的に供給が途絶する危機が幾度か訪れました。中でも前述の1870年の包囲戦は決定的で、当時の政府(第二帝政末期から第三共和政への過渡期)は充分な備蓄をしたものの、予想以上に包囲が長期化し約200万人の都市人口を養う食料は圧倒的に不足しましたalysasalzberg.medium.comalysasalzberg.medium.com。これは一つの政治的判断ミスとも言え、結果的に市民は生存のためタブーを破る選択を迫られたのです。
非常食としてのネズミ料理:都市伝説と史実
ネズミ食というと都市伝説のように聞こえるかもしれません。しかし19世紀パリの非常時には現実に存在した食文化でした。その証拠に、1870年の包囲戦下で出版された料理小冊子『包囲下の料理人(La Cuisinière assiégée)』には、馬、犬、猫、そしてネズミの肉を使った料理のレシピが含まれていますalysasalzberg.medium.com。この中でネズミ肉については「調理法に工夫が必要(十分な加熱が必要)」と注意書きがあり、寄生虫症(旋毛虫症、トリヒナ症)の危険に言及されていますalysasalzberg.medium.com。つまり、ネズミを食べるには下処理が大変で、衛生面のリスクも高かったのです。それでもなお人々はネズミを食べざるを得なかった――この事実自体が当時の飢餓の深刻さを物語っています。
包囲戦下のパリでは、ネズミ料理が実際にテーブルに上ったことを示す具体的な記録も残っています。当時営業を続けていた高級レストラン「ヴォワザン」では、1870年クリスマスの特別メニューとして**「ローストキャット(猫の丸焼き)」がネズミを添えて提供されましたatlasobscura.com。他にも「ラット・サレミ(ネズミのロベールソース煮込み)」「犬の腿肉のネズミ添え」といった料理名がメニューに並び、カンガルーシチューや象のコンソメスープなどと共に供されていたのですen.wikipedia.orgen.wikipedia.org。こうした逸話は都市伝説ではなく史実であり、実際に残されたメニュー表や日記、新聞記事**によって裏付けられています。
当然ながら、平時のフランス料理にネズミが登場することはありません。当時でもネズミ食はあくまで非常時の代用食扱いでした。しかし人々は驚くべき工夫でそれを「料理」に仕立てています。ある記録では「犬はマトン(羊肉)の代わりとして悪くない」「猫はウサギ肉の味わいだ」などと評され、挙句の果てに**「豊かな人々はラットのパテで宴を催した」とも伝えられますatlasobscura.com。実際、市場価格でもネズミ肉は猫や犬より高価で、太ったネズミ1匹が50スウ(約0.5フラン)もしたと報告されていますatlasobscura.com(※猫・犬肉は1ポンド20~40スウ)。高値にもかかわらず売れていたのは、それだけ追い詰められた状況下でネズミが貴重なタンパク源と認識されていた**ということでしょう。
もっとも、ネズミは衛生的な不安も伴うため誰もが積極的に食べたわけではありません。当時の報道によれば、実際に消費されたネズミの数はそれほど多くなく、人々は伝染病の恐れや調理の手間から敬遠しがちだったともいわれますen.wikipedia.org。そのため、猫や犬、馬など他の代替肉が先になくなり、それでも飢えが極限に達した段階でようやくネズミに手を出した人が多かったようです。料理人たちの中には「おいしいネズミと臭いネズミは見れば(匂いを嗅げば)わかる」などと豪語する者もいたそうですが、これは生ごみ漁りのネズミより穀物倉庫にいたネズミの方がマシといった経験則だったのかもしれません。いずれにせよ、ネズミを調理してでも生き延びようとしたパリ市民の姿は、当時の風刺画や文学にも描かれ、後世まで語り草となりましたobonparis.com。
追い詰められた人々:グルメではなくサバイバル
パリ市民がネズミを口にした理由は、決して「物好きな珍味探し」や変態グルメ嗜好からではありません。その背景にあったのは純粋な生存本能であり、極限まで追い詰められた状況でした。具体的な要因を整理すると以下の通りです:
-
飢饉・食料不足:度重なる不作や物流の混乱で、一般市民はしばしば食糧難に陥りました。特に貧困層ではパンすら手に入らない日もあり、空腹を紛らすために目の前を走るネズミに手を伸ばすこともあったと推測されます(ネズミは文字通り「無料で走り回るタンパク源」でした)。
-
戦争・都市封鎖:1870年のパリ包囲戦のように、戦争による都市封鎖は突然都市から食料を消し去りましたatlasobscura.com。外部との連絡を断たれた大都市で人々が飢えれば、どんな生き物でも食べざるを得なくなります。ネズミ食はこの極端な状況の産物でしたpolitico.eu。
-
政治的混乱と政策不足:第二帝政の崩壊と普仏戦争敗北という政治的大事件の中で、行政は市民の食を十分守れませんでした。物価高騰や配給制限が追いつかず、市場経済にアクセスできない最貧層から順に非正規の食糧調達に走ったのです。政府の支援が届かない中で、下層市民は下水道や路地裏で捕まえられるネズミに頼らざるを得なかったとも考えられます。
このように、ネズミ食の背景は狂気や嗜好ではなく切迫した事情でした。それだけに、史料に残る当時の声には悲壮感とブラックユーモアが混じっています。包囲戦終結後に出回った風刺詩には「空腹にならなければ何が美味いかなんて分からないものだ。我らがこれらの肉を食べていたのは、生きるためであって、食べるために生きていたわけではない」との一節があったと伝えられますatlasobscura.com。極限状態で人々が示した**「生きるための創意工夫」**こそ、ネズミ料理という奇妙な事実の核心なのです。
現代のパリでネズミは食べられるのか?
では現代のパリではどうでしょうか。結論から言えば、公式にはネズミを食用とすることはありません。フランスの食品衛生上、野生のネズミを捕獲して食べることは明確に違法かつ危険です。ネズミは多くの人獣共通感染症の媒介動物であり、その体には病原菌や寄生虫が潜んでいます。例えば、ネズミの肉には旋毛虫(トリヒナ)などの寄生虫が含まれる場合があり、不十分な加熱調理で食べれば重篤な寄生虫症を引き起こす恐れがありますalysasalzberg.medium.com。また、ネズミの排泄物やノミ・ダニを介してペストやレプトスピラ症といった疾病が伝播するリスクもありますlemonde.fr。こうした衛生上の理由から、現在のパリでネズミを食品として扱うことは認められていませんし、現実にも一般的ではありません。
もっとも、「誰も絶対に食べていない」と断言はできません。世界を見渡せば、ネズミを食材とする食文化はいくつも存在します。たとえば東南アジアのベトナムやカンボジアでは、大型のイネネズミ(ライスフィールド・ラット)を捕獲して専門店で調理する習慣があります。カンボジアでは収穫期になると野生のネズミをベトナム向けに1日2トン近く輸出するほど需要がありpmc.ncbi.nlm.nih.gov、ベトナム農村では焼きネズミやネズミの串焼きが名物料理として供される地域もあります。またインド北東部のある部族は毎年3月7日に「ネズミ狩り祭り」を行い、最もたくさんのネズミを獲った者が誇られる伝統さえありますpmc.ncbi.nlm.nih.gov。フィリピンではネズミ肉の缶詰が「STAR肉」(RATSを逆綴りにした商品名)として売られていたり、中国南部やアフリカ・ガーナでも伝統的にネズミ料理が存在したりしますpmc.ncbi.nlm.nih.govpmc.ncbi.nlm.nih.gov。これらは主にドブネズミより一回り小さい野ネズミや草原ネズミで、農地周辺で穀物を食べて肥育した個体が使われます。適切に下処理・加熱調理すれば風味もよく、高級食材として珍重されることもあるのです。
このように世界にはネズミ食文化が点在しますが、パリでは衛生面と文化的嫌悪感から公には行われていません。もっとも、歴史を知る者からすれば「19世紀のパリでネズミを食べていた」と聞いても驚かないでしょう。極限状況下での伝統は細々と語り継がれ、現代でもごく一部の好事家や移民コミュニティでひっそり再現されている可能性は否定できません。しかし少なくともレストランのメニューに**「ratatouille(ラタトゥイユ)」という名前でネズミ料理が出てくることはない**ので、ご安心ください(※ラタトゥイユは南仏発祥の野菜煮込みで、名前にrat〈ネズミ〉とありますがネズミ肉は入っていません…残念ながら?)。
パリは今も「ネズミの都」なのか?
ネズミを食べる文化は廃れたとはいえ、パリとネズミの関係自体は現在も切っても切れません。むしろ現代のパリは、19世紀以上にネズミが繁栄する都市になっています。その数は推定で少なくとも300万~600万匹とも言われpolitico.eu、一部の推計では900万匹以上(人間の人口の3~4倍!)に達するとも報じられました。実際の正確な数は数えようがありませんが、専門家によれば「パリ市民1人あたり1~1.75匹のネズミが地下に生息している」とされ、少なくとも人間の数を上回ることは確実ですpolitico.euquod.lib.umich.edu。パリの地下鉄トンネル、下水道網、セーヌ河岸の石垣、観光地のゴミ箱の陰――あらゆる場所がネズミにとっての楽園と化しています。パリ市当局も度々大規模な駆除作戦を展開していますが、近年のネズミは殺鼠剤(ラットポイズン)への耐性を獲得しており、一筋縄ではいきませんpmc.ncbi.nlm.nih.govpmc.ncbi.nlm.nih.gov。実験では、市販の抗凝血剤系毒餌に対しパリのドブネズミの一部が遺伝的耐性を示すことが確認されており、**「スーパーラット」**の台頭が懸念されています。
ネズミが増え続ける理由は、都市生活の副産物とも言えます。大量の生ごみや排水が絶好の餌場を提供し、温暖化による平均気温上昇で通年繁殖が可能になったことも指摘されていますpolitico.eupolitico.eu。さらにパリは古い下水道や地下空間が縦横に広がり、ネズミが人目を避けて巣を作るには理想的な構造です。主役である**ドブネズミ(Rattus norvegicus)は18~19世紀にアジアからヨーロッパ各地へ侵入し、先住のクマネズミ(Rattus rattus)**を駆逐して都市部を支配するようになった種ですquod.lib.umich.edu。フランス語ではドブネズミを「スュルムロ」(下水ネズミ)とも呼び、その名の通り下水や地表で活動します。体長は頭胴長で20~25cm、尾を入れると30~40cmにも達し、体重も200~400gとネズミ類では大型ですseikatsu110.jp。泳ぎが得意で高い知能を持ち、雑食性ゆえに人間の捨てるあらゆるものを食べて繁殖します。一方、クマネズミ(フランス語では「屋根裏ネズミ」)はもう少し小柄で細身、高所を好むため郊外や屋根裏部屋に生息しますが、パリ市内ではドブネズミに生息域を奪われ数を減らしていますquod.lib.umich.edu。こうしたネズミたちのしたたかな生態を理解するため、近年では研究者がパリのネズミにマイクロチップを埋め込み行動追跡を行う試みまで登場しています。もはやピクサー映画『レミーのおいしいレストラン(Ratatouille)』は単なるフィクションではなく、パリの現実を映すドキュメンタリーなのかもしれません。
おわりに:歴史が語る人間とネズミの関係
「19世紀のパリジャンがネズミを食べていたって本当?」――この問いに対する答えは、本稿で見てきた通り**「はい、本当です。ただし状況次第です」**となります。豊かな美食の都パリも、一旦危機に陥れば人々は生き延びるため手当たり次第に食料を求めました。飢餓と戦争という極限の中で、普段は忌み嫌うネズミさえ命をつなぐ糧となり得たのです。それは決して狂気ではなく、人間の持つ適応力と執念の証でもあります。一方で現代の私たちは、スマートフォンで食事の出前を注文し、飽食の日々を当たり前のように送っています。そんな私たちの足元の地下では、今も変わらずネズミたちが生き抜いています。もしタイムスリップして19世紀のパリを訪れることがあれば、夕食に出されたシチューの肉が何なのか、少し勇気を出して尋ねてみる必要があるかもしれませんね…。現代の豊かさに感謝しつつ、歴史の一幕としてパリのネズミ食の物語を記憶に留めたいと思います。


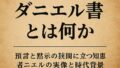
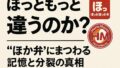
コメント