デスクの上のiMacには『ブレードランナー2049』が流れている。ジョニーウォーカー12年は高くて買えない。代わりに赤いラベルの安ウイスキーをロックグラスに注ぎ、キャラメルコーンをつまみにしながら考える。
「我思う、ゆえに我あり」。この有名な命題を、もっと簡潔に言い換えてみたい。
「在る」と「認識」する「自己」在り。
小難しい哲学用語や詭弁を抜きにして、この一点だけに集中してみたい。
◯ブレードランナー2049→【ブレードランナー2049】鑑賞直後レビュー・個人評価および感想
構成
では本の全体構成から見てみよう。『方法序説』は、意外にもスタイリッシュで読みやすい。
フランスの思想家ルネ・デカルトによるこの書は、1637年に出版され、全6部で構成されている。100ページに満たないコンパクトな本で、彼の他の著作『哲学原理』『省察』『情念論』『屈折光学』などと同様に、数学好きだった彼の美学が現れている。
「在る」について
『方法序説』は、人生の節目節目で読み返したくなる本のひとつだ。私がこれを読むのは3回目か、あるいは5回目かもしれない。何が真実で、何が虚構なのか分からなくなったとき、「我思う、ゆえに我在り(I think, therefore I am)」という命題がよぎる。
旧約聖書『出エジプト記』では、燃える柴の中から神がモーセに語りかける。「モーセ、モーセ」。モーセは答える「ここにいます(Here I AM)」。そしてモーセが神に名前を問うと、神はこう答える。「私は在る、という者である(I AM Who I AM)」。
「在る」ということそのものに、真実のすべてが凝縮されている。哲学者プラトンも「在る」とは何かを延々と語り続けた。
◯プラトン→哲学者【プラトン】対話編〜レビュー・解説まとめ
虚無について
では「在る」の反対、「無い」とは何なのか。虚無とは、そもそも「存在しない」からこそ“無”なのだ。
しかしその「無」が全存在を包むほどの無限だとしたら?存在自体の無限とはどう整合するのか?――このような逆説は、プラトンも挑んだテーマだった。
内容と読みどころ
『方法序説』における名言「我思う、ゆえに我在り」が登場するのは第4部だ。それまでの第1〜第3部は、デカルトによる自伝的経緯の記述が多く、ブログのような読み味すらある。
第4部で思考の拠点となる命題が示され、第5部では心臓の構造と機能が科学的に語られる。さらに興味深いのが第5部後半の「自動人形」に関する話である。
なお第6部は、後続の大論文に向けた序文的な意味合いを持っており、当初出版時には『屈折光学』『気象学』『幾何学』が付録として収められていた。
「我」の実体とは
第4部において、デカルトは「我」の本質を「考える存在である」と断言する。身体をもたない「思考する実体」こそが「自己」なのだと。
だが、この結論を腑に落とすには時間がかかる。私たちは普段、「自己」とは身体を含むと考える。喜怒哀楽を持ち、飢えや痛みを感じる「我」は、どうして「身体なき実体」なのだろう?このズレこそが、デカルト哲学の面白い難しさである。
自動人形とアンドロイド
第5部では心臓のポンプ作用や血液循環を科学的に解説したうえで、動物を「自動機械」として扱う比喩が登場する。ここでデカルトは、人間にそっくりの機械を作ったとしても、本物との違いは明らかだという。なぜなら、機械には人のように「言葉を話す力」がないからだ。
この議論は、まさに現代のAIやアンドロイドを予言していたかのようだ。21世紀の私たちは、スマホやインターネット、そしてChatGPTのような存在と日々接している。デカルトの予想を、現代の技術が遥かに超えてしまったとも言えるだろう。
⚫デカルト関連記事→デカルト名言集【方法序説】思想についてのまとめ
◯まとめ記事→【ルネ・デカルト】の本〜感想・レビューまとめ
まとめ:デカルト的思考と現代の「我」
『我思う、ゆえに我在り』――この言葉に含まれるのは、揺るがない存在の証明であり、現代に生きる私たちにとっての出発点でもある。
自分が「在る」と気づくこと。そこにすべてが始まる。
だからこそ、この本は今でも読み返す価値がある。短いけれども、読むたびに何かが変わる一冊だ。

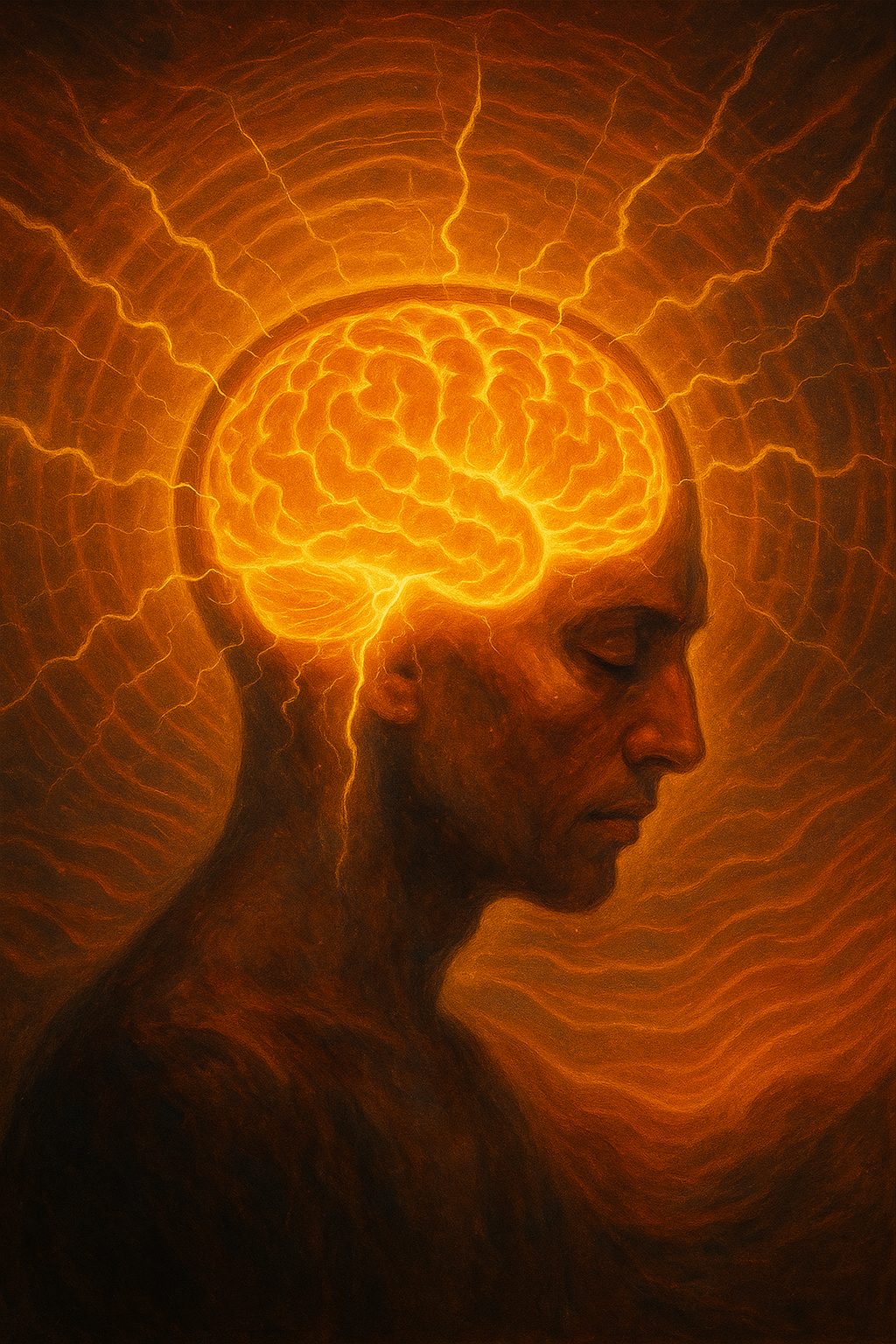


コメント